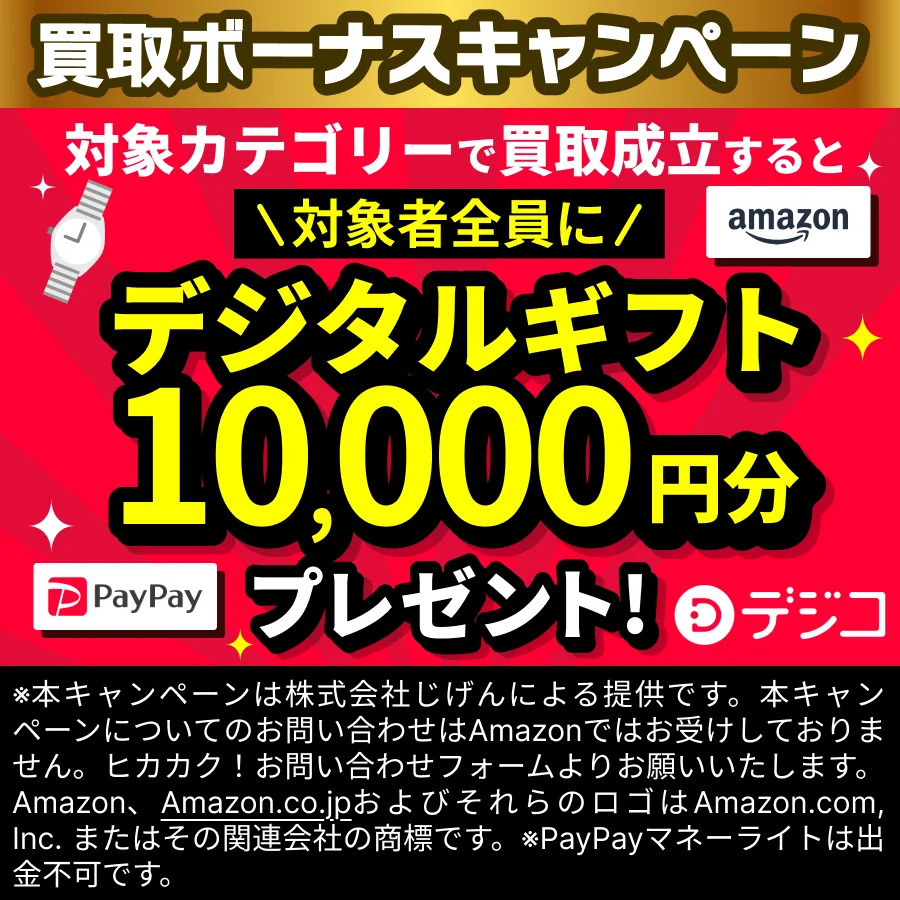近ごろ、ミニマル(必要最小限)な暮らしが注目を集め、モノやコトに囲まれない生活がいかにメリットが多いのか、広く認識されるようになってきた。ミニマリストなる者も出てきて、価値観が大きく変わりつつあるようだ。
そんな中、中高年にスポットをあてた「生前整理」や「老前整理」という考え方が生まれ、次第に浸透しつつあるように思える。

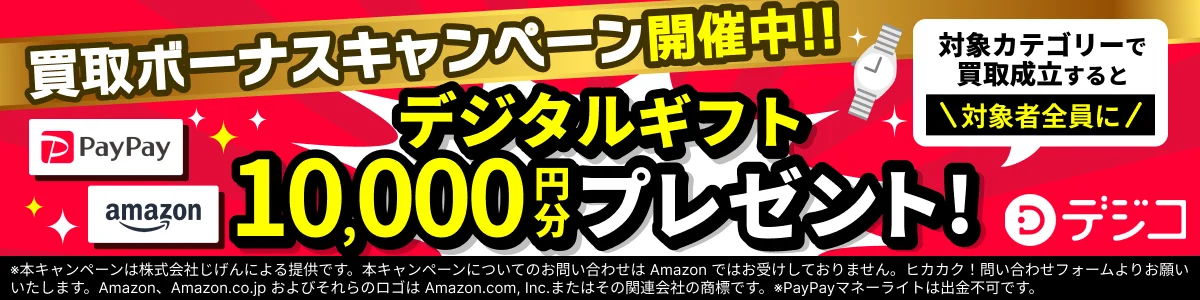
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
生前整理とは?
生前整理とは、読んで字のごとく、生きているうちに行う整理のことだ。もう少し具体的にいうと、死んでしまってから遺族に迷惑をかけないように、あらかじめ整理しておくことをいう。
一般的に、誰かが亡くなると、遺族にかかる負担は小さくない。一つに財産の適正な分与(いわゆる相続)、そして遺品の整理や諸手続きが待っている。
例えば、一口に財産といっても、現金から預貯金、有価証券や債権、動産から不動産と、さまざまな形に変わっているのが通常なので、本人ではない遺族が完全に把握するのは難しい。特に、負債(未払金や借金など)がある場合は、ことさらに問題が大きくなる。
見た感じ、預貯金や家があるからといって嬉々として財産を相続したはいいが、実は被相続人には負債もあったというのではたまったものではない。当然、プラスの財産を相続してしまっていれば、マイナスの財産も相続することになり、マイナスの方が大きければ悲劇だ。こういった事態の発生を防ぐために、生前整理が担う役割は非常に大きい。
また、遺族にとって、遺品の片付けは非常に大きな負担となることがある。特に独居であった場合には、家具や家電、あらゆる持ち物を片付けなければならず、手間も時間も、場合によってはお金もかかることになる。
これに加えて、もし賃借住居に住んでいた場合なんかには、退去日というデッドラインもあるだろうから、遺品整理もラッシュで行わなければならない。
その他、遺族による諸手続きの負担を軽くするためにも、モノだけではなく、コトも整理しておくことが推奨される。どのような契約をしているのか、どのようなサービスを利用しているのかなどを明確にしておく、場合によっては、あらかじめ解消しておくことで、遺族は非常に助かるのだ。
このように、自分があちらの世界に旅立つ前に身の回りのモノやコトをしっかり整理しておくと、遺族に迷惑がかからない。日本人は人に迷惑をかけたがらない国民性であるので、生前整理が浸透してきているのも頷ける。
老前整理とは?
生前整理と似たようなものとして、老前整理がある。こちらも読んで字のごとく、老いる前に行う整理のことだ。
生前整理と老前整理の大きな違いは、その目的にある。生前整理が遺族の負担を緩和するために行うものである一方、老前整理は自分がより良い老後を過ごすためのものだ。前者は人のために、後者は自分のために。「人生100年時代」を生きる我々にとって、老後のセカンドライフはとても長く、充足させる甲斐は十分にあるものだろう。
人は、歳を重ねると共に、体力も「脳力」も衰えていく。片付けは体力や力を使うことはもちろん、意外と頭も使うものだ。そのため、よくあるケースではあるが、退職後に心機一転して身の回りを片付けようと思っても、まったく片づかないということが多いのだ。
そんなことにならないよう、老いる前に、具体的には40代、50代、60代のうちに、モノやコトを処分したり清算したりすることが推奨されており、あるいは常にミニマルな考えをもって片付ける習慣をつけておくことが望ましいともいわれている。
生前整理、老前整理のやり方は?
生前整理や老前整理は、それぞれが置かれた環境によって、どのように進めるべきか異なるため、「絶対にこうしなければならない」という決まりはない。あくまでそれぞれの目的を見据えて、マイペースで行えば良いのだ。
とはいっても、整理は簡単そうにみえてなかなか進まない。特に、捨てるに捨てられないといった呪縛から逃れるのは、なかなか難しい。片付けの第一人者ともいえる近藤麻理恵さんの著書「人生がときめく片付けの魔法」が世界中で大ヒットしたことから、片付けたくても片付けられないというのは世界共通の難題であることがわかる。
片付けるコツ
片付けを予定に入れておく
多くの人は、片付けは適当な時間に気の向くまま行うものだと考えている。しかし、片付けをタスクとして予定に入れておくことで、片付けに意欲的に取り組むことができるのでおすすめだ。例えば、「次の土曜の朝から昼まで、床の間の押し入れを片付ける」と具体的に計画しておくことで、片付けはとてもはかどるものだ。
片付けに必要なモノはあらかじめ用意しておく
ゴミ袋や軍手、場合によっては工具など、片付けている過程で必要になるものは、片付けを始める前に必ず用意しておこう。片付けている途中で、やれゴミ袋はどこだ、やれ軍手はどこだ、やれドライバーはどこだといちいち探していては非効率的だし、見つからなければどんどん意欲が削がれていくことになる。
なお、ゴミ袋はスーパーでもらってくる大きめの袋ではなく、しっかりとした45リットルぐらいの大きさのゴミ袋を用意しておこう。また、1枚や2枚でなく、多めに用意しておこう。ゴミ袋がなくなると、その時点で片付け終了となってしまうからだ。
要るモノと要らないモノに分ける
片付けで最も難しいのが、要るモノと要らないモノに選別することだ。もったいない精神が出てしまうと、これもいる、それもいる、あれもいるとなってしまい、まったく片付かないことになる。そんな場合は、家族や友人に立ち会ってもらい、自分がどう思っているのか聞いてもらったり、客観的なアドバイスをもらったりするとよいだろう。
例えば、書類であれば3年以上の前のモノは処分する、服であれば昨年着なかったモノは処分するといった具合に、それぞれ処分する基準を設けて選別するのがおすすめだ。
また、選別するときには、いったん全て荷物を出してしまったほうがよい。一度要るモノに選別したところで代用品が後から出てきて、やっぱり要らなかったとなってしまっては、選別も効率的に進まなくなるためだ。
思い出の品は最後に手を付ける
思い出の品は、片付けの大敵だ。例えば、写真。昔の写真が出てくると、ついつい見入ってしまい、片付けの手が止まる。こんな経験はないだろうか。思い出の品は、選別も大変なうえ、作業の手が止まってしまうので、片付けの最後に行うのが望ましいだろう。
要らないモノは早急に処分する
片付けで発生した要らないモノは、早急に処分するようにしよう。例えば本、本は捨てようと思って出していても、ふとページをパラパラめくっていると、だんだんと読んでしまう。すると、やっぱり捨てるのは忍びねぇ・・などと、トータルテンボスみたいなことを言ってしまうのだ。
そのため、次の回収日には捨てられるよう、縛るなり、玄関近くに出しておくなりしよう。 また、粗大ゴミについては、通常、回収依頼が必要になる。回収依頼も面倒くさいと感じてしまうかもしれないので、処分すると決めたのなら、その場で回収依頼するようにしよう。
今日、多くの自治体ではインターネットで簡単に申し込めるようになっているので、億劫にならないでほしい。
売る
今や、ほとんどのアイテムは売ることができる。業者に買い取ってもらうこともできるし、フリマアプリやネットオークションを利用して売ることもできるのだ。「押入れの整理」を「埋蔵金発掘」と考えると、モチベーションもすこぶる上がるので、ぜひお試しいただきたい。
また、実際のところ、タンスの肥やしになっているような不用品がある場合には、売ってしまうのが、片付けにとっても家計にとっても嬉しいところだろう。もし、大量に売れそうなモノがあるのなら、業者に出張買取を依頼するのがおすすめだ。
参考になるブログはある?
今では、さまざまな人がブログを書いており、生前整理や老前整理、片付けについて知見やノウハウを公開している。ここでは、いざ整理や片付けを行うにあたって、参考になりそうな、収穫のありそうなブログについて紹介しよう。
幸せ住空間セラピスト「古堅純子」オフィシャルブログ
幸せ住空間セラピストとして、整理や収納、片付け、掃除など、多くの著書もある古堅純子さんのオフィシャルブログは、生前整理をするにも、老前整理をするにも、ぜひ目を通してもらいたいブログだ。笑顔でハッピー、幸せであることをモットーとしているような方なのか、とても前向きに整理を始めてみようとなれる。
生前整理をテーマにした記事の中に、印象的なところがあったので紹介しよう。モノの要不要は、あくまで所持している人が決めることであって、外野が「これ要らないんじゃない?」と促すのはタブーということだ。
捨てる事を前提として話をするのではなく、なぜそれを大事にしているのか、理由を聞いてあげることが大切だと説いている。所持している人からすれば、その理由を一通り話したところで、「やっぱり要らない」と結論を出せたりするのだそうだ(2018年6月11日「生前整理」記事 より)。
生前整理ブログ 山崎由香のHappyLifeブログ
掃除マイスター1級認定講師、片付け収納マイスター1級認定講師、5Sインストラクター認定講師、生前整理アドバイザー1級、生前整理アドバイザー認定指導員、おまけに遺品整理士という肩書を持つ山崎由香さんのブログには、掃除や生前整理などの片付けに関するノウハウがまとめられているので、ぜひ一読してほしいと思う。
こちらもハートフルな内容が印象深かった。例えば、実家(親)の家を片付けるのに、ついつい出てしまう「片付けてよ!」「早くしてよ!」「こんなもの捨ててしまったらいいのに!」といった言葉。このような言葉を向けられたら、心が寂しくなってしまう。
そうではなく、「一緒に片付け手伝うね」「何か困ってることはない?」「本当に大切なものは なに?教えて」と、あたたかい言葉をかけてあげれば、心が動いてくれるはずと。親の思いに耳を傾けることが、スタートだと説いている。
プロというのはノウハウがあるだけではなく、ヒト本位な考えがしっかりとできているようだ。
実家断捨離ブログ 捨てられない母とミニマリスト娘の攻防戦
捨てられない母とともに実家(汚部屋)の片付けに奮闘するミニマパッカーこと吉永ケイさんのブログは、リアルな感じが共感を呼ぶ。写真つきで何をどうしたのか、何をどうすればよいのかがわかりやすく掲載されていて、一見する価値はあるだろう。
汚部屋であることのヤバさや生前整理を進めないとマズイ理由にも説得力があるので、特に片付けが難航している人や汚部屋住人におすすめだ。
「遺品整理ブログ 祖父の荷物に10年かかった思わぬ理由」を読むと、遺品整理の大変さ、生前整理の大切さがよくわかる。
片付けトントン 片付けブログ
愛知県の整理業者「株式会社中西」のウェブサイトには、片付けブログという直球の名前のブログが掲載されている。専門業者による専門ブログということだけあって、ノウハウが実に役に立つので、見て損はないだろう。
また、ブログは漫画や画像でわかりやすくまとめているので、サクサク「ふふ・・」といった感じに軽く読み進めることができる。人寄せに作ったブログではなく、楽しいから作っているブログのような印象を受けた。
まとめ
生前整理、老前整理は簡単にいえばヒトをハッピーにするものなのかもしれない。これらに取り組む人達が書いたブログを読むと、究極的にはそこに行きつくような気がしてきた。
手際よくスムーズに整理を進めるためにもノウハウがあるが、ただ漠然と片付けるよりも、自分がハッピーになる、遺族がハッピーになる、そんな風に考えるようにすれば、きっとモチベーションも維持でき、整理も進むのではないだろうか。
先に紹介したブログの他にも、生前整理や老前整理、断捨離や片付けをテーマとしたブログはたくさんあるので、いろいろ目を通して、知識や共感を得てみてはいかがだろうか。