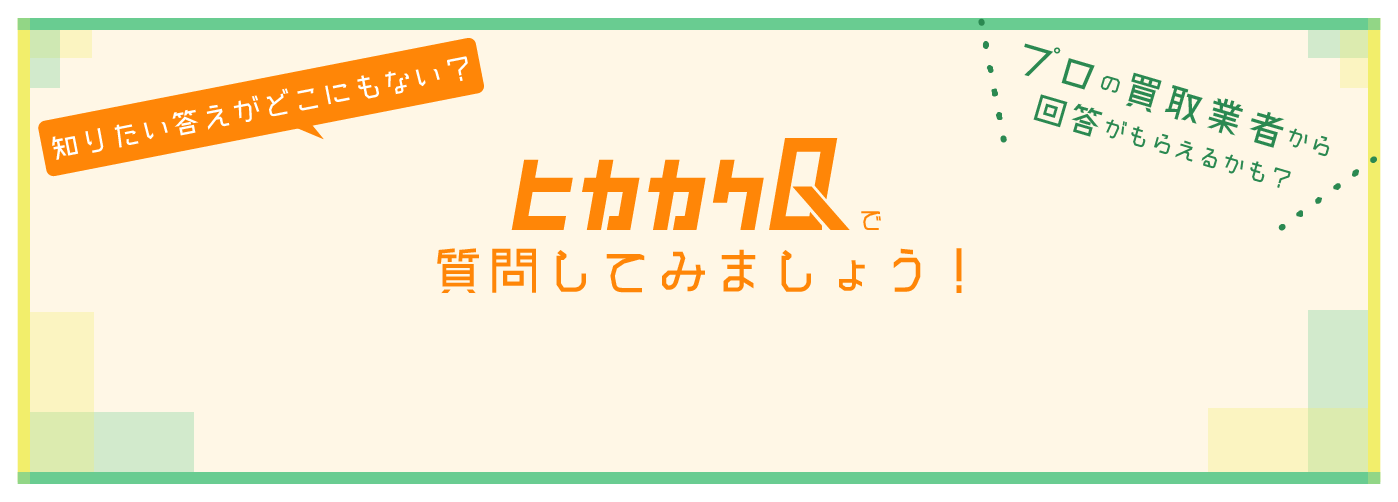シングルマザーになることで受けられる支援や手当を知りたい
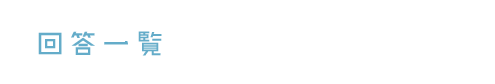 3/3 件
3/3 件
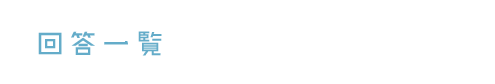 3/3 件
3/3 件
2019/01/22
離婚をしてシングルマザーになる人、未婚のシングルマザー、どちらも年々増えています。 一昔前はシングルマザーというと世間体的に良く思われない社会背景がありましたが、現代社会では珍しいものでもなく、法的にも積極的にシングルマザーへの支援がある体勢になってきています。 シングルマザーになると基本的な助成金のほかに「7つの割引制度」が受けられます。しっかり把握して申請を行うことで、シングルマザーでも暮らしやすい環境を手に入れることができます! ※シングル世帯の基本的な助成金 ・児童手当 ・児童扶養手当 ・児童育成手当 ・特別児童扶養手当 ・乳幼児・義務教育未就学児童の医療費の補助 ・ひとり親家庭等医療費助成制度 ・遺族年金 ・生活保護 ◆7つの割引制度 ① 税金の免税制度 所得税や住民税の減免を受けられます。単身の親、生計を共にする子供がその子の総所得が38万円以下、合計所得が500万円以下であれば…住民税から26万円、所得税から27万円の控除が受けられるようになります。 ② 保険金や年金の免除 国民年金や国民健康保険が免除されます。所得が少ない人は年金保険料の全額、もしくは半額を免除できる制度があります。所得が基準以下であったり、収入が大きく減少した場合には、国民健康保険料を減免できる可能性があります。(詳細は区市町村へお問い合わせください) ③ JRなどの交通機関割引 母子・父子家庭はJRや公共バスの割引があります。JRの通勤定期は3割引きで購入でき、公共バスの料金は割引、もしくは無料になります。ただし児童扶養手当を受給している世帯であることが条件なので、きちんと手続きが必要になります。 ④ ごみ処理の減免制度 粗大ごみ等、ごみ処理を行う際に発生する手数料に関しては、児童扶養手当を受給している世帯の場合減免される制度があります。 ⑤ 上下水道の減免制度 児童扶養手当などシングルとしての助成を受けている世帯であれば、水道基本料金もしくは水道料金の一部が免除されることがあります。対象になる明確な条件は公表されていませんが、対象とされるかどうか自治体に相談してみる価値はあるでしょう。 ⑥ 非課税貯蓄制度 元本350万円までであれば、国債や地方債などの公債、預金、郵便貯金の利子所得で課税となる所得税と住民税を非課税にできます。所得税は通常15パーセント、住民税は通常5パーセントを非課税にできる制度になっています。 ⑦ 保育料免除・減額 自治体ごとに保育料の免除・減税があります。母子家庭を支援するための制度です。

2019/01/21
シングルマザーが受けられる支援や手当としては、主に下記があります。 ◆児童扶養手当 一人親家庭を対象に、国から支給される手当です。 「母子手当」という言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、それはこの児童扶養手当を指します。 支給される額は親の所得やお子様の人数により異なります。下記に例を示します。 お子様1人:月額42,500円~10,030円 お子様2人:月額52,540円~15,050円 ◆児童育成手当 お住まいの自治体から支給されます。 支給されるかどうか、支給される場合の金額はお住まいの自治体により異なります。 またこちらも児童扶養手当と同様に、所得によって支給有無や支給額が変わります。 一例として、一人親家庭でお子様が18歳になるまで、1人につき月額13,500円を支給するという自治体が多いようです。 自治体に問い合わせてみると良いでしょう。 その他、中学卒業までもらえる「児童手当」や、心身に障害がある場合の「特別児童扶養手当」などは、通常通り支給されます。 ◆一人親家庭の住宅費助成 自治体によって、一人親家庭の住宅費(家賃など)を助成する制度を持っているところがあります。 支給条件などは自治体によって個別に設定されていますので、こちらも確認することをおすすめします。 ◆一人親家庭の医療費助成 こちらも各自治体の取り組みとして行われています。 各自治体ともに、最近では中学生まで自己負担無料、高校生まで自己負担1回500円など、多大な支援をしているところも多いですが、一人親家庭に対してはさらに手厚い補助が受けられる可能性があります。 ◆所得税、住民税の減免制度 一人親で、総所得金額が500万円以下の場合は、所得税と住民税からそれぞれ控除を受けることができます。 ◆JR定期券割引 扶養者がJRの通勤用定期乗車券を購入する際、3割引で購入することができます。 事前に各地域の福祉事務所で手続きをする必要があります。 (なお対象は通勤用定期のみです。お子様の通学用定期の割引はできません) その他、ごみ処理手数料、上下水道、保育料などが減免になる自治体もあります。 おおむね以上となります。 それぞれの助成金などは、条件が自治体によって異なるものがほとんどです。 支給漏れなどで不要な支出とならないよう、各自治体の市民生活課などに相談してみると良いですよ。

2019/01/21
・児童扶養手当:地方自治体から、子供が18才になった年度末まで支給されます。 ・児童手当:児童扶養手当とは別に、児童手当(旧名称は子ども手当)はひとり親家庭だけでなく全家庭を対象とした国の支援制度です。 ・自治体によっては家賃補助・住宅手当を行なっているところもあります。 ・医療費助成制度:自治体ごとに行なっているひとり親家庭への支援制度で、18才未満の子どもの医療費が無料になります。 ・寡婦控除:納税者自身が寡婦と認められた時に受けられる所得控除の事です。 母子家庭の場合には 特定の寡婦と認められることがあり、通常の控除に加えて更に控除額が上乗せされることもあります。 ・国民年金と国民健康保険の免除は 収入が少ないなどの理由で受けられることがあります。 ・保育料の免除と減額がありますが、自治体によって異なります。 ・JRなどの交通機関では ひとり親家庭を対象にした割引制度があります。 ・自立支援教育訓練給付金:雇用保険の教育訓練給付金が受けられない人が対象です。経費の20パーセントが支給されます。 ただし教育訓練を受講・終了させる必要があります。 上限もあるのでお住いの市役所か区役所へご相談ください。 お母さんとお子さんが安心して生活していくためにも、これらの支援や手当は必要不可欠だと思います。 なので最初は手続きが大変だと思いますが、今後の安定した生活のためにもぜひこういった支援への申し込みをしてください。 市が毎月発行する広報新聞にも有益な情報が載っていることがあるため、毎月欠かさずチェックしてください。 それと、やはり自分から役所へ問い合わせるなど働きかけることもポイントです。自治体によって制度も内容も変わりますので、上記であげた支援制度以外で受けられるものがあるかなど、積極的に問い合わせられることをおすすめします。 役所にまめに足を運ぶことで、掲示板などに掲載されている有益な情報を入手することもできます。 支援制度以外でも、母子家庭問わずお子さん向けの無料の催し物やサービスなどの情報が得られますので、役所を上手に活用してください。 お母様とお子さんの幸せを心から願っております。
関連する質問
 Q買取に関わる入金方法について
Q買取に関わる入金方法について受付中!
回答数:3でつ子2018/07/08 Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?
Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?受付中!
回答数:4一条冬華2018/07/08 Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問
Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問受付中!
回答数:2匿名希望2018/08/09 Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?
Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?受付中!
回答数:4w2541607672018/08/31 Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?
Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?解決済み
回答数:4ぬんぬん2018/09/05