
最大20社の買取額をかんたん比較!
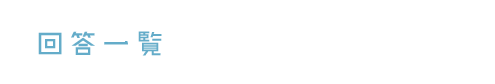 3/3 件
3/3 件
2019/02/23
相続不動産は、自分が使用しなければ売却を検討することもあると思います。そこで知っておきたいのが、相続した不動を売却した際の税金についてです。以下、ポイントを簡単にまとめますので、参考にしてみてください。 1.相続した不動産をそのままにしておくことのデメリット 相続した不動も活用しなければ宝の持ち腐れです。将来的に自分で不動産を使用することや、貸家として他人に貸すことをせず、そのまま放置しておくのであれば、売却してしまった方が望ましい場合もあります。 (1)固定資産税がかかる 土地や家屋、事業をしていれば有形の固定資産に、毎年固定資産税が課せられることになります。不動産を相続するということは、当然不動産が建っている土地も相続することになるケースの方が多いので、毎年土地と家屋分の固定資産税を払わなくてはなりません。固定資産税は「固定資産の評価額×1.4%分となります。 (2)不動産の価値が下がってしまう 不動産をそのままにしておくと、建物の老朽化などが進み不動産としての価値も低くなります。売却するときに不動産を譲渡されたときの価値よりも低くなっているケースも多く見受けられます。 2.相続した不動産を売却した際の確定申告 相続した不動産を売却して利益を得た場合、確定申告の必要があります。確定申告を行う場合は通常の「申告書B第一表」と「申告書B第二表」と一緒に、「申告書第三表(分離課税用)」と「譲渡所得の内訳書」の作成が必要です。 (1)申告書第三表(分離課税用)と譲渡益 譲渡益を得た場合に関わってくる欄は、収入金額・所得金額の分離課税の部分です。不動産の場合は、分離課税の短期譲渡か長期譲渡の一般分に分類することができます。また、収入金額と所得金額の他に、税金の計算欄も記載する必要があります。 (2)譲渡所得の内訳書 譲渡所得の内訳書は、売却した不動産の詳細や金額を明確に記載するためのもので、これを元に申告書の所得金額等が明確になります。 3.相続した不動産を売却した際の税金 相続した不動産の譲渡により利益を得た場合、所得額に応じて所得税と住民税が加算されます。課される所得税や住民税の税率は、不動産の所有期間の長さによって変化します。また、課税の対象は日本だけでなく海外に所有する土地や家屋も含まれます。 (1)課税譲渡所得 税金は、譲渡で得た収入全てにかかってくるわけではなく、「課税譲渡所得」課せられます。「課税譲渡所得」とは、売却で得た収入から取得の際にかかった購入費用や仲介費、一定の控除額を引いたものです。 (2)短期譲渡所得 短期譲渡所得は、土地や建物の所有していた期間が5年以下の場合を指します。評価の期間は、売却した年の1月1日が基準になり、短期譲渡所得の場合、課税譲渡所得に対し所得税が30パーセント、住民税が9パーセントそれぞれ加算されます。 (3)長期譲渡所得 長期譲渡所得は、土地や建物の所有期間が5年を超える場合で、所得税15パーセント、住民税5パーセントがそれぞれ課税されます。

2019/01/24
相続で土地や建物を得たとしても、かならずしもその土地が必要とは限りませんよね。自分で住むような立地ではないし、かといってアパートにも駐車場にするにも適していない。 そういった場合は、売却することがたしかにベストです。土地は保有しているだけで維持費に固定資産税にと、いろいろ費用がかさむものですから、いつまでも持っているよりも早く手放した方が得策でしょう。 ただし、不動産を売却したときには税金がかかってしまうので、そのことをよくしらないと痛い目にあってしまうかもしれません。 具体的にどのような税金がかかるのかと言うと、まず譲渡所得という物があります。これは購入した金額よりも、売却したときの利益が大きいときにかかる税です。 たとえば五千万で購入した土地が七千万で売れたら、二千万の利益がでますよね。その利益である二千万円には所得税と住民税が課せられます。これは相続された土地にたいしても適用されるので、気をつけてくださいね。 そしてなんと、土地を売却した際には、思いっきり税金がかかってしまいます。 たとえばマイホームのために購入した土地の場合は、売却した際に税金が抑えられるような特例が用意されています。しかし、ただ単に土地を売る場合、そういった特例はまったく用意されていません。 この税金を軽減させるには、その土地の取得費を知る必要があります。取得費とは、その土地や建物を購入した際の価格にプラスして、建物を建築した際にかかった費用と、リフォームしていればその費用を合計したものになります。こちらを知っておくことで譲渡費用を抑えることができます。 また相続申告期限から三年以内の売却でも節税になるので、売却するなら早めに越したことはありません。 確定申告ですが、譲渡所得は事業所得や給与所得といった総合課税とは少し違います。分離課税と言って、別で税額を計算することになります。 つまり確定申告では、通常の第1表でも第2表でもなく、分離課税用の第3表というのを用意し、譲渡所得の内訳書と一緒に作成します。 住民税に関しては、納税通知書と納付書が来るので、期限内に支払えば大丈夫です。

2019/01/23
相続により土地を手にした場合、現金化することも考えますよね。 そのとき相続した土地の売却方法や土地を売却した際の確定申告の仕方を下にまとめますので、参考にしてください。 【相続した土地の売却方法】 相続した土地に家を建てたり賃貸に出さない場合は、固定資産税などの維持コストがかかるため売却する方が金銭的には良いですよね。 土地を高く売る方法としては、不動産売却の比較サイトを使うのがオススメです。 このサイトを使うことで、数ある不動産買取業者の中で最も高値で取引できる業者が見つかるはずです。 私がススメておいてなんですが、比較サイトに盲目的に従うのもいいですが、1つご自身の中で基準になる価格を作られるのも良いと思います。そういった基準になる価格があると、比較サイトで提示してもらった金額と比較することができるので、売却価格が出てきた時に迷わずに済んだりしますよ。 その基準になる価格は国税庁の出している路線価と国土交通省が出している公示価格です。この地価は、1年に1回、国が出しているものなので信ぴょう性の高い物になります。 基準になる価格があると、判断もしやすくなるのでお時間があれば一度目を通してみるといいかもしれませんね。 国税局 路線価URL:http://www.rosenka.nta.go.jp/ 国土交通省 公示価格URL:http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/Ari... 【土地を売却した際の確定申告】 土地を売却した際は、確定申告をしなければなりません。 なぜなら、給与以外の所得が手元に入るからです。給与は普段会社で源泉徴収されているので所得税を考える必要がありませんが、土地を売却したときに出た所得は、普段会社でされている源泉徴収がされていないものになります。 なので、会社にかわりご自身で所得税を納めなければなりません。 その手段が確定申告というものになります。 しつこくなってしまいましたが、確定申告の方法は以下になります。 なお、社会人で年末調整がされている前提でお話ししますね。 ①源泉徴収票、住民税の支払調書、土地の売買契約書の用意 ②確定申告申告書を作成(下のURL通りに作成してください) ③確定申告書を所轄の税務署職員へ提出 ※e-Taxを使うことでオンラインで確定申告書を提出することが可能 国税庁HP 確定申告書作成コーナー:https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm ※e-Tax:http://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html なお、土地の所得税の計算方法は以下になります。 ・(土地取得価額+取得費用-売却費用)×15%もしくは30% この15%と30%の違いは、取得から5年経過したかどうかになります。 経過した場合は15%で、未経過の場合は30%になります。 土地の売買には、軽減税率など色々な特例があるので、できれば税務署へ行き、税務署職員と内容把握をしながら申告書を作成するのが間違いがなくて理想になります。 ですが、もしお時間がない場合は、e-Taxでのオンライン提出になります。e-Taxは間違いが起きやすいため慎重に確定申告を行ってくださいね。
 Q
Q受付中!
 Q
Q解決済み
 Q
Q受付中!