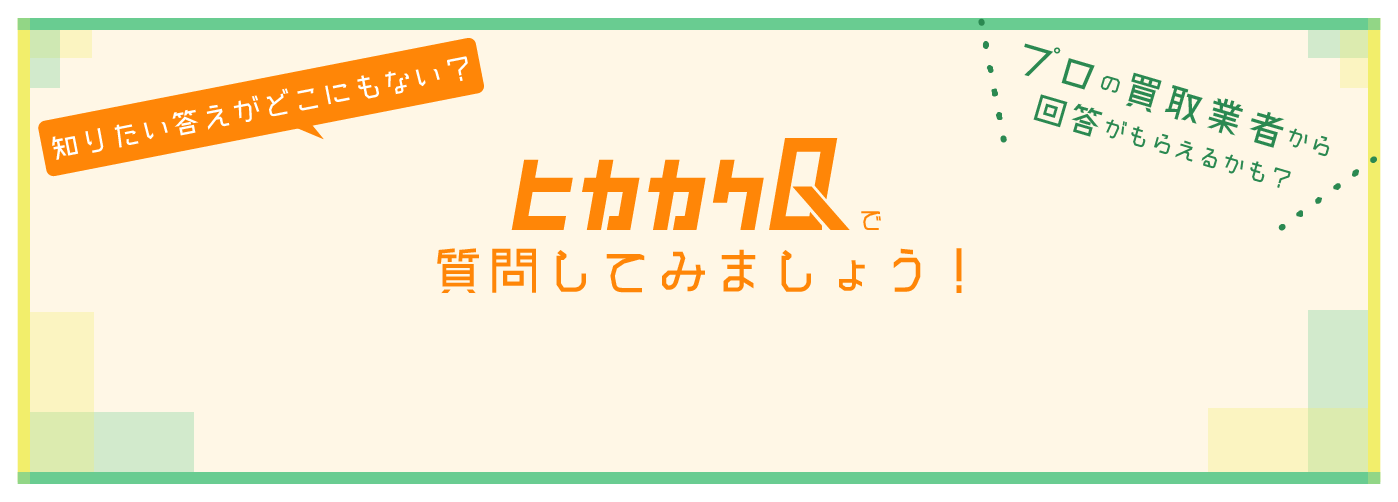タイに移住した場合、社会保険料の支払いはどうなるか?
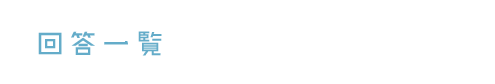 5/5 件
5/5 件
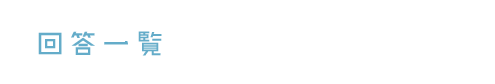 5/5 件
5/5 件
2019/02/10
タイの社会保険は、会社に勤めている人が加入できるものしかありません。 日本にある国民健康保険のようなものはありません。 タイで仕事に就けば、医療の保険と年金保険、また失業保険に加入することができます。タイ人ではない日本人でも、勤務している人は全員入ることができます。 ◆医療保険 個人が負担する額は給与の5%です。 全額会社が負担してくれるという会社もあります。 加入すると、通院や手術が無料になったりします。 とてもいい保険のように思えますが、タイに住む日本人が実際にこの社会保険制度を利用することはほとんどありません。 理由は指定された病院でしかその保険が適用されないからです。 タイで社会保険が利用できるのは指定の病院だけです。指定の病院は、タイのローカル病院だけです。日本語や英語で診察を受けることができる病院や医療水準が高い病院では社会保険が適用されないのです。 ですが会社によっては独自の医療制度を福利厚生として取り入れている会社もあります。 指定の日本語が通じたり、医療水準が高い私立病院での治療費を全額負担してくれる会社もあるのです。 ◆年金保険 タイの年金は、納付期間が15年以上ならば年金を毎月受け取ることができます。 納付期間が15年未満の場合は一括で受け取ることになります。 満55歳以上で、仕事をしていなければ、年金を受け取ることができます。 ですが受け取れる金額はとても少ないです。 タイに住みながら日本の年金制度を利用することもできます。 日本の国民年金は、「日本国内に居住する20歳以上60歳未満の者」に適用される年金制度です。 なので、現在の法律では「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満の者」は任意加入することが認められているからです。 タイで働いていても、任意加入で日本に保険料を収めていればそ年金を受け取ることができます。 ですが、日本の年金の納付額が月1万5千円くらいと考えると、タイの物価からするととても高額になることも考える必要があります。 ◆失業保険 タイで失業保険を受け取る条件は、継続して6ヶ月以上保険料を払っていることです。もしくは直近の15ヶ月以内に計6ヶ月以上の保険料を払っていることです。 ビザや労働許可証についても厳しくチェックされるそうです。

2019/02/03
タイへの移住を考えているのですね。確かに、移住したあとの保険については迷うことも多くあります。日本の制度とは違う訳ですから、それも仕方のないことなのです。では、タイへ移住してそのまま現地で仕事に就くという前提で、どのように社旗保険を支払っていくのか解説していきます。 ◇タイの社会保険 タイの社会保険がどのようなものなのか簡単に解説します。ここを知っておくことによって、日本との違いがよく分かると思います。移住したあとに困らないようにしっかりと理解しておきましょう。 ①社会保険参加病院を登録する タイに移住して現地の会社に入社すると、まずは社会保険参加病院から任意で一つ選んで登録しなくてはいけません。ただし、会社の総務が勝手に決めてしまうこともあります。その場合、社会保険カードに病院名が書かれているはずなので確認しておきましょう。初回登録時に、第3希望まで申請可能となっているので、行きやすくて評判の良いとこを選びましょう。 ②保険料は給料の5% タイの社会保険料の自己負担は、給料の5%となっています。ただし、最高でも750バーツの支払いでストップとなります。給料の5%が750バーツを超えたとしても、750バーツしか請求されないので安心してください。基本的には給料から天引きされています。 ③登録した病院での医療費は無料 これは非常に大きなメリットとなります。日本では3割を負担するのが基本となっていますが、タイであれば無料になるんですね。とてもお得なのですが、注意すべき点もあります。それが、とても混むということです。 治療費は無料な訳ですから多くの人が訪れます。すると、自分が診てもらう時間が少なくなってしまいます。緊急時以外は、相当の時間を待つ可能性もあります。さらに、日本ほど医療が発展していないので、少し不安が残ってしまいますね。 ④歯科治療費の限り年900バーツまで請求可能 これもタイならではの制度ですね。そもそも、歯科治療なんて年に何回も行う訳ではありませんし、数年に一回しか歯科に通わない人もいます。それでも、治療したあとに請求出来るのはありがたいことに変わりありません。 ⑤緊急時に限り、登録病院以外で受診しても治療費を後から請求可能 急病であったり、事故が発生したことによって緊急手術などが必要になった場合、どうしても登録病院に間に合わない場合もあります。移動中に容体が悪化してしまっては元も子もありません。そのため、緊急時に限り登録病院以外で受診しても治療費は返ってくるので実質無料になります。 日本と同じように給料から天引きされますが、保証内容はかなり違います。しっかりと覚えておきましょう。
happy-life
2019/02/02
こんにちは。 社会保険ということは、現在は会社勤めおされているということですよね。そちらからの出向でしたら、日本企業勤務のままなので、今まで通り、社会保険を支払うことになります。 退職して移住されるとなりますと、その時点で社会保険はなくなります。 タイに移住する場合に日本で加入している国民健康保険はそのままにしておく場合と、国民健康保険の加入を止める場合とあります。 国民健康保険だけでなく日本の住民票も、もしタイに長期で移住するのであれば抜いたほうが得策です。 もし国民健康保険に加入したままでタイで入院したり手術をした場合には、国民健康保険の国保海外療養費支給制度を利用することができます。 その場合にはまずタイで入院したり、手術をした病院の医療費を自分で支払います。 そして、日本へ帰国した後にタイの病院で発行してもらった領収書を持って市役所で還付の手続きをします。 もうひとつの方法として、海外旅行傷害保険に加入するやり方があります。 クレジットカードの中には海外旅行保険が付帯するものもありますが、これは短期の観光旅行などに限られるので説明は省きます。AIAなどの海外旅行保険に加入していれば、もしタイで入院や手術をしてもキャッシュレスで入院や手術を受けられます。 もし日本で国民健康保険にも海外旅行保険にも加入していなくても、タイで仕事を見つけ現地採用になれば、自動的にタイの社会保険に加入できます。 これは会社の従業員は外国人でも、タイの法律で強制加入が義務付けられています。 タイの社会保険は給与の3%で、最高でも3000バーツ)までで会社と従業員で半々で負担します。 タイの社会保険の他にもタイのAIAでは日本人向けの医療保険を行っていて、どこの病院でも無料で入院や手術が受けられます。 ただし歯の治療だけは例外です。 ご参考になれば幸いです。

2019/02/01
海外の国に移住する、または長期間に渡って海外の国に滞在した場合の保険料について説明します! 1年以上に渡って、海外に滞在したり、海外で勤務したりする場合には、日本で住んでいたの市区町村に対して、「海外転出届」を提出しなければなりません。そして、提出後は住民登録が抹消されます。 これにより国民健康保険や後期高齢者医療のような、公的医療保険の適格者資格を失うので、保険料を納付する必要がなくなります。 保険料を納付する必要がなくなるということは、これらの保険サービスを受けられなるということなので、移住先の民間医療保険や日本の海外旅行保険などに加入して、病気やケガに対処しないといけません。 しかし社会保険は、例出向により、日本の企業との雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合は喪失しません。 出向元の日本の企業が、給与を支払っている場合は、適格資格を喪失しないのです。 少々脱線しましたが、結論としては日本での社会保険料納付義務は一年で無くなります。 参考になれば幸いです。

2019/02/01
タイは気候も温暖で、国民性も朗らか、物価も安く、治安もそこそこいいので海外移住にはうってつけの国ですね。 移住先としての人気も、常にトップ3には入る人気国だと思います。 さてお尋ねの海外移住した場合の社会保険料についてご説明させていただきます。 海外移住した場合に気にしなければならない社会保険は、公的医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険など)、年金、介護保険の3つです。 今回は海外移住ということで、企業の在籍出向などではありませんので、雇用保険についてのご説明は割愛させていただきます。 1 公的医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険など) 公的医療保険は、国内に住所を有することが加入要件となっています。 ところで、1年以上の期間にわたって海外に滞在する場合は、原則としてお住いの市区町村に「海外転出届」を提出しないといけないことになっています。 この「海外転出届」が提出されると、市区町村の住民登録から海外転出を理由としてはその方の登録がなくなります。 1年以内の期間の海外滞在中に、海外の病院などにかかった場合は海外療養費制度というものが使えます。 これは、国内の病院にかかったのと同様、海外の病院でかかった医療費を健康保険から一部(7割部分など)負担し、本人に払い戻すというものです。 今回は移住ということですから、1年以上の期間であると思われます。 「海外転出届」が提出された結果、公的医療保険の加入資格が無くなり、健康保険料を納付しなくてよいということになります。 もちろんその反面で、健康保険に基づく医療費の保障サービス(いわゆる「3割負担」など)は受けられなくなります。 もちろん海外療養費制度も使えません。 また、タイは2001年から通称「30バーツ保険」といういわゆる国民皆保険制度を始めました。 しかし、外国人は残念ながらこれに加入できず、恩恵を受けられません。 医療保険については、お金を払って民間の医療保険に加入することになります。 仮に、タイに帰化して国籍取得した場合は「30バーツ保険」を利用できますが、そこまでおすすめできません。 なぜなら、日本の国民健康保険などと違い、受診できる病院に制限があり、常に混んでいて、医療レベルも低いからです。 現地でも富裕層は、有料の医療保険を使用してハイレベルな医療機関にかかっています。 2 年金 国民年金についても、国内に住所を有することが加入資格要件となっています。 したがって、海外に移住し、国内の住民登録が無くなりますと、国民年金保険料を納付する義務がなくなることになります。 もちろんその反面として、年金保険料を納付しなければ、将来受給する年金に影響します。 年金自体が受給できない又は受給できた場合でも、年金金額が低くなることとなります。 ところで、国民年金には受給するための最低資格期間(10年)があります。 この資格期間は、通常は年金保険料を納付した期間のことですが、実は海外滞在期間もこの資格期間に通算できます。 例えば、保険料納付5年+海外滞在10年などの場合は、最低資格期間10年を満たしますので年金の受給資格が発生するということです。 ただし、受給資格と受給金額の話は別々の話です。 上の例でいいますと、海外滞在中は年金保険料納付がないので、通算15年間全期間で保険料納付した方に比べて、受給金額はとても低くなります。 このような将来の年金受給金額の目減りの不安に備えて、海外滞在中の方などでも加入できる国民年金の任意加入制度があります。 3 介護保険 介護保険も国内住所が加入要件となっています。 40歳以上の方は、介護保険に加入することとなっていますが、健康保険などと同時に徴収されることが多いため、あまり意識されないかもしれません。 しかし、40歳になった時点で天引きなどで徴収される健康保険の金額が増加しています。 これも海外に移住された場合は、加入資格がなくなりますので介護保険料を納付する必要がなくなります。 その反面として、介護保険サービスも受けられなくなる点は他の社会保険と同様です。
関連する質問
 Q買取に関わる入金方法について
Q買取に関わる入金方法について受付中!
回答数:3でつ子2018/07/08 Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?
Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?受付中!
回答数:4一条冬華2018/07/08 Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問
Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問受付中!
回答数:2匿名希望2018/08/09 Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?
Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?受付中!
回答数:4w2541607672018/08/31 Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?
Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?解決済み
回答数:4ぬんぬん2018/09/05