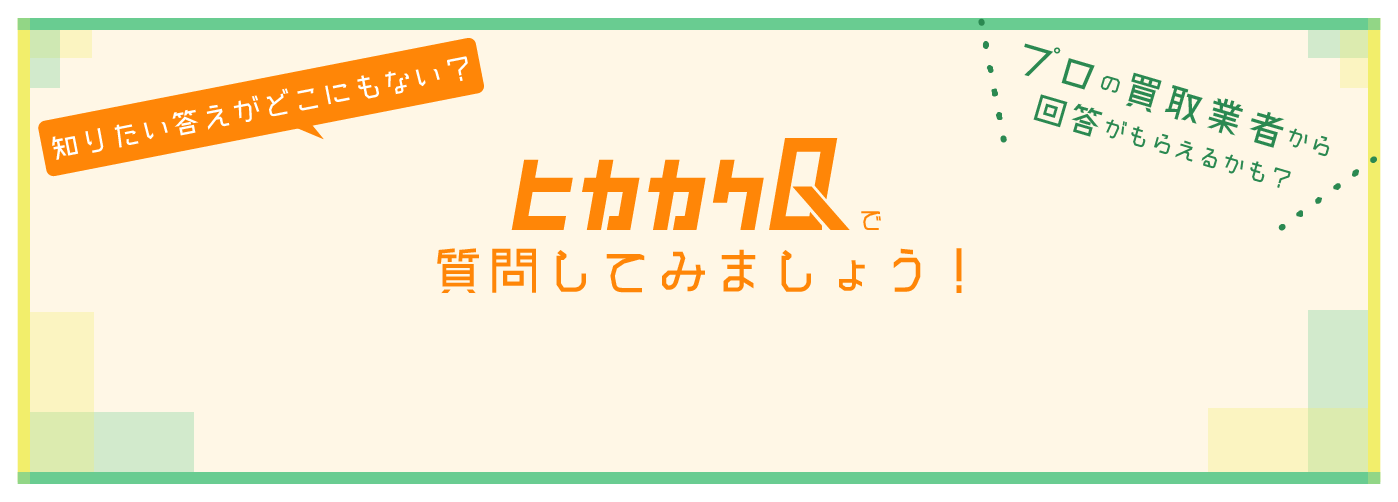信託銀行各行のラップ口座を徹底比較
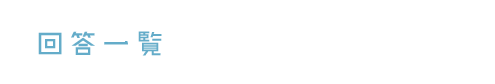 4/4 件
4/4 件
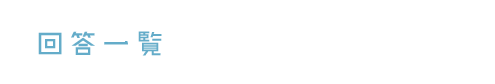 4/4 件
4/4 件
2019/02/18
信託銀行のラップ口座を比較してみると次のようになります。 ・「過去の運用実績」―「全体の手数料」で算出した場合 1:SMBCファンドラップ・・・「年率9.58%」-「1.512%」=「8.069%」 2:三井住友信託ラップ口座・・・「年率6.20%」-「1.512%」=「4.688%」 3:野村ファンドラップ・・・「年率5.93%」-「1.362%」=「4.569%」 4:ダイワファンドラップ・・・「年率4.367%」-「1.512%」=「2.855%」 5:日興ファンドラップ・・・「年率-0.88%」-「1.296%」=「-2.176%」 6:みずほファンドラップ・・・「年率-1.82%」-「1.620%」=「-3.440%」 上記の結果はヘッジファンドダイレクトの発表が基になっています。 参考URL:http://media.yucasee.jp/posts/index/15164 ちなみに過去の運用実勢は、ヘッジファンドダイレクトより発表されている内の長期運用のもので判断されています。 ラップ口座は、ダントツでSMBCです。 続いて三井住友信託になっていることから、三井住友系は強いですね。 ファンドラップ型サービスは、1000万円から3000万円の投資金額が一般的なため富裕層クラスの投資商品として見られがちです。 ただし、契約金額でのラップ口座の場合は、「野村証券」や「大和証券」が力を入れていますね。 どれがいいのかは、実際に各ファンドサービスに相談してみてください。

2019/02/16
ラップ口座とは、投資家と金融機関が契約を結ぶことにより、 管理・売買・投資のアドバイスまでを含んだ資産運用を任せることができる投資一任サービスのことをいいます。 「ファンドラップ」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。 運用対象を投資信託(ETFを含む)に限定しているラップ口座をファンドラップ口座といいます。 このように厳密にはファンドラップとラップ口座に違いはあるのですが、 ラップ口座のほとんどがファンドラップ口座であるため、基本的には同じ意味だと思ってもらって問題はありません。 なので、これから紹介するファンドラップがラップ口座だと考えてください。 信託銀行以外にも証券会社のファンドラップもあるのでそちらも紹介します。 ・野村ファンドラップ 投資一任受任料:運用資産の0.4104% ファンドラップ手数料:運用資産の1.296% 運用管理費用(信託報酬):信託財産の1.35%±0.70% 信託財産留保額:最大で信託財産の0.5% 最低投資額:バリュー・プログラムは500万円、プレミア・プログラムは1000万円 投資額に対して最大で年間4.2567%のコストがかかります。 バリュー・プログラムでは国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、不動産が投資対象であり、 プレミア・プログラムではそれらにコモディティが加わります。 野村ファンドラップはファンドラップ口座の国内シェアNo.1は野村證券が提供するものです。 契約金額ベースのシェアで32.5%を占めています。 円建てで国際分散投資を実現することができ、年間6回まで運用コースの変更が可能となっています。 ・ダイワファンドラップ ファンドラップ手数料:契約資産の時価評価額に対して年間1.512% 信託報酬:0.77%~1.41% 信託財産留保額:なし 購入手数料:なし 最低投資額:300万円 ダイワファンドラップは大和証券が提供するサービスです。 国内シェアNo.2でTVCMで一気に有名になったものです。 24.7%のシェアを占めています。 野村ファンドラップと比較すると投資金額のハードルはやや低めとなっています。 手数料についてもわずかではありますが低めに設定されています。 運用スタイルは100種類以上にものぼります。 投資対象は国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、不動産、コモディティとなっています。 「ダイワファンドラップオンライン」という50万円から利用でき、手続きの全てがネットで完結するものや、「ダイワファンドラッププレミアム」という3,000万円から利用できるものもあります。 ・SMBCファンドラップ ファンドラップ手数料:0.972% ファンドラップ投資一任報酬:0.324% ファンド・オブ・ファンズ管理報酬:0.685% 管理報酬:最大2%程度 信託財産留保額:なし 購入手数料:なし 最低投資額:300万円 SMBCファンドラップは、SMBC日興証券が提供する投資一任サービスです。 国内シェアNo.3で22.1%のシェアを占めています。 こちらはSMBC日興証券が提供するサービスですが、申込窓口は三井住友銀行となっています。 三井住友銀行はSMBC日興証券の代理人というかんじです。 SMBC日興証券が最適なポートフォリオを構築してくれます。 それを元にした提案や案内三井住友銀行がしてくれて、運用管理はSMBC日興証券がしてくれます。 2年以上の契約で基本報酬が30%割引とされています。 ここまで紹介してきたファンドラップは国内トップ3のものです。 この3社で国内シェア約8割を占めています。 他にもファンドラップはたくさんありますが、代表的なものを紹介しました。 ただ、ファンドラップの致命的な欠点として手数料が高いということがあります。 「%」で聞くとあまりイメージできないかもしれませんが、金額で考えてみるとすごく高いことがわかります。 ファンドラップを選ぶ場合はそのことも考慮することをおすすめします。 参考になれば幸いです。

2019/02/13
こんにちは。 信託銀行のラップ口座の比較ですね。 「ラップ口座」とは、利用者が金融機関との間で「投資一任契約」を締結し、資産運用のプロに自分の資産の運用を一任するサービスです。投資家は資産運用の基本スタイル(積極派、安定派など)を伝えるだけで、実際の運用は一任します。 銀行が取り扱っていることもありますが、投資一任契約の相手方は証券会社です。証券会社は投資家の希望に従う形で投資信託を選択し、途中で資産構成の変更も行いながら、顧客資産を運用します。 プロに資産運用を全て任せるということが、ラップ口座を利用するメリットになります。 ラップ口座のうち、投資信託のみで運用しているものを「ファンドラップ口座」と呼んでおり、ラップ口座のほとんどがファンドラップ口座です。 ラップ口座ビジネスは近年急速に成長しています。 2018年9月末時点で預かり資産が8兆7469億円、口座件数も80万件を超える規模となりました。金融緩和で低金利の時代、急速に伸びているラップ口座は、大手金融機関の新たな収益源となっています。 一昔前まではラップ口座のサービスを利用するには1億円以上の資産が必要でしたが、昨今では300万円程度から利用できるようになりました。 日本投資顧問業協会の「契約資産状況 (平成30年9月末)」によりますと、契約件数と契約金額のシェア上位3社は以下のとおりでした。 ・野村證券株式会社 契約件数24.1%(1位) 契約金額32.5%(1位) ・大和証券株式会社 契約件数17.7%(3位) 契約金額24.7%(2位) ・SMBC日興証券株式会社 契約件数19.8%(2位) 契約金額22.1%(1位) また、ヘッジファンドダイレクト株式会社によるレポート(2016年11月)によりますと、運用実績 の上位3社は以下のとおりでした。 ・SMBCファンドラップ 年率 9.58% ・三井住友信託ファンドラップ 年率 6.20% ・野村ファンドラップ 年率 5.93% ここで、ファンドラップでは、証券会社と運用会社への手数料が二重で発生するデメリットがあります(運用報酬と信託報酬)。 しかもこの手数料は、運用成績に関わらず毎年発生し続けます。1,000万円の運用資産で、仮に運用成績が0%で手数料のみ払い続けるとすると、手数料2%では20年後に668万円に、手数料3%では543万円になってしまうのです。 信託報酬が高めの金融商品ばかり選ばれる可能性も、ないとは言い切れません。運用のプロに任せるとはいえ、必ずしも良い運用成績になるとはかぎりませんから、高コスト・高リスクの運用といえるかもしれません。 それでも利用者や預かり資産が増えているのは、いわゆる団塊の世代の利用が増えているからではないかと推測されます。 ご質問の趣旨からは逸れますが、適当に分散投資をするだけなら、バランス型で信託報酬が低い投資信託を選んで購入すれば十分です。 昨今話題のAI(人工知能)技術を生かしたロボアドバイザーであれば、最低投資金額が10万円程度のものもあります。人間vs機械ということになりますが、AIの進化はめざましいものがあり、人間のプロに比べてそれほど劣ることはないでしょう。しかも、機械化によってコストも大幅に抑えられています。 資産運用にはいろいろな選択肢がありそうです。 ご参考にしていただけましたら幸いです。

2019/02/13
そもそもラップ口座のメリットですが、資産運用を任せることができることにあり、投資家に最適な運用方法をプロポーズしてくれるだけでなく、売買まで全てをワークしてもらえます。 本業で忙しいため、あまり時間を確保できない方やナレッジや経験がなくても、資産運用にたずさわれるという点は魅力だと思います。 分散投資が可能 投資を行う際は分散投資を行うことで、いざというときの損失リスクを抑制できます。 1つの銘柄に集中投資する場合には、相場が上昇すれば大きな恩恵を受けることができますが、下落した場合には、価格変動のリスクを一点に集中して受けることになるため、大幅な損失を被ってしまう可能性があります。 一方、ラップ口座では日本株式・外国株式・日本債券・外国債券・REIT・コモディティ・ヘッジファンド・MRFなどの運用を組み合わせることによって、ある程度分散投資を行ってくれる可能性がある点がメリットと言えるでしょう。 デメリットは最低投資金額が比較的高く、手数料が比較的高いということです。 ネット証券などを利用して自分で株式投資を行うケースのコストは、かなり高いと感じると思います。作業の委託料がかなりのっています。 また、ファンドラップの場合、証券会社への運用報酬と、ファンドの資産運用会社への運用報酬(信託報酬)が両建てで生まれます。これもコスト増の要因です。 プロに任せれば必ず利益が出るわけではない状況で、毎年高い手数料が確実に取られることを考えると、ファンドラップはコストが極めて高い投資信託であるということが言えます。 手数料控除後リターンを信託銀行のファンドラップで比較すると、三井住友信託ファンドラップがおすすめですが、自分で投資の勉強をある程度してから、個人で投資をするのがオススメです。 投資は「必ずしもプロが勝つわけではない」というわからない要素が沢山ある環境です。景気が良い時はみんな儲かりますので、資産運用はよくよく考えてトライしてみてください。 以上、参考になれば、幸いです。
関連する質問
 Q買取に関わる入金方法について
Q買取に関わる入金方法について受付中!
回答数:3でつ子2018/07/08 Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?
Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?受付中!
回答数:4一条冬華2018/07/08 Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問
Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問受付中!
回答数:2匿名希望2018/08/09 Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?
Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?受付中!
回答数:4w2541607672018/08/31 Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?
Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?解決済み
回答数:4ぬんぬん2018/09/05