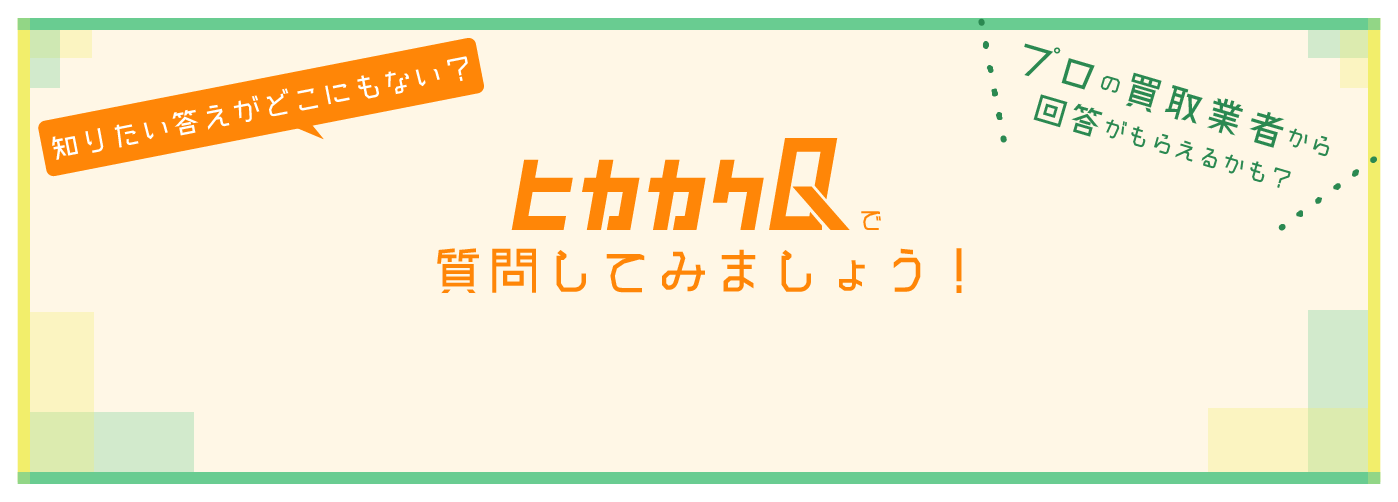個人年金保険を受け取る場合に税金はかかる?他におすすめの資産運用は?
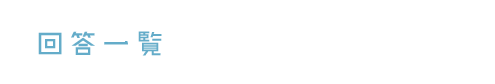 3/3 件
3/3 件
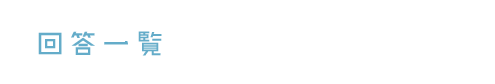 3/3 件
3/3 件
2019/03/12
個人年金の受け取りには税金がかかってきます。 また、契約者や受取人に誰を指定するかによって、年金受取時にかかる税金が異なります。 税金の種類によって実質の年金額も変わりますので気をつけましょう。 ●契約者・保険料負担者=受取人は所得税 契約者(保険料負担者)が年金の受取人と同一人物の場合は「雑所得」となります。 所得税と住民税の課税対象にです。 年金種類や年金額、払込保険料の総額に応じた金額(必要経費)を年金額から差し引いた残額が課税対象で、 残額が25万円以上の場合、残額に所定の税率を乗じた金額が源泉徴収されます。 ●契約者・保険料負担者≠受取人は贈与税 契約者(保険料負担者)と年金の受取人が異なる場合は、贈与税の対象になります。 贈与税を計算するには、まず「年金受給権の評価額」を算出する必要があります。 「評価額」は大きく分けると次の3つで、一番大きい金額が課税対象となります。 1.契約返戻金の金額(解約した場合などに支払われる金額) 2.一時金相当額(一時金の給付可能な場合) 3.年金年額×残存期間や平均余命に応じ、所定の利率を用いて計算 ※贈与税には110万円の非課税枠が設定してあり、110万円とは別の控除額も設けられています 贈与税を求める計算は (年金額-110万円)×税率-控除額=贈与税 となります。 また、ややこしいのですが 年金を毎年受け取る場合は、初年度の年金額に対し、贈与税が課せられます(初年度のみ所得税は非課税)。 2年目以降の年金は所得税の課税対象になり、課税部分が段階的に増加する方法で計算します。 保険料負担者と年金受取人が異なる場合は、 所得税の源泉徴収は行われませんので、申告をする必要があります。 さて、二つ目のご質問ですが、個人年金のように税金を払わなくてよい資産運用制度を最近政府が推進しています。 2018年1月スタートの「つみたてNISA」と それよりひとあし先に始まったiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)です。 これは、金融庁が、「貯蓄から資産形成」を国民に対して促す目的で始めたプロジェクトで、 日本では、投資から得られた利益に対して、 通常20.315%の税金(所得税+住民税+復興特別所得税)がかかりますが、 これがゼロになります。 二つの主な対比を載せておきます。 ・つみたてNISA 期間:最大20年間 年間投資上限:40万 投資対象商品:金融庁が定めた基準を見たく投資信託 資産の引き出し:いつでも引き出せる お金を出す時:課税対象 運用時:非課税 ・iDeCo 期間:加入から60歳まで(10年間延長可能) 年間投資上限:14万4000円~81万6000円(職業、加入している年金の制度により異なる) 投資対象商品:金融庁が定めた基準を見たく投資信託・定期預金・保険 資産の引き出し:60歳までできない お金を出す時:非課税 運用時:非課税 条件により、どちらが向いているか別れてきますので よく研究なさって、納得の資産運用をなさってください。

2019/03/11
こんにちは。 まず、個人年金保険を受取る場合、税金はかかるかどうかについてご回答いたします。 結論から申し上げますと、税金がかかります。 個人年金保険は、公的年金(厚生年金と国民年金)とは別に、一定期間にわたって保険料を支払い続けることで、将来時点で年金を受け取ることができる保険金融商品です。 この個人年金保険の年金を受け取るときにかかってくる税金は、以下のように場合によって異なります。 第一に、保険契約者(保険料を支払う人)と年金受取人が同じケースです。 この場合、受け取った保険金は雑所得となり、所得税が発生します。 計算式は、 雑所得=総収入金額-必要経費 必要経費=受け取る年金金額×払込保険料の合計額/年金の総支給見込額 であり、ここで求められた雑所得がその他の所得と合算されて所得税の課税標準となります。その課税標準の金額に応じた税率を掛けると、所得税の金額が求められます。 第二に、保険契約者と年金受取人が異なるケースです。 この場合、年金受取人が契約者から、年金(を受け取る権利)を贈与されたとみなされるため、贈与税がかかってきます。 贈与税はの控除額は110万円ですので、110万円までは非課税になります。 計算式は、 贈与税額=(課税価格‐基礎控除110万円)×税率‐控除額 です。 次に、二つめのご質問、個人年金よりもお勧めの資産運用についてご回答いたします。 年金的なものとすれば、普通は確定拠出年金(iDeCo)やつみたてNISAなどが候補として挙げられると思います。 つみたてNISAでは運用した利益にかかる税金が非課税になるだけですが、iDeCoでは拠出した掛け金が控除対象になるという大きな節税メリットがあります。 いずれもローリスクローリターンの比較的安定な投資信託を中心に運用することになります。信託報酬が低く、運用成績がまずまずのものを選べば、年換算で2-3%程度の運用益を見込める可能性があります。複利効果がそのペースで続き、なおかつ一定金額を拠出し続ければ、将来的に安心できる金融資産になっていることでしょう。 ただ、資産運用にはさまざまなやり方があり、特にこういったローリスクローリターン的な運用をしなければいけないわけではありません。 個別株に投資して、値上がりや配当、株主優待を受け取ってもいいでしょう。不動産投資では、アパート・マンション経営なども考えられます。FXで外貨に投資するのもありかもしれません。 いずれもiDeCoやつみたてNISAにくらべればハイリスクハイリターンですが、こういった選択肢を排除しないことも大切だと思います。全額をこういった投資にするのではなく、ローリスクとハイリスクを半々にするなども考えられます。 ご自身の興味や得意分野なども考慮の上、自己責任でご決断ください。 ご参考にしていただけましたら幸いです。

2019/03/11
個人年金の受取には税金がかかります。 いわゆる雑所得の扱いとなり、受取額に対し一定率の所得税や住民税を納付する必要があるのです。 また、もし受取人をご自身ではなく奥様など別の方にしていた場合、所得税に加えて贈与税の課税対象にもなります。 せっかく老後のために貯蓄したものを税金で取られてしまうのも面白くないと思いますので、契約を検討されている場合、受取人は本人となるように契約されることをおすすめします。 個人年金以外でおすすめの方法として、今は確定拠出年金があります。 毎月掛け金を拠出し、積立式で貯蓄していくもので、企業で契約できるタイプと個人で契約できるタイプ(iDeCo)があり、積立可能額は契約者の年収によって変わります。 確定拠出年金は中身自体は投資信託、または定期預金、保険となっており、資金を投資会社に預けて運用してもらうものとなります。 確定拠出年金のメリットは運用益が非課税なこと。通常の投資信託などの場合は運用の中で出た利益に一定の税金がかかるのですが、確定拠出年金であればそれが免除されるのです。 また掛け金は給与所得の対象から控除されるため、現状の所得税を下げるというメリットもあります。 ただ確定拠出年金は元本保証ではありませんので、理屈上は資金がマイナスになるリスクもあります。 ただ現時点の運用状況を見る限り、確定拠出年金で大損しているというものも少なく、堅調に資産形成できているケースが多いようです。 また確定拠出年金は受取開始が60歳以降と決まっていて、それまでの間は受け取ることができませんし、途中解約も原則的にはできません。 ただ個人年金も基本的には老後にしか使わないお金と決めて貯蓄するものですので、この点は確定拠出年金特有のデメリットでもないと思います。 同様の方法として、積立NISAという方法もおすすめです。 こちらは確定拠出年金よりもさらに少額で始めることができ、利益に関しては非課税というメリットも同様です。(掛け金の給与所得控除はありません) ただし年間投資金額に40万円という上限があるため、その枠を超えた分は別の手段での運用を検討する必要があります。 今は個人年金よりも、確定拠出年金、積立NISAのほうが注目を集めています。 どれを選んでも大損するということはあまりないとは思いますが、ご自身に合ったものを選択するのが良いでしょう。
関連する質問
 Q買取に関わる入金方法について
Q買取に関わる入金方法について受付中!
回答数:3でつ子2018/07/08 Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?
Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?受付中!
回答数:4一条冬華2018/07/08 Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問
Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問受付中!
回答数:2匿名希望2018/08/09 Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?
Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?受付中!
回答数:4w2541607672018/08/31 Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?
Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?解決済み
回答数:4ぬんぬん2018/09/05