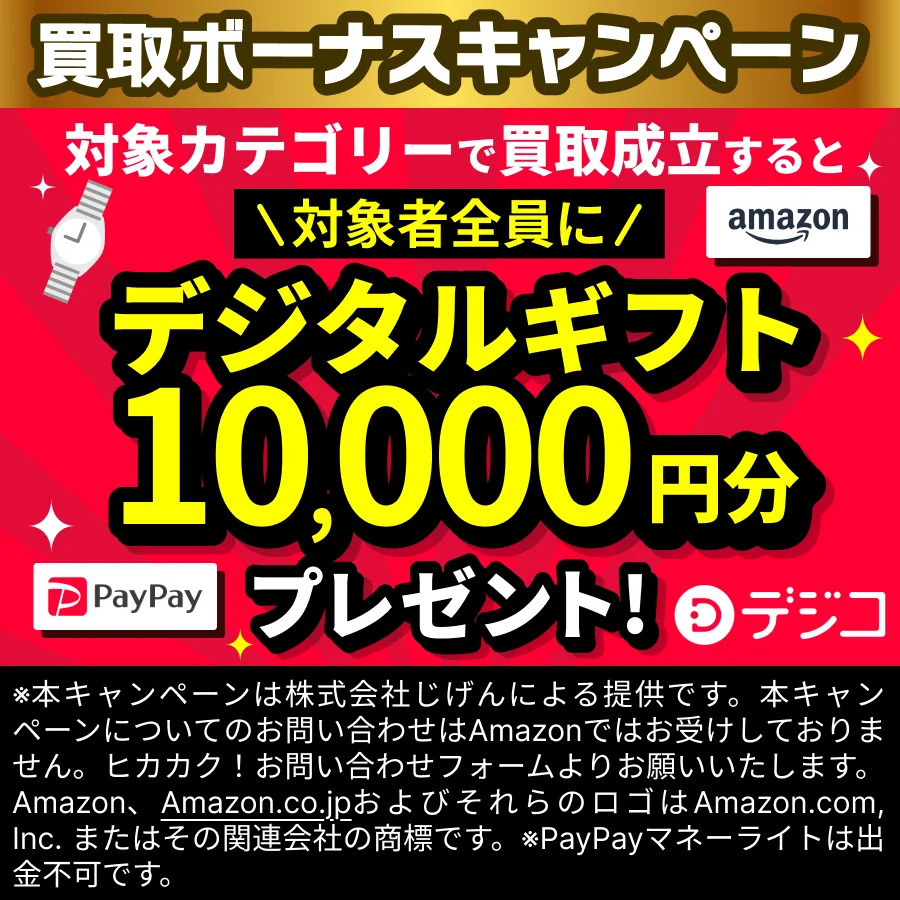骨董品や美術品は、1点30万円以上のものを古美術商や買取専門店、リサイクルショップ等で売却した時のみ、譲渡所得になる資産だ。
ヤフオクやメルカリを使って反復的に美術品や骨董品の売却が行われている場合は、他種類の所得の中で税金計算を行う仕組みとなる。
また譲渡所得には節税をする上で欠かせないさまざまなポイントがあるため、高額資産の売却をしている人は注意が必要だと言えるだろう。
今回は、美術品・骨董品に大きく関係する譲渡所得について、皆さんと一緒に基礎知識を確認していきたい。


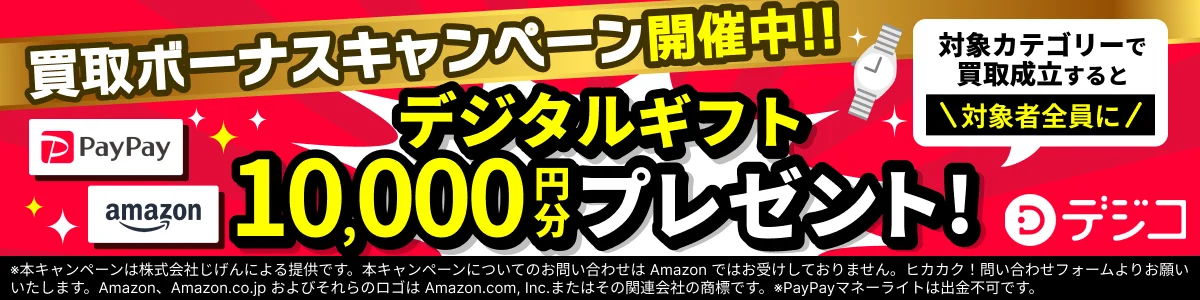
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
譲渡所得とは?
譲渡所得というのは、税計算の基礎となる資産の譲渡によって生じた所得の総称だ。
ここで指す譲渡とは、有償・無償問わず所有資産を移転する行為の全てを指す。また譲渡の中には通常の売買だけでなく、交換、公売、競売、財産分与、代物弁済、法人に対する現物出資なども含まれるため、その範囲は意外と幅広い捉えた方が良いだろう。
もし自分が行った行為に対して譲渡か否かの判断ができない場合は、弁護士や税理士といった専門家に相談をするようにして欲しい。
事業所得との違いは?
譲渡所得と混同されやすい存在としては、事業所得や不動産所得といったものがある。
譲渡所得は基本的に、売却や処分といった行為による臨時収入的な性質を持つ。これに対して事業所得の場合は、継続性や反復性によって得られる収入となるのだ。
こうした両者の違いから考えると、オークションサイトなどを利用して骨董品や美術品の売却を生業としている人の収入は、明らかに譲渡所得にはならないと捉えて良いだろう。
また不動産についても、「所有物件による収入か?売却による収入か?」によって所得が変わってくるため、収入源とも言える品目だけでなく行為についても必ず着目するようにして欲しい。
譲渡所得対象のとなる資産とは?
国税庁のホームページで紹介されている譲渡所得対象の資産には、骨董、書画、宝石、金地金、土地、建物、借地権、土石(砂)などの18品目が並んでいる。
またその中には、著作権や特許権、ゴルフ会員権といった権利もあるため、物理的に存在する物以外を譲渡時には注意をするようにして欲しい。また売掛金や貸付金といった金銭債権については、譲渡所得から除かれる仕組みとなっている。
資産を譲渡しても所得税が課税されない場合もある
資産の譲渡を行っても、必ず所得税が課税されるわけではない。
例えば、債務を弁済する能力が著しく困難な人が強制換価手続によって資産が競売にかけられた場合は、当然非課税となる。
また非課税扱いの7ケースの中には、骨董品や美術品に関する内容もあるため、特例などを上手に活用することで商品売却時の節税が可能になると捉えて良いだろう。
骨董品・美術品に関わる特例の内容については、当ページの最後に詳しく紹介したい。
譲渡資産の種類によって異なる課税方法
譲渡所得の課税計算は、資産の種類によって分離課税もしくは総合課税から選択される形となる。
土地、短期所有土地の譲渡とみなされるもの、上場カバードワラント、店頭カバードワラントといったものは、給与所得や事業所得といった他の所得金額とは区別し、租税特別措置法にもとづいた税率で計算をする分離課税の対象となる。
これに対してゴルフ会員権の譲渡に類似するものと、今回のテーマとなる美術品や骨董品、工芸品などについては、給与所得や事業所得などの他所得金額と譲渡所得を合計し、所得税法で定められた累進税率で税額計算をする仕組みとなるため、譲渡所得に該当する行為があった場合はどちらに該当するのかを必ず確認する必要があると言えるだろう。
譲渡所得は複数種類の税金計算に使われる
骨董品や美術品などの売却によって生じた譲渡所得は、所得税だけでなく個人住民税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料といった部分にも大きな影響をもたらす存在だ。
国保税や介護保険料では、住民それぞれの所得に応じた所得割という基準を使って税額を算出しているため、譲渡所得の条件に含まれるお金がたくさん入ってきた翌年は、それだけ所得税以外の税金が増える可能性が高いと捉えた方が良いかもしれない。
国保税などの税金が上がるのは譲渡の翌年のみ
個人住民税や国民健康保険税などは、前年の1月1日~12月31日までの所得を基準に計算が行われる。
そのため、何らかの事情で譲渡所得が一気に増えた場合は、その翌年だけ国保税などの税額がアップする仕組みになっているのだ。
しかし譲渡所得は臨時収入的な位置付けとなるため、骨董品や美術品の売却処分が1回きりであれば、翌々年の税額まで影響することはないと捉えて良いだろう。
譲渡所得の対象となる骨董品や美術品について
譲渡所得の基礎知識を確認したところで、当ページの主テーマとも言える骨董品や美術品に関わる譲渡所得の話に移っていこう。
1組または1点の価額が30万円以上
骨董品や書画、美術品などについては、1組または1個の価額が30万円を超えるもののみ、譲渡所得の課税対象となる。
また30万円を基準に考える品物の中には、貴金属や宝石なども含まれるため、ジュエリーやアクセサリーの売却時にも同じ考え方を用いると捉えて良いだろう。
1つ30万円に満たない美術品や骨董品は非課税
1点の価額が30万円に満たない骨董品や美術品は、日頃の暮らしに必要な生活用動産に含まれることで非課税対象となる。
生活用動産の中には、衣類や家具、通勤用の自動車といった品目も並んでいるため、例えばリサイクルショップで30万円を超えない骨董品と古着、ブランド品などを売却した場合についても、譲渡所得の対象から外れると捉えて良いだろう。
骨董品や美術品の譲渡所得における計算方法と注意点
30万円を超える骨董品や美術品の売却によって発生した譲渡所得の金額は、下記の計算式に当てはめる形で算出される仕組みとなっている。
【譲渡所得の金額】 = 譲渡価額(収入金額)-(取得費 + 譲渡費用)-50万円
収入金額とは?
収入金額もしくは譲渡価額は、その名のとおり骨董品や美術品の売却によって支払われたお金のことである。
仮に骨董品や美術品の処分によって金銭以外のものを受け取った時には、その時価についても収入金額に含めて良い仕組みとなっている。
取得費とは?
骨董品や美術品の収集にかかった費用は、取得費として譲渡所得から差し引くことができる。
具体的な例としては、絵画の購入に使ったお金だけでなく各種手数料も取得費に含まれる。
また所有者との紛争に使った訴訟費用についても、相続財産を除けば取得費に分類されることもあるため、このケースに該当する場合は税務署や税理士に相談をすると良いだろう。
譲渡費用とは?
骨董品や美術品の売却にかかった直接的な費用も、譲渡費用として控除できる。
買取店利用時は、出張料、査定料、振込手数料といった諸費用がかかるため、これらのお金を譲渡所得から差し引けることを知っていれば、業者選定も効率良く行えることだろう。
短期譲渡所得と長期譲渡所得
総合課税では、所有期間が5年を超えている長期譲渡所得と、所有期間が5年に満たない短期譲渡所得に分けて計算を行う仕組みとなっている。
長期譲渡所得の場合は、上記の式によって算出した譲渡所得の2分の1が総合課税対象となるため、効率的な美術品投資や節税を目的とする人には、購入から5年以上の所有を経た売却がおすすめと言えるだろう。
美術品・骨董品の取得日がわからない場合は?
短期・長期譲渡所得の判断に欠かせない取得日がわからない場合は、どんなに10年以上の長きに渡って所有している美術品であっても、短期譲渡所得での税額計算となる。
ちなみに骨董品コレクターなどの他者から資産を購入した場合は、引渡しを受けた日が取得日となる。
贈与や相続による取得の場合は贈与者もしくは被相続人が取得した日となるため、取得日における厳密な定義を知っておくことも必要だと言えるだろう。
同じ年に短期譲渡所得と長期譲渡所得、両方の譲渡益がある場合
その年の譲渡益の中で長期と短期の両方がある場合は、先に短期の譲渡益から特別控除分の50万円を差し引く流れとなる。
ちなみに譲渡益の合計金額が50万円以下の場合は、その金額までの控除となるため、注意をして欲しい。
骨董品や美術品の譲渡で非課税になることもある
最後に、文化庁で定める「美術品等に係る税制優遇措置」によって譲渡所得の非課税が生じる2つのケースについてご紹介しておこう。
重要文化財を国等に譲渡した場合
文化財保護法指定の土地を除く重要文化財を、国や地方公共団体、独立行政法人国立美術館などの機関に譲渡した場合は、その所得税が非課税となる。
これに対して重要有形民族文化財については、2016年12月31日までの譲渡所得の2分の1相当額が課税対象となるため、この両者の違いと期間についてはきちんと確認するようにして欲しい。
個人が国などに美術品を寄付した場合
公益を目的とする事業を行う法人や国、地方公共団体への財産寄付で国税庁長官の承認を受けた場合は、その寄付がなかったものとみなされることで譲渡所得についても非課税となる。
これに対して法人への財産贈与や遺贈の場合は、時価で財産譲渡があったものとして課税が行われるため、より良い寄付先を決めることで美術品を社会に役立てるだけでなく、節税効果も得られると捉えて良いだろう。
また文化庁では、法人税や相続税の税制優遇措置も設けているため、展示や公開のメリットの大きな美術品や骨董品を所有しているなら、一度ホームページを確認してみても良いかもしれない。
まとめ
所得税を中心としたさまざまな税金計算の基礎となる譲渡所得は、30万円を超える骨董品や美術品の売却にも大きく関わる存在だ。
特に数百万円~数千万円もの高額作品の売買や相続に対しては税務署も目を光らせているため、今回紹介した基礎知識をきちんと頭に入れた上で確定申告に向けた準備を行うようにして欲しい。