
2017年6月28日、画像1つ送るだけで即現金が手に入る魔法のようなアプリが登場した。それが現金化アプリ「CASH」で、目の前にあるものがなんでも即現金に化けるという衝撃は瞬く間にネットを駆け巡った。
この「CASH」はリリース初日に1件当たり約5,000円、総額3.6億円以上のアイテムを換金した後、僅か16時間でサービスを停止したことでさらに話題となったのである。「錬金術」と騒がれ、その是非を含めて様々な逸話が駆け巡った現金化アプリ「CASH」の当時の事情と、現在の状態、即日現金化はもうできないのかについて報告する。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
現金化アプリ「CASH」リリース初日と「錬金術」
CASHとはどんなアプリなのか
「目の前のアイテムが 一瞬でキャッシュに変わる」をキャッチフレーズに登場した現金化アプリ「CASH」は、ツイッターなどで情報が拡散されると凄まじい勢いでダウンロード数を伸ばすこととなった。それは他に類を見ないほどの「手軽さ」と「即時性」が、ユーザーの心を掴んだためである。
当時のCASHの利用法はこうだ。まずはスマートフォンにアプリをダウンロードし、電話番号を登録してSMSで認証を行う。次に現金化を希望するアイテムのカテゴリーとブランド、コンディションを選択する。そしてアイテムの全体が移るように商品の写真を撮影し、送信すれば即座に査定金額が提示され、専用ウォレットに同額が表示されるのだ。
ここで「キャッシュを引き出す」を選択すれば、手数料の250円を引かれた残りが、ユーザー指定の銀行口座に振り込まれる。のんびり操作していても、10分もあれば換金完了だ。しかも荷物の送付期限は2ヶ月後で、その間に受け取った金額に15%のキャンセル料を加えて返金すれば、アイテムを引き渡す必要もない。別名「質屋アプリ」と呼ばれたゆえんである。
最初は恐る恐る利用に踏み切ったユーザーがあまりの簡単さに拍子抜けした後、怒涛の勢いで手元の品を換金し続けながら、情報を拡散し続けたのもむべなるかな、であった。
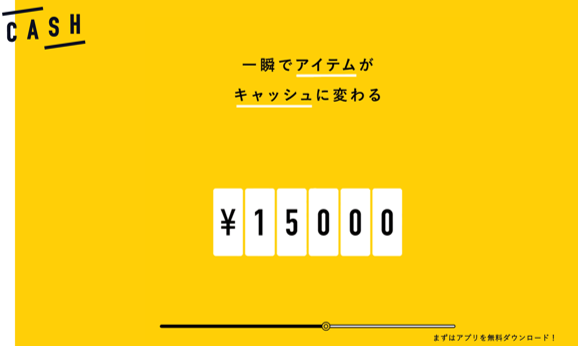
CASH登場前は?
それまでにもヤフオクなどのオークションサイトや、フリマアプリのメルカリに出品することで、使わなくなった身の回りのアイテムを換金することはできた。それより以前からブックオフやハードオフなどの店頭に持ち込むことで現金化をすぐに行うこと自体は出来た。しかしネットサービスやアプリで振り込みを受けるまでの期間は長くなってしまう傾向があり、「メルカリ疲れ」と言う言葉がネット上で流行したことからもわかる通り、現金を得るためには非常に手間暇をかける必要があったのだ。
そもそも客が現れなければ売れないから、出品者はタイトルの付け方一つとっても、目を引くよう工夫を凝らさなければならない。出品者は数多く、競争は熾烈だ。少しでも高く売れるようにと背景やライティングにまで工夫を凝らして画像を撮影し、購入希望者が現れてもトラブルが起こらないようにと神経を使う。
逆恨みでもされて悪い評価を付けられると、問題のある出品者とみられて売れ行きが悪化する心配があるからだ。CASHにはそんな面倒が一切ない。少々安くてもいいからできるだけ早く換金したい、不用品を処分するのに余計な手間はかけたくないというニーズに対し、CASHのシステムはぴったりあてはまるものだったのだ。面白半分で使ったユーザーも多かったとは思う。
錬金術出来てしまったシステムとはどういうことなのか
こうしてCASHはその売却手続きの簡便さで大好評を得たが、その反面システム・仕組みには抜け穴的な部分があり、これが後々「錬金術」と揶揄される原因となったのである。
特に注目を集めたのが査定方法だった。CASHの査定は、アイテムの状態についてはユーザーからの申告のみで、しかも全体画像さえ送信すればいいというものである。そこで、さっそくいたずら心で普通なら値のつくはずもないアイテムを査定にかけるユーザーが現れたのだ。
その結果とんでもない事実が発覚した。使えないiphoneが最高額の20,000円と査定されたのはまだしも、エアコンのリモコンや食べ終わったばかりの料理の皿にまで同じ最高額が表示されたのである。
これはアイテムの品名をiphoneの最新機種とし、画像を別なものにしてみたというもので、ふざけて査定に出したユーザーの肝を冷やし、システムの不具合を疑い、心配する声が相次いだ。
さらに驚くべきは、激安ショップで10個249円のヘアゴムが1本1,000円になったという事例である。もしもユーザーが悪意を以って査定を行えば、スマートフォン1つでCASHからいくらでも現金を引き出すことができたわけだ。

そして、悪質なユーザーを排除する手段が不足していたという面も確かにあった。CASH側は査定にかけられたアイテムと、実際に送られてきたものが一致しなかった場合、アカウント停止と言う手段を取ることは可能である。しかし、アイテムが引き出された現金の代価として回収されるのは、最長2ヶ月後だ。
つまり、あくまでも理屈の上ではあるが、この間に商品名や状態を偽ったアイテムをどんどん査定にかけてしまえば、元手をかけずに大金を手に入れることもできるという弱点があったのである。
サービス停止の理由は「錬金術」ではなかった
サービス停止の真相
リリースから僅か16時間後の2017年6月29日午前2時、CASHは突然サービスを停止し、やはり「錬金術」を行ったユーザーが相当おり、その被害が甚大だったのではないか、と言う憶測を呼んだ。
しかしその後のインタビューで、CASHのCEO・代表取締役であった光本勇介氏はユーザーの9割以上がきちんとしたアイテムを送ってきたと語っている。実際には、CASHの「錬金術」はほぼ行われなかったということになる。
CEOによると、CASHがサービスを停止せざるを得なかった理由は、予想をはるかに超える利用者数と換金額にあった。CASHが稼働していた時間は正確には16時間34分、その間に7万2,796のアイテムが現金化され、総額3億6,629万3,200円が支払われた。即時査定、即時換金のシステムとは言え、この勢いが続くとなれば資金はあっという間に底をついてしまう。この資金自体は以前にCEOの光本氏がZOZOTOWNに売却していたSTORES.jpの売却益で賄われていたと噂されていた(売却額ほどの資金力がなければ賄うことは難しく、資金調達リリースに関しても情報発表が無かったことから)。
短期間に膨大な量のアイテムが送付されて来たことも問題だった。CASH側はアイテムの回収まで2ヶ月と言う長い期限を設けていたが、生真面目なユーザーたちはせっせと換金したアイテムを送り付けたのだ。
その結果、翌日には1万点を超える荷物が殺到することになり、CEOは悲鳴を上げた宅配業者から「届けられる状態ではない」と呼び出された。仕方なく、CEO自ら現場に立ち、緊急募集したアルバイトたちとともにひたすら荷物を仕分け続けたのである。
これについてCEOは、反響の規模こそ予想外のものであり、そのためサービス停止と言う事態を招いてしまったが、ほとんどのユーザーが正直な取引を行ったことは当然であり、想定内だったという見解を示している。
ブログカードがロードできませんでした。
不正行為は計算済み
「錬金術」を使うことは、アカウント停止と言うリスクと隣り合わせだ。せっかく瞬間的に現金を手に入れる手段があるのに、一時僅かな金額を手に入れるためにそれを失うのでは釣り合わない。もちろん、新しくスマートフォンを契約すればもう一度アカウントを登録することはできる。
しかしCASHの査定上限額は20,000円であり、スマートフォンをわざわざ購入するコストに見合うものではないとなれば、確かに「錬金術」はリスクを負うに値しない行為である。
さらに、CASHは念には念を入れて、仮にユーザーの3割が不正行為を行っても採算がとれるモデルを構築したうえでスタートしたとCEOは語った。騒動の裏では当然のリスクヘッジが行われていたわけだが、ふたを開けてみればユーザーの大半は正しいビジネスセンスの持ち主であり、むしろそのためにサービス停止に至った、と言うのが真相だったのだ。
「錬金術≒即日現金化」はまだ可能なのか、もうできないのか
サービス再開
様々な逸話を生み出し、炎上とも騒動とも呼ばれる事態を巻き起こしたCASHは、その約2ヶ月後となった8月24にサービスを再開した。ただし再開にあたっては、基本的なスタイルはそのままながら、システムに修正が施されていたのである。
取引開始時間は毎日午前10時で、換金額に1日1,000万円の上限が設定された。これはユーザー個人のアカウントに対するものではなく、CASH全体での額だ。つまり取引開始から仮に1時間でユーザー全体の換金額が1,000万円に達した場合、午前11時でCASHの査定受付は終了となり、間に合わなかった人は翌日を待つしかなくなったのである。
この新システムにより、運営不能になりかねない額が引き出される事態は回避されることとなった。送付される荷物も対応できる分量に収まるようになり、安定した運営が可能になったのである。

再開後の変化
何より大きな変化は、返金がなくなったことだ。もともと返金ができるようにしたのは、ユーザーが後になってアイテムを売ったことを後悔し、やっぱり買い戻したい、となるケースを予想してのものだった。ただしこの場合、CASH側にとってはビジネスの機会損失と言う形になる。
そこで2ヶ月の猶予を設け、査定額の15%をキャンセル料に設定したのだ。ところがこれが「質屋アプリ」と言われ、キャンセル料を利息とみなせばとんでもない高利だ、との批判を受けることになってしまった。結果的に見れば、実際にキャンセルを選択したユーザーは全体の2%にとどまったため、返金とキャンセル料は撤廃されることになったのである。
ネット上では「貸金業法違反では」と言う声も聴かれたが、スキーム作りから著名な金融に知見のある法律事務所の協力を得ており、当然、金融庁などから指導が入った事実もない。CASHはきちんと免許を取得した古物商であり、質屋でも高利貸しでもないのだ。ここは法的スキームのカラクリによってグレーもしくはホワイトな業態としての整理が出来上がっていたということだろう。
査定部分の強化
「錬金術」騒動を引き起こす原因になった査定部分も強化され、精度の高い判定が行われるようになった。カメラロールの中にある画像は査定に利用できなくなり、その都度ごとに撮影する必要がある。アイテム送付の期限も2ヶ月から2週間に短縮された。
さらにユーザーの評価制度を導入したことで、軽い気持ちで「錬金術」を行おうとするユーザーに警告を出すことができるようになった。実際にシステム修正後、ネットの情報に乗って激安品を購入し「錬金術」を実行したユーザーは、あっという間に「星1つ」、最低の評価を受けている。アカウント停止にリーチがかかった状態だ。
CASHには査定可能なアイテムについての膨大な情報が集積されているが、それでも日々増え続ける物すべての価値を把握できるわけではない。そのためうまく実売価格より高く査定されるアイテムを見つけることができれば、システム修正後も極僅かながら「錬金術」ができる可能性はある。ただし、その結果をどう受け止めるかはユーザー次第だ。
ブログカードがロードできませんでした。
ブログカードがロードできませんでした。
ブログカードがロードできませんでした。
まとめ
現金化アプリ「CASH」の現在とその後も錬金術は健在しているのかご紹介した。リリースした途端に一気に想定以上の換金が進み、サービス停止まで追い込まれたほど時代の流れにあったアプリということが分かるだろう。
現在はいくつかのシステム改善が行われたが、錬金術を行うことはまだ僅かながら可能なようだ。しかし錬金術は警告が出たり評価が最低になったり、アカウント停止になるなど、リスクを負うに値しない行為であるため、錬金術はいずれなくなるだろう。CASHはその後、FANZAやDMM英会話などを展開するDMMグループに70億円で買収され、これまた大きなニュースとなった。
その後、DMMから再度MBOという形で光本氏によって一度買い戻されたCASHは再びバイセルテクノロジーズという上場ベンチャー企業によって買収されている。尚、バイセルテクノロジーズは着物はバイセル、ハナハナハナのテレビCMで話題の着物出張買取サービスを全国展開する企業であり、CASHアプリとの連携、CASHの買取カテゴリー拡大が期待された。
しかし、現在「あとでキャッシュ」しか利用できなくなっているようで、2021年12月時点では即日現金化はもうできなくなっており、話題となった際に謳われた価値は失われてしまったようだ。即日現金化したい場合は買取一括査定サイト「ヒカカク!」を使って店頭買取や出張買取で即時現金化してもらうのが良いだろう。
CASH、運営会社BANKや創業者CEOの光本勇介氏に関する記事一覧
ブログカードがロードできませんでした。

ブログカードがロードできませんでした。
CASH利用時の体験談は以下ページで投稿してみよう。
買取価格
スピード
手数料
許可番号
ポリシー
ウイルス
対策









