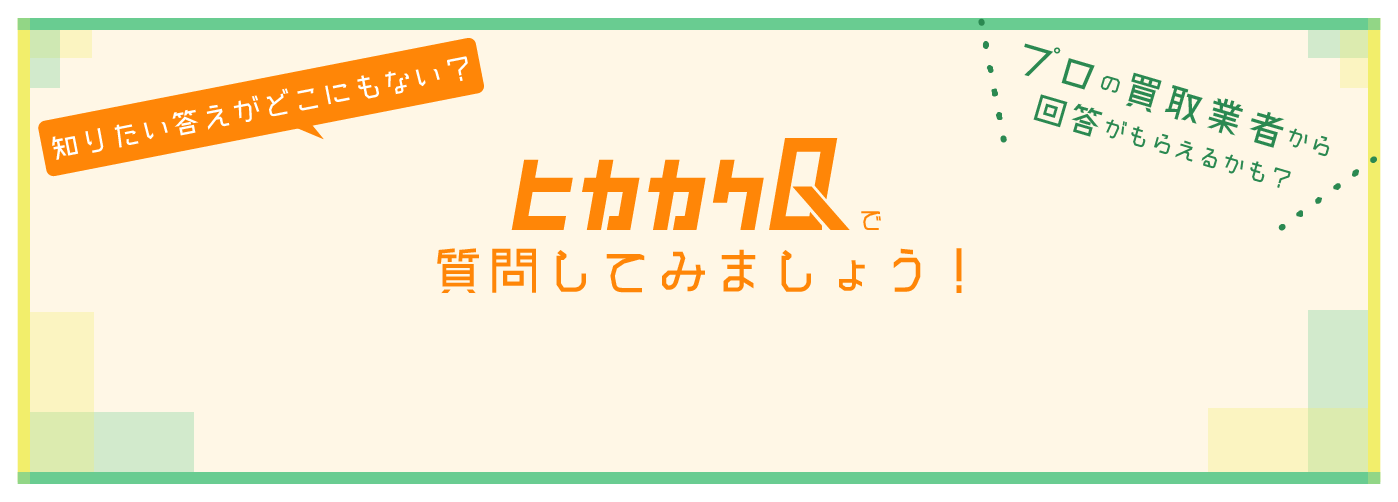積み立てNISAの仕組みや儲かる理由
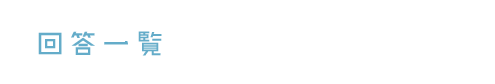 3/3 件
3/3 件
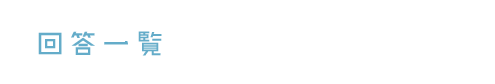 3/3 件
3/3 件
2019/02/12
つみたてNISAの仕組みとしては、非課税の投資枠を年間40万円としたうえで投資を継続しておこなえるというものです。その為、全額で800万円分の非課税枠があるものの、年間では40万円分のみしか非課税で投資できないことに注意が必要です。 儲かる仕組みは簡潔に言えば、投資を行って利益が出た場合に還元されるというものであり、必ずりえきが出るものではないと言えます。つまり、つみたてNISAは20年間、40万円の非課税枠を有しつつ、長年運用していくことによって利益を作っていくというものです。 仮に、将来に備えるのであれば、iDeCoの方が優れている面もあります。例えば、iDeCoの場合は60才まで途中引き出しが不可能であるものの、元本保証の商品や自分のニーズに合わせて投資を行う商品を分散していくことが可能です。そのうえで、iDeCoに使用した金額は所得税や住民税に対して控除することが可能であり、節税効果も有しています。その為、長期的な資産運用と資金作りが目的である場合はiDeCoの方が向いていると言えるでしょう。 加えて言えば、つみたてNISAの場合は、投資信託をメインで扱うものであり、株式などの金融商品を運用することはできません。特に新規株式上場などの機会は、株の投資を行う上で非常に重要である為、その機会を逃すことになります。ちなみに、つみたてNISAを運用している場合、一般口座を運用することは可能であるものの、株まで扱える一般NISAを使用することができません。 例え、金融機関が異なったとしてもNISAの口座は個人では1つしか持つことが出来ず、運用もその金融機関でしか行えません。仮に、他の金融機関に必要書類を送り開設の申請を行ったとしても口座を開くことはできないでしょう。また、つみたてNISAと比較した場合、運用期間は下がるものの、短期的な投資を行うのであれば一般NISAとiDeCoの併用を行った方が将来に対する有効な対策となり得るでしょう。 つみたてNISAは、一般NISAと併用できません。そのうえで、金融機関の変更や商品の変更なども可能であるものの、慎重に商品を選択する必要があります。また、iDeCoなどの商品とは明確に定義や運用期間、商品の性質が異なり、完全な投資商品であることを念頭におきましょう。また、つみたてNISAに関しては年間の非課税投資枠が40万円分しかないことに注意が必要です。

2019/02/12
積立NISAですが、中身については「投資信託」とほぼ同じと考えて良いです。 つまり、お金を専門家に預けて運用してもらう仕組みですね。 例えば株式売買など、どの銘柄を買ってどの銘柄を売るといった取引はなかなか素人がやってうまくいくものではありません。 そういった難しい部分をプロに任せ、利益が出たらその一部を報酬として支払うというものが、投資信託および積立NISAの考え方です。 では投資信託と積立NISAでは何が違うのかというと、大きくは下記の3点が異なります。 ・出資の仕方 ・出資金額の上限 ・利益かかる税金 【出資の仕方】 投資信託の場合、自分の好きな時に好きな金額を信託会社に支払い、運用を委託します。 積立NISAは、出資に関しては積立式を取っています。 毎月何円、毎日何円といった形で、定額を出資し続ける方法ですね。 とはいえ、金額の変更や積立の停止、積立額の引き出しなどは任意のタイミングで柔軟にできますので、実質的にできることは投資信託と大差ありません。 あくまで投資商品の性質として、積立式が基本であると理解いただければと思います。 【出資金額の上限】 投資信託は、原則的に出資額に上限はありません。 お金があればあるだけ出資することはできます。 積立NISAは、出資額の上限が年間40万円までという決まりがあります。 例えば毎月の積立で年間の上限まで出資したい場合、400,000円を12で割った33,333円が毎月の積立額の上限になりますね。 そのため、大金を投資できるものではないと言えます。 【利益にかかる税金】 投資信託に限らず、投資によって得た利益には一定率の税金を支払わなくてはなりません。 ただし積立NISAに関しては、利益には税金がかからないというルールがあります。 利益が出たら丸々自分のものにできるということですね。 以上が積立NISAの簡単な説明です。 積立NISAは上記のとおり出資額に上限があることから、「儲ける」という意味ではそれほど有利なものではありませんが、「損しにくい」ものではありますね。 上記の3つのルールがあることにより、積立NISAは今まで資産運用をしたことがない初心者向けの投資商品となっています。 毎月100円ずつ積み立て、年間1,200円の出資で運用するなんてことも可能です。 非常に低リスクで始められますので、まずはここから資産運用のイメージを身につけると良いでしょう。 もし資産運用にご興味があるようでしたら、積立NISAから始めてみると言うのは有用だと思いますよ。

2019/02/12
回答させていただきます。 2018年1月からはじまり、「つみたてNISA(積立NISA)」は一般的となりつつあります。 口座開設受付は2017年10月から既に開始されており、日本に住む20歳以上の方であれば誰でも契約することができます。 つみたてNISA最大のアドバンテージは、投資によって得られた評価益や分配金等の運用益がタックスフリーとなることです。 日本では、投資から得られた所得に対して、通常20.315%のタックス(所得税+住民税+復興特別所得税)がかかりますが、積み立てニーサはこれがゼロになります。 つみたてNISAの非課税対象は、長期の積み立て目的の「投資信託」のみです。現行のNISAとは違って、個別株は買えないのです。投資信託を利用して、長期でコツコツと資産運用したい方には非常にメリットがありますが、「個別株」も「投資信託」の双方も、NISA口座で運用したいという場合は、現行のNISAの運用が適していると思います。 また、損益通算が使えない点も、注意が必要です。通常、複数の証券口座を使って運用している場合、すべての証券口座の1月~12月の利益と損失を足し合わせて、ほかの運用次第ではタックスを低くすることができます。 例えば、口座Aでプラス400万円、口座Bでマイナス50万円だったケースでが、350万円が課税対象となります。 しかし、つみたてNISA口座では損益通算が利用できないため、口座AでプラスとつみたてNISA口座でマイナスは相殺できず、プラスのみ課税対象になります。つみたてNISA口座を利用しながら、ほかの複数の口座で並行して投資を行う人にとってはかなりのディスアドバンテージとなります。 さらに、つみたてNISAでは、金融庁の基準をクリアした投資信託やETFしか投資対象とされていません。 限定されることで選びやすいというメリットもありますが、広い選択肢をこのむ方にとってはデメリットとなるでしょう。 以上、つみたてNISAはメリットが多いですが、デメリットをしっかりとはあくして、賢く活用していきましょう。 以上、参考にしていただければ幸いです。
関連する質問
 Q買取に関わる入金方法について
Q買取に関わる入金方法について受付中!
回答数:3でつ子2018/07/08 Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?
Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?受付中!
回答数:4一条冬華2018/07/08 Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問
Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問受付中!
回答数:2匿名希望2018/08/09 Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?
Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?受付中!
回答数:4w2541607672018/08/31 Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?
Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?解決済み
回答数:4ぬんぬん2018/09/05
査定実績
2025.08.27  YuniT が査定しました
YuniT が査定しましたYuniTのコメント
8月28日買取成立
エルメス ケリーダンス2フリンジ付き2025.08.21  YuniT が査定しました
YuniT が査定しましたYuniTのコメント
コメントなし
CHANEL(シャネル) マトラッセ ショルダーバッグ A2200 ブラック×ゴールド2025.08.21 カイエモン が査定しました
カイエモンのコメント
コメントなし
Voigtlander(フォクトレンダー) BESSA-L シルバー2025.08.21  リカージョイ が査定しました
リカージョイ が査定しましたリカージョイのコメント
コメントなし
SUNTORY(サントリー) 響 ジャパニーズハーモニー