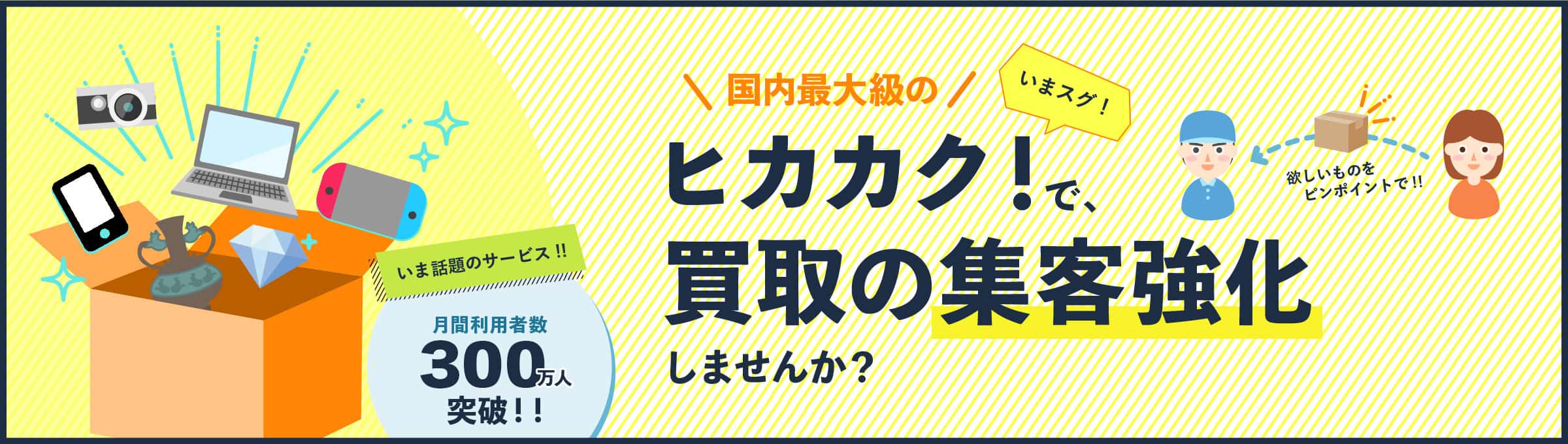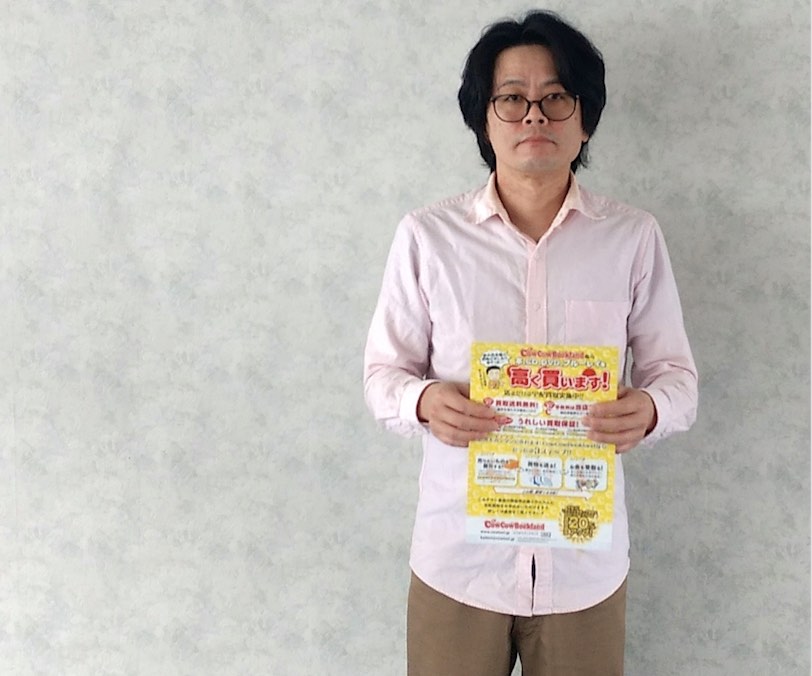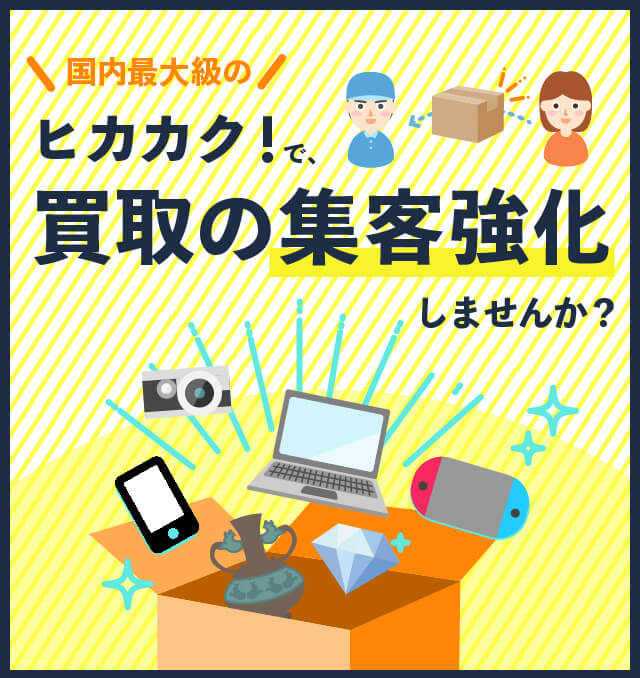買取店を経営していると、売り手が持ち込んできた品物の真贋を見極めることが重要になる。
査定をして適正価格で買取、相場に合った価格で販売することで健全な営業ができるからである。
しかし、世の中には不正品やコピー品も流通している。精巧に作られているものもあるので、うっかり買い取ってしまうこともあるだろう。
買取店はこのような際に法的な義務を負っている。買取店に課せられている義務について知り、具体的な対策を考えられるようになろう。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物営業法による買取店の義務とは
買取店を営業するためには古物営業法の定めに従わなければならない。この法律の中ではさまざまな義務が買取店に課せられているが、その中でも代表的なものが三つある。
「本人確認義務」「取引の記録義務」「警察官への申告義務(不正品の場合」となっている。では1つ1つ詳しく解説していこう。
1.本人確認義務
一つ目は本人確認義務であり、品物を業として買い取るときには売り手の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければならない。
相手方の身元を確認する作業になっていて、書類などによって実際に目で確認する意外にも、これらの情報が記された書類の交付を受けたり、電子署名を受けて電子ファイルで提出してもらったりする方法でも良い。
2.取引の記録義務
二つ目は取引に関する記録の義務である。買取をおこなったときには取引に関する情報を台帳に記録して、最終記録日から3年間保管しなければならない。
記載内容として取引の年月日、買い取った品物の品目と数量、特徴である。
また、本人確認をおこなった方法と、確認された住所、氏名、年齢、職業についても一緒に記録することが求められている。
3.不正品は警察官に申告義務
そして、三つ目に挙げられるのが不正品やコピー品を買い取ってしまったという状況で重要になる義務である。
盗品やコピー品などの不正品という疑いがあると認められたときには、直ちに警察官に申告する義務が課せられている。直ちにというのは気づいたら速やかにということであり、厳密に期日が定められているわけではない。
疑いがあると認められた場合
疑いがあると認められたときに申告しなければならないのが原則なので、明確な証拠が捉えられていなくても疑わしいときには警察に連絡をすることが求められているのである。
不正品を取り扱っているという自覚がなくても、うっかり買い取ってしまったというケースも十分に考えられる。それにもし気づいたら直ちに連絡すれば良い。
それを隠蔽してしまったときには営業許可を取り消されたり、業務停止命令が下されたりすることになる。
盗品だと分かっていて買い取った場合
特に盗品だと認識していながらも買い取ってしまった場合には刑法がかかわることになるので気をつけなければならない。
盗品有償譲受罪という刑法256条に定められている犯罪になり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになる。
この処分を受けた場合には5年間は営業許可が下りないため、買取店としては大損害になることは否めない。
また、買い取ったときだけでなく、運搬、保管、処分であっても例外ではない。無償で引き取って処分したというだけでも罪に問われるので、他の品物を買い取るついでに善意で引き取るときすら気をつけなければならないのである。
不正品やコピー品への対策
不正品やコピー品は流通しているので常に買取店は目にするリスクがある。適切な対策を講じておかなければ大きなリスクを抱えることになるのは確かだろう。
対策として、まず考えておくべきなのが不正品やコピー品などを買い取ったと気づいたときに起こすべき行動を理解しておくことである。直ちに警察に連絡するのが基本だとわきまえておけば良いが、それで全てが解決されるわけではないということにも留意しておこう。
買取店を営業する立場としては不正品やコピー品を買取したことによって実質的に損をしていることになる。
また、それが遺失品や盗品という形で不正品だった場合には所有者からの求めがあったときには返還しなければならない。
この際には代金を求めることはできず、無償で引き渡すことになってしまう。このような事態に備えておくことも重要なのである。
売り手の本人確認をおこない、詳細を記録する義務があるのはこの際に対策を立てられるようにする意味もある。買取店としては正規品であることを前提とした取引をおこなっているだろう。
買取店は不利な立場に立つことも
民法に従って解釈すると、それが不正品やコピー品などであった場合には売買契約自体が無効であると解釈することが可能である。ただし、それを売り手側が否定することも可能で、事業者側は不利な立場に立つことになる。
事業者側に重大な過失があって不正品やコピー品の取引をしたという場合には買取店側が責任を負うことになるのである。
具体的には少し詳しい人が見れば明らかにコピー品だとわかるようなものを正規品として取り扱って売買してしまったようなケースが挙げられる。
あくまで買取店は専門家として業務をおこなうことが求められているため、売り手よりも重い責任を負わざるを得ないと覚えておくと良いだろう。
この点に関しては古物営業法にも明記されていて、取り扱う品物が不正品かどうかを判断できる管理者を置き、国家公安委員会則で定められている知識や技術、経験などを習得させる機会を与えることが努力義務となっている。
その努力を怠っていたために不正品を見抜くことができなかったと解釈されてしまうと、その契約自体は成立してしまうことになる。
買取のリスクを抑えるためには
買取店として安心して営業できるようにするには鑑定眼のある人材を確保することが必須だと言えるだろう。買取の査定をするにはマニュアルを作ってアルバイトに任せてしまうケースもある。
事業を拡大する上では重要な観点かもしれないが、それによって不正品やコピー品を買い取ってしまうリスクが高まることは否めない。
安心して経営できるようにするための対策として、専門のスタッフを雇用して売買契約をする前に必ず鑑定をおこなうようにするのが望ましい。
一方、もう一つの対策として契約書に不正品やコピー品などについての規定を加えるのも良い方法である。
不正品の場合には全額返金することを誓うといった一文を入れて、売り手に必ず署名してもらうようにすれば万が一の事態に備えられる。その契約書を活用することで、不正品だと示せれば返金を法的に求められるようになる。
真贋の見極めに必要になった費用も請求することも契約書に加えておけば、不正品やコピー品を買い取ってしまったときにも金銭的な損失を最小限に抑えることができる。
売る側は問題ないのか
不正品やコピー品を買い取る立場での義務や責任については重いことがわかるが、売り手の方は何も責任を負わないのかと疑問に思う人もいるだろう。
売り手についてもそもそも盗品のような不正品を取り扱うことは禁じられている。これは不正品だとわかっていて、故意に買取に出した場合には責任を問われることになる。
詐欺罪や商標法違反に相当することになり、特に何も対策をしていなかったとしても買取店側も損失を取り戻せる可能性が高い。
しかし、現実的には不正品やコピー品だとわかっていたことを立証するのが難しい場合が多い。本当に不正品だとは知らずに買取店に持ってきて売買契約をしたというケースでは、実は個人の売り手は基本的には何も責任を負わなくて済んでしまう。
個人はあくまで素人として捉えられていて、精巧に作られている偽物を見た目で正規品かどうかを判断するのは困難だと解釈されている。
そのため、正規品だと完全に信じて買取を依頼し、正規品の相場で取引をしたとしても罪に問われることはないのである。
このような扱いの違いを理解して、買取店は不正品やコピー品への対策を充実させなければならない。
査定と鑑定の違いを理解して人選をすべき
不正品やコピー品を持ち込んできたときに鑑定をして正規品ではないと判断できればその場で断ってしまうことはできる。
その意味で鑑定ができる人材を確保することは買取店にとって不可欠なのは確かだが、鑑定と査定の意味を取り違えないように気をつけなければならない。
買取店が繁盛するためには正確に品物の価値を査定した上で利益になる価格で買い取ることが必須である。
鑑定とは?
鑑定はあくまで真贋を見極めることであって、価格が現状としてどの程度かを計算するものではない。
品物の状態や相場は関係なく、単純にその品物が正規品か偽物かを判断することである。
真贋を判断する鑑定には査定とは全く異なる能力が求められるので、人選の際には注意が必要である。
査定とは?
査定は価格を決めることである。査定価格は商品の品目や特徴、状態などに加えて、売買相場を考慮して定められるのが特徴である。
同じ品物であっても月日が経てば劣化して査定価格は下がることになり、相場が変動して価格が上下するといったことも起こり得る。
査定をするときにはまず鑑定をして正規品かどうかを考えるのが妥当だが、実際には正規品だと仮定したらどの程度の価格になるかというスタンスで査定することが多い。
そのため、相場情報に詳しくて査定が得意な人であっても鑑定ができるとは限らない。
まとめ
鑑定眼のある人材はそれほど多くはないため、人材を確保しようとしても苦労を伴うことは否めない。それでも買取店を経営していきたいけれど、本当に不正品やコピー品を扱ってしまわないか心配という場合もある。
鑑定を担当する人材を複数確保してダブルチェックする体制を整えるなどの対策も考えられるが、万が一の事態が発生したときに困らないように準備しておくのも良いだろう。
警察への申告以外の手続きについてはほとんどが法的手続きが絡んでくることになる。契約が無効だと主張するにも裁判所を利用する必要が生じる可能性すらあるだろう。不正品やコピー品の売買契約をしてしまったときに契約書にどのような文面を入れておけば心配ないかも悩みどころになる。
この対策として有用なのが顧問弁護士を雇う方法である。契約書の作成や、不正品が見つかったときの諸手続きについていつでも気軽に相談できるようになる。
優秀な弁護士を顧問にできれば、そのような事態を招かないための業務改善についても提案してもらえるだろう。不正品に関する問題が心配なら考えておいた方が良い対策である。