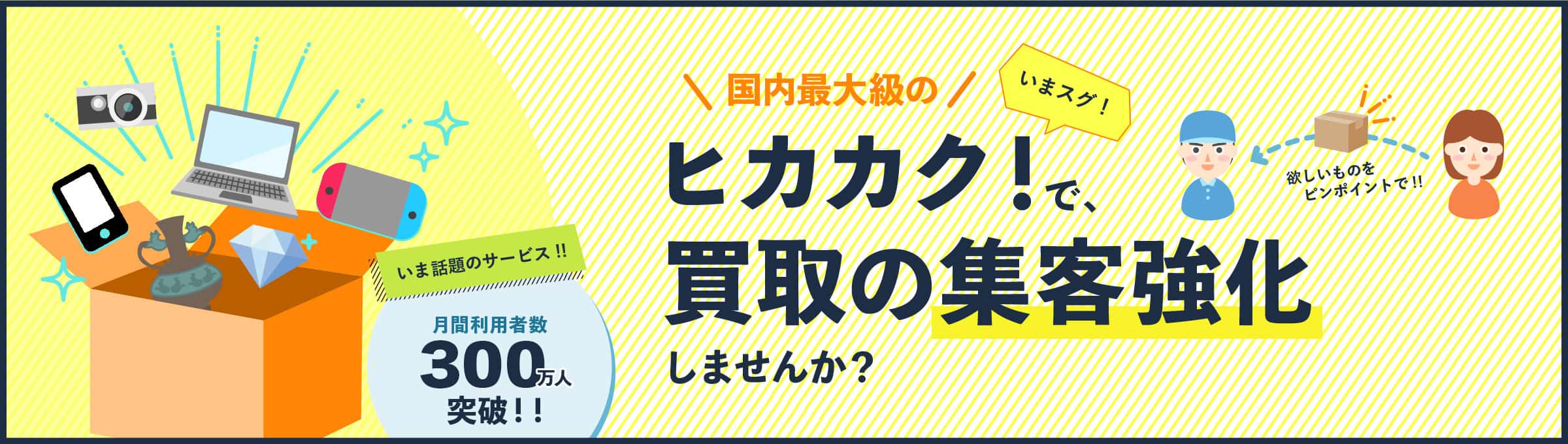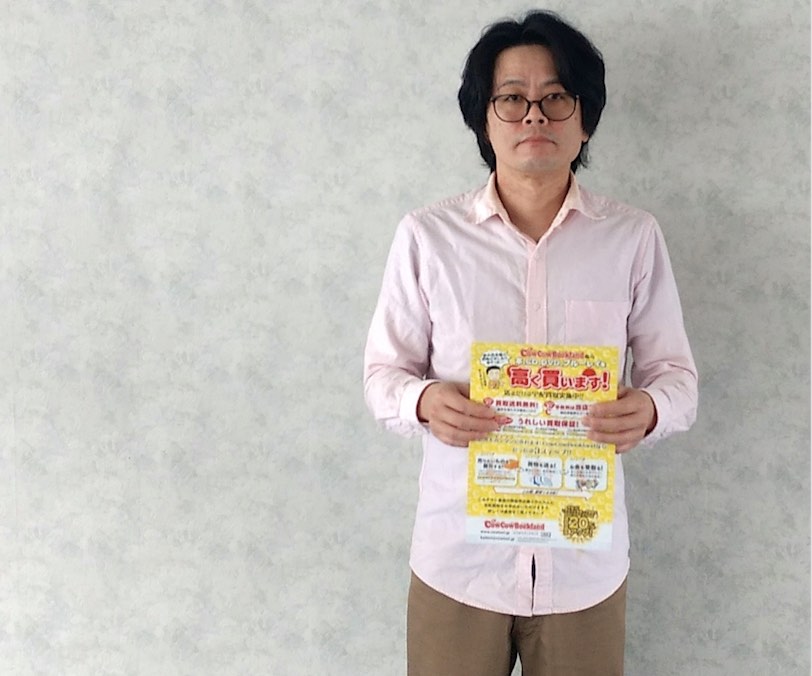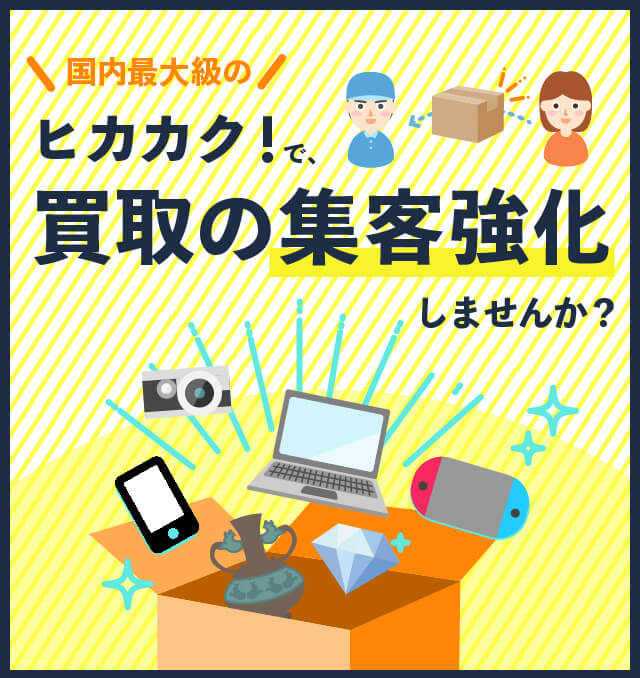中世ヨーロッパに作られた物や昭和の頃に作られた物など、そのとき特有の雰囲気ある作品に恋い焦がれる人は少なくない。場合によっては、それらに囲まれたアンティークショップやヴィンテージショップの開業を夢見る人もいるだろう。
新品ではないため、営業するにあたって古物商の許可を得る必要があることは言うまでもないが、それ以外にも、開業には多くの準備を要する。どういった商品を扱うかによっても、必要となる準備は異なるが、今回は多く取り扱う物を中心として、開業にあたって必要となる準備を説明していく。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
アンティーク・ヴィンテージショップとは
アンティーク・ヴィンテージショップは小売業に含まれる。今回は、一般的な小売店開業手続きにはない、特殊な手続きについてまとめている。一般的な小売業の開業については、独立行政法人 中小企業基盤整備機構サイトが参考になる。
アンティーク・ヴィンテージと中古品との違い
アンティークやヴィンテージは、中古品・古着・Used品とは違う特別な意味がある。アンティークやヴィンテージに該当するものは、高額取引が見込まれるため、鑑定が必要になる場合がある。
アンティーク(antique:フランス語)とは
アンティークとは、古美術の意味。骨董品のこともアンティークと言われる。ただし、衣類について使われることは少ない。
ヴィンテージ(vintage)とは
ヴィンテージとは、もともと特別なあたり年であるワインの葡萄収穫年の意味だったが、ファッション分野で、優れた遺産と呼べる物についてヴィンテージと言うようになった。
中古品(used)とは
一度使用された物。新品か中古品かの厳密な区別については、商品の種類による。
アンティークショップとは
昔は西洋の骨董品を扱う小売店をさしていたが、現在は、西洋のみではなく、日本や中国アジア諸国の骨董品、年代物の家具、古美術品、書画、武具、ジュエリー、年代物の着物など、扱う範囲が広くなっている。
お客様もグローバル化し、海外からの注文がくることもある。ここ数年は、中国美術品バブルが起きており、特に中国のアンティーク商品が高値で取引されている。
アンティークショップの種類
アンティークショップには、主に3つの種類がある。基本的に、小規模経営店舗形式が多いが、フランチャイズ方式や無店舗方式などもある。
フランチャイズ店舗型
アンティーク家具の分野で、全国展開のフランチャイズ方式アンティークショップがある。開業資金が割高で月々の支払いや契約期間などの制限があるが、マニュアルがあり、開業までの日数が少なくてすむ。
小規模経営店舗
店主の得意分野やこだわりのある小規模経営店舗。海外への買い付けを含む仕入れ、販路開拓などもその店舗の店長やスタッフが自己裁量でおこなう。アンティークショップと言うと、一般的にはこの小規模経営店舗をさすことが多い。フランチャイズ方式と違い、利益はすべて確保できる。開業準備はすべておこなう。
無店舗・事業所のみ
店舗の賃料などの維持費、従業員の人件費などを節約できる。仕入れの出張料や鑑定料は、事業所側負担が多い。仕入れも販路も自分で探す必要がある。店舗による窓口がないため、店舗ありのアンティークショップと比べ、さらなる集客努力が必要である。
鑑定や価格評価をおこなう機関
日本国内外で、アンティークやヴィンテージの鑑定や価格評価をおこなう機関がある。アンティークやヴィンテージ商品を扱う際に、贋作や盗品などを仕入れてしまったら、大きな損失を被ることになる。そのため、常に防犯に関する情報を収集する必要があるだろう。
アンティークやヴィンテージを扱うには、専門知識を得るために分野に応じて学会などで情報収集する必要があるだろう。
一般財団法人東京鑑定評価機構
鑑定裁判でも助言を求められるほどの評価機構。日本のトップクラス鑑定士が所属している。
東京都古物商防犯協力会連合会
誤って盗品や遺失物を仕入れてしまうことがないように積極的に活動している。警察との共催により、古物商の法令講座を開き、市場の信頼性を高めている団体。法改正があれば会員に周知している。
CINOA
CINOA(Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art)は、1935年設立の世界的な美術品骨董品の取扱協会だ。オーストリア・オーストラリア・ベルギー・スイス・チェコスロバキア・デンマーク・スペイン・フランス・イギリスなどに機関がある。
サザビーズ 東京オフィス
世界的に有名なオークショングループ。
東洋陶磁学会
定期的に学術誌を出している学会。
公益社団法人 日本陶磁協会
定期的に特別展などもおこなっている協会。
公益社団法人 日本美術刀剣保存協会
作刀実地・研磨・外装技術研修や刀職技能訓練講習などもおこなっている協会。
日本中国美術家協会
サイトはほとんど中国語で書かれている。芸術家年鑑などを販売しているようだ。
仕入れや販売時に公的手続きが必要な事例
アンティークショップ、ヴィンテージショップで扱う商品は多岐にわたるため、扱う商品によってさまざまな国際条約・法律・条例・規則の規制を受ける。特に最近注意が必要な物は象牙である。宝飾品や飾りに多用されていた象牙について、平成30年から事業所の届出や商品の登録が必要になり、失念すると罰則対象になる。
また、最近流行のインターネット販売の場合は、お客様が海外在住者であることも少なくない。その場合は、文化庁で申請し、輸出の通関手続きをおこない、お客様が住む国の法令規則に応じた対応が必要である。開業後も今後も細かな規則が出てくる可能性が高いため、常日頃の情報収集が必要である。
以下、開業準備の仕入れや買取時に必要な物についてまとめた。
アンティーク・ヴィンテージ商品
アンティーク商品やヴィンテージ商品を取り扱う場合は、古物商免許が必要である。小さな物でも大変価値のある商品であるため、窃盗の対象になりやすい。窃盗犯が盗品を換金するために、アンティークショップ・ヴィンテージショップの仕入れ買取取引を悪用することがある。
もしも仕入れや買取をした商品の中に盗品や遺失物が紛れ込んでいれば、一定期間内に限り、もとの持ち主に無償で返さなければならず、ショップ経営上大きな損失を被る。さらに、このような事件が続くと、アンティーク市場・ヴィンテージ市場そのものが不安定化する恐れがある。
古物商免許は盗品の売買を防ぎ、窃盗そのほかの犯罪を防止し、取引市場を安定化するためにできた免許制度である。盗まれた物を被害者に速やかに返還することを重視するため、帳簿記録の義務や警察協力義務があり、無許可営業に該当すると、”3年以下の懲役または100万円以下の罰金”という重い罰則を設けている。
窃盗犯が窃盗物を換金することを防ぐために、次の取引を古物営業法で規制。ネット上の販売であっても該当すれば古物商許可が必要である。
- ・中古商品や中古車を買い取って売る
- ・仕入れた中古商品や中古車を手直しして売る
- ・仕入れた中古商品や中古車の使えそうな部品を売る
- ・委託販売する
- ・仕入れた中古品をレンタルする
- ・中古品を交換する
自己所有の物を販売するなど、盗品換金リスクの低い販売行為は古物商許可は不要である。しかし、価値のあるアンティーク商品・ヴィンテージ商品を選び抜き、販売を続けるには、仕入れや買取が必要である。現時点で該当しなくとも、事前に古物商許可を受けておいたほうが、今後のビジネスチャンスを広げることができる。
銃砲刀剣
個人から買取したアンティークの銃や刀が、実は未登録である場合がある。直ちに管轄の警察に発見届を出し、都道府県教育委員会で銃砲刀剣の登録をしなければならない。登録ができない場合は、原則所持できない。
手続きの詳細などについては、東京都教育委員会のサイトを参考にすると良い。
また、アンティーク品として扱われる銃は、慶応3年(1867年)以前に製造された古式銃のみ。古式銃に該当しない場合は、現代銃として、所持するだけでも違法になる。
古式銃であれば、都道府県教育委員会での美術品・骨董品登録が必要である。現代銃や現代銃に改造された古式銃は、拳銃の不法所持違反に該当し、処罰対象になるので特に注意が必要である。
象牙・象牙商品
アンティーク商品において、象牙加工品は珍しくない。印鑑だけでなく、装飾品や根付、箸などさまざまな加工品が存在する。
近年においては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(「種の保存法」)が改正され、平成30年(2018年)6月1日に施行されている。
象牙は部分的でも加工品であっても、無償・有償取引を問わず、個人事業主・法人が特別国際種事業者としての登録しなければならない。取引記録の記載と、陳列・広告時の登録番号などの表示、管理表作成が必要である。また、環境省および経済産業省による立入検査の場合は、協力しなければならない。
これの登録については、一般財団法人自然環境研究センターでおこなっている。
登録事項の変更がある場合も、必ず変更届が必要である。登録免許税納付書または領収証書(90,000円)が必要であるので、要注意である。
古酒・ヴィンテージワイン
買い取った古酒・ヴィンテージワインを対面で販売する場合は一般酒類小売業免許が必要である。国税庁申請の手引きについては、税務署の一般酒類小売免許申請の手引(PDF)に書かれている。
また、買い取った古酒・ヴィンテージワインをインターネットやカタログ通販で販売する場合は通信販売酒類小売業免許が必要である。こちらも、税務署の通信販売酒類小売業免許申請の手引(PDF)に詳細が書かれている。
注意しなければならないのは、空き瓶の販売だ。古酒・ヴィンテージワインの空き瓶は、アンティークや骨董品としての価値があるため、古物営業法の規制を受ける可能性が高くなると言われている。
海外向け通信販売
骨董品の輸出に関しては、関税手続きが必要である。ワシントン条約に該当する商品、ダイヤモンド原石、インクなど、輸出に規制がかかる場合があるため特に注意が必要である。
ワシントン条約に該当するものは原則買い取ることができず、違反した場合に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。さらに、関税を通さない場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課せられることになっている。
指定の例としては、渡り鳥条約などに基づく物、絶滅の恐れがあると判断される種、ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種などがある。ただし、ワシントン条約付属書Ⅰに限っては、原則禁止として、登録を受ければ陳列・広告・譲渡しなどが可能となっている。この例外にあたるケースとしては、環境大臣の許可を受けた場合や、大学や博物館などが所定の届け出を提出した場合などである。
また、国宝や重要文化財は国外持ち出しが禁止である。海外輸出に関する国宝や重要文化財ではないことを証明する”古美術品輸出鑑査証明”が必要である。申請方法の詳細については、文化庁のサイトで確認することができる。
まとめ
アンティークショップ・ヴィンテージショップの開業にあたっては、まず営業形態を考えることからになるだろう。そして、何を扱うかで必要書類も変わってくる。申請する際には、各サイトが出している手続き方法などをよく読み込んだ上でおこなう必要があるだろう。
もし不安な場合や、時間がないために申請が難しいと感じる場合は、行政書士へ依頼するのも一つの手だ。もちろん有料になるため、予算との相談になることだろう。
また、営業するにあたって協会や学会の情報も合わせて入手しておきたいところだ。サイトをブックマークしてしまうとよいかもしれない。
この記事を監修した専門家