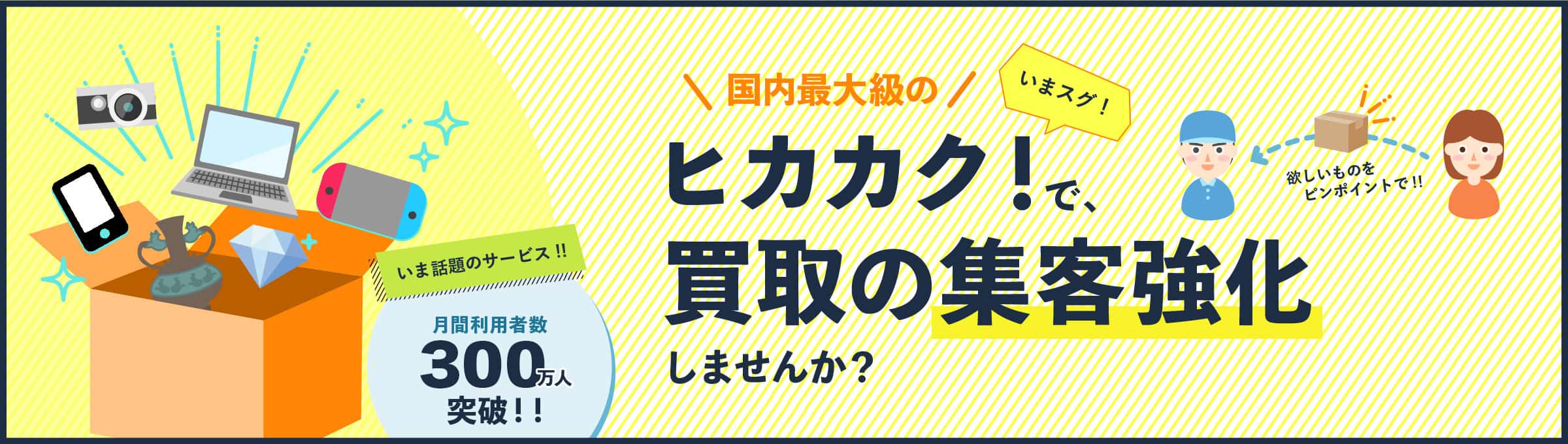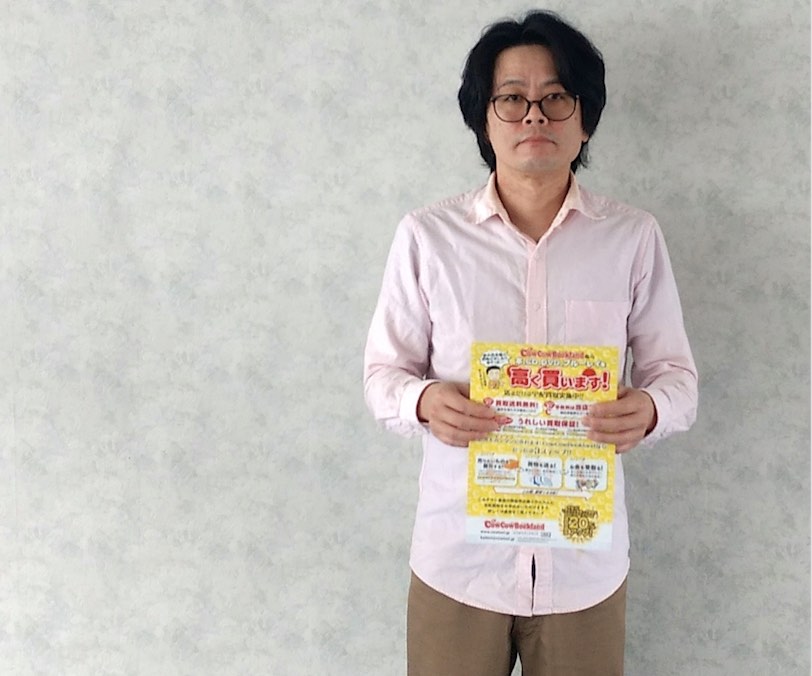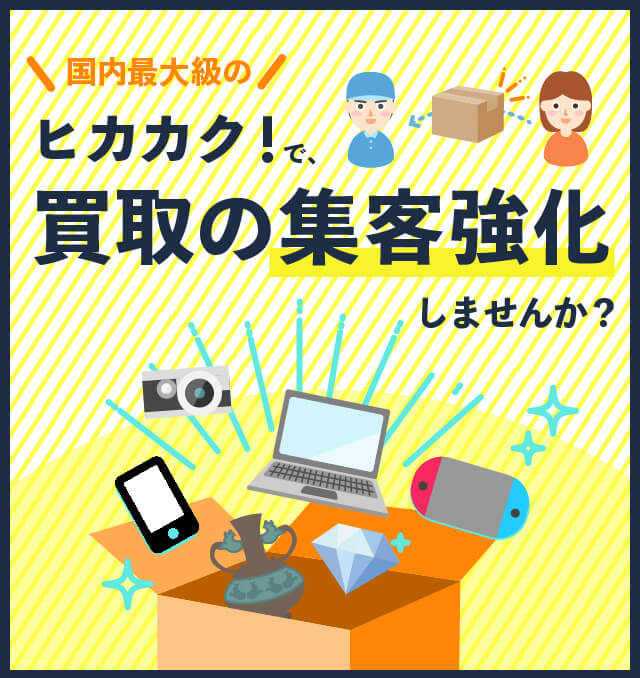街やネット上で多く見かける古本屋は、どのようにして成り立っているのだろうか。今回は古本屋の仕組みを知るために必要な要素である古本屋の仕入れや原価率、廃業率について詳しく解説していく。業界内でしか知られていない事柄も多く紹介していくので、古本屋の仕組みに興味がある方は参考にしてほしい。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古本屋とは
古本屋は古書を扱う書店のことで、古物商の1つである。古本屋自体は古くからおこなわれている仕事であり、一説によると貸し本屋が中古本収集をおこなうようになったのがきっかけで、古本屋文化が発達していったと言われている。
近年ではせどりが個人でもおこないやすいこと、店舗を持たずにネットで本の売買ができることが関係し、副業として古本屋業を営む方が増えてきている。古本屋として実店舗営業をおこなうには古物営業法に準じて、店舗地域を担当する都道府県公安委員会の許可が必要だ。
店舗を持たない古本屋も存在する
古本屋を営む方の中には、店舗を持たずamazonマーケットプレイスやECサイト、楽天市場やyahooショッピングで売買をおこなう方も多い。ネット上で無店舗営業をする場合、店舗維持費が掛からないのは大きなメリットだと言えるが、その分ネット上での宣伝活動に力を入れなければならない。
サイトやキャンペーンの充実など、購買者に認知してもらうための活動を早い段階でおこなわないと利用者に認知されず多数の同業者の中に埋もれてしまう。また、ネット利用する人をメインターゲットにしている場合は、客層のことを考えた品ぞろえをおこなう必要があるだろう。
amazonマーケットプレイスを利用する際は、FBA(フルフィルメント by Amazon)という梱包・発送をおこなってくれるサービスが活用でき、楽天市場やyahooショッピングでは運営アドバイザーや集客効果のあるサービスを受けられる。利用できるサービスは最大限に活用することで、高い売り上げ見込みが期待できる。
古本屋を開業するために必要な物
古本屋は誰でも今すぐに始められるわけではない。古本屋を開業するために必要な物を紹介していく。
古物(商)営業許可
古本屋を営む際は、都道府県公安委員会の許可、すなわち古物(商)営業許可申請が必要だ。ネットショップの場合、古物(商)営業の許可を受けているかチェックされている訳ではないので、中には許可申請を所持していない店舗も見られる。古物(商)営業許可申請をおこなうには以下の物を準備する必要がある。
- ・申請書類
- ・手数料約2万円
- ・住民票や身分証明証
- ・委任状(営業責任者本人以外が申請をおこなう場合)
- ・ホームページがある場合はプロパイダによる資料
- ・営業所の賃貸契約書、駐車場契約書
- ・法人の場合は責任者や役員全員の書類や会社書類 など
申請方法
申請は地域管轄の警察署でおこなえる。提出書類は個人や法人、業務内容によって異なるので詳細はそちらのほうで確認すると良いだろう。ゲーム機やゲームソフト、CD、電子機器などの中古物を同時に扱う場合は、書類の記入項目が増える。
仕入れはどのような方法でおこなわれる?
現代の古本屋の仕入れは、次の4つの方法がメインである。
古本卸から仕入れる
1つ目に紹介するのは、古本卸、つまり古本屋向けに古書販売する業者を利用する方法だ。古本卸は取引業者を絞っているケースがあるため、あまり存在を露出しないが、「古本 卸」などのワードでネット検索すれば中古本卸会社のホームページにヒットする。
卸会社自体が経営難になった本屋から書籍を買い取っているため品数は充実しているケースが多い。大きな古本屋を用意したい場合は、古本卸を活用すると良いだろう。
古書交換会(市場)
陶芸品や美術品の世界では良くあることだが、古本の世界でも業者市に参加して売り物を仕入れる方法がある。業者市に参加するには、各都道府県に存在する古書組合に入らなければならず、入会費が必要である。
組合参加は業界情報や同業者との繋がりを得られるメリットもあるので、参加しておいて損はないだろう。ちなみに古物商同士の業者市を自身で開催したい場合は、古物市場主(二号営業)の許可が必要である。
客からの買取
お店に訪れた客からの買取も商品の仕入れとしての側面を持つ。買取するときに客に良い印象を与えれば、買取のリピーターを増やすことも可能なので、適切な買取金額を提示するのが基本だ。
店舗がない古本屋でも出張買取をしたり、郵送買取の窓口を用意しておくことで買取による仕入れがおこなえる。他店より高値買取をすることで買取依頼を申し込む客は増えていくが、利益効率が悪くなることを忘れてはいけない。
せどり
せどりは古本屋やオークション、各ネットショップを巡回して、掘り出し物や販売価値のある品物を自らの眼で探し出す方法である。組合に参加したり、客からの買取依頼を待たなくても良いのは、せどりの大きな強みだと言える。
古本屋では専門外の本を安価で売っているケースが多々あるため、知識と熱意さえあれば利益を出せる品物を仕入れることができる。ちなみにネット上でおこなわれるせどりは電脳せどりと呼ばれ、簡単に調査と取引をおこないやすいのがポイントだ。
仕入れる本はどのような物が多い?
古本屋にとって仕入れ対象になるのは、仕入れてからすぐ売れる見込みのある本である。利益の大小よりも売れるかどうかが古本屋事業にとって重要だ。例え希少価値のある古本を見つけたとしても、長期的に並べておかないと捌けないような本は、在庫としての負担のほうが大きくなってしまう。
数年後に得る1万円の売り上げと仕入れから数日の間に得る1,000円のどちらが、古本屋の営業を支えているのか、店舗維持や人件費に掛かる金額を考えれば答えは明白だろう。
古本屋が仕入れる本の原価率は?
中古物販売に限らず商売では、経費の関係から3割〜5割の原価率に留めるのが一般的である。しかし、古本屋の場合は5割以上、場合によっては8割の原価率で仕入れているところもある。なぜこのように原価率の高い仕入れをおこなっている古本屋が存在するのだろうか。なぜなら前述したように早い段階で利益に結びつくかどうかが店舗経営にとって大事だからだ。
基本的に古本屋は利益ありきの商売である。いくら原価率を安く抑えても売れなければ意味がない。在庫を抱えているよりも、薄利多売で利益を出していったほうが商品の回転率が上がり、客とのやり取りは活発になる。
古本屋の廃業率は?
古本屋を開業する人からすると気になる廃業率は、どの程度なのだろうか。詳しいデータは発表されていないが、一般的な書店の場合、2016年では25店が廃業・倒産しており前年度と比べると1.5倍の廃業率である。
廃業率が増えた原因には、電子書籍普及による紙離れが影響していると見られている。廃業した古本屋のうち、1億円を下回る負債金額での倒産は13件あるので、小規模事業者の活動が難しくなっていると判断して良いのかもしれない。
上記の例を踏まえると古本屋の場合、同様に電子書籍の影響を受けつつ、一般書店より遥かに業者数が増加し、供給が飽和しているので廃業率は一般書店よりさらに悪化している可能性が高い。
古本屋が廃業してしまうのは何故?
古本屋の廃業理由として、多く見られることの1番は十分な利益を出せなかったことが原因だが、細かく分けると利益を出すことへの認識の甘さや品物管理の難しさが要因として挙げられる。
運営に必要な利益が出せない
古本は1点の売り上げ金額が少ないので、たくさんの量を捌いていかなければ商売にならない。光熱費や家賃、設備費、本の仕入れ代や維持費用などの経費代も稼がなければいけないことを考えると固定客を多く獲得しない限りは苦しい経営を強いられるだろう。
しかし、現代ではそうした商売の難しさとは裏腹に、古本屋業の自由なイメージに憧れてサラリーマンから古本屋に転職する方が増加している。脱サラして古本屋業を営む方々は、地道にコツコツと利益を出すという現実を認識できていないケースが多く、廃業率の増加に加担しているのが現状である。
大量の本を被害から守るのは難しい
本を売り物にする以上、本の管理をしっかりおこなう必要がある。しかし、いくら気を使っていても懸念材料となるのが万引きや災害などによる被害だ。万引き被害の場合、扱う本の点数が多いほど対応しづらくなる。
少量の盗難でもその分の金額を売り上げるまでに時間が掛かるため、被害を避けなければいけないが、監視カメラや人員配置をするための資金を補うのが難しく、本を万引き被害から守るのは大変なのである。
また、不意の水害や火災、震災に弱いのも管理が難しい点だと言える。品物である本がこれらの被害に遭い、保険適用したとしても販売利益に相当するような金額はまず戻ってこない。大規模な災害で品物が失われてしまえば、その時点で廃業を視野に入れる必要性が出てくる。
古本屋の業務効率を上げるテクニック
古本屋は、運営する上で注意しなければいけない事柄が多い事業だ。これから古本屋を始めようとしている方にとって不安を感じる要素が多かっただろう。しかし、これから紹介するテクニックを用いれば、集客や効率化の懸念を大幅に解消できる。
人件費を用意してスタッフを雇う
販売から利用客の対応まで全てを自らでおこなうのは、決して悪いことではない。しかし、商品の梱包や発送を1日に何十人分もおこないながら、店頭での応対も兼ねるというのは大変で、ミスの量が増える可能性がある。
ミスによりクレームが多くなると対応や補填にも向き合う必要があるので、人員を確保して余裕のある業務を初めからおこなうほうが自分自身はもちろん、お店のためになる。本に影響する万引き犯罪や被害は、スタッフを増やすことで防げる可能性が高いので人員はできる限り確保しておこう。
ホームページを作る
店舗を持たずにamazonマーケットプレイスや楽天市場などを利用して古本販売をおこなっていたとしても、ホームページを用意することで、品ぞろえや活動内容をより詳しく利用客に知らせることができる。告知やセール商品、買取強化商品の連絡などを発信すれば、集客や利益への効果も期待できるだろう。
サイトデザインはこだわりがなければ無料テンプレートの見やすいものでも良いが、SEO対策は検索表示や訪問者アップに関係するため重要だ。
宣伝チラシを配布する
ネットショップや実店舗の集客に欠かせないのが、宣伝チラシの配布である。ネット社会の今、チラシに効力があるのか疑問を持つ方もいるかもしれないが、ホームページを作ってもアクセスが少ないと自身のサイトが検索結果で上位に表示されず、一向に注目は集められない。
古本屋を運営する際はチラシを配って、存在を多くの方に知ってもらうところからスタートしよう。地域のネットワークやSNSアカウント、各宣伝媒体を利用できる場合は、それらの活用もぜひ考えてみてほしい。
まとめ
ここまでで古本屋についてや開業するために必要な手順、仕入れ方法ごとの特徴、廃業率や売り上げを伸ばすためのテクニックなどを述べてきた。今までは店舗を持って営業することが多かったが、近年はサイトやECショップを利用してネット上で古本屋業を営む方が増えてきている。仕事として営業するには都道府県公安委員会の許可が必要で、古物(商)営業許可申請を済ませる必要がある。
仕入れる本は回転率が良く、売れやすいものが基本だ。原価率が高くても回転率を重視しなければ利益に結びつかず、店舗に利用客が集まらない。最近は通常の本屋が電子書籍の影響で、売り上げを上げるのに苦戦している。そのため個人業者が多く存在し、飽和状態になりつつある古本屋も廃業率が高いとみるのが妥当である。
営業する上での注意点が多い古本屋だが、チラシやホームページで宣伝をしっかりおこない、スタッフを雇って業務の効率化を実現していくことで運営は軌道に乗りやすくなる。これから古本屋業や古本による売買を始めようとしている方は、今回紹介した内容を頭に入れて損をしない運営をおこなえるように心がけよう。