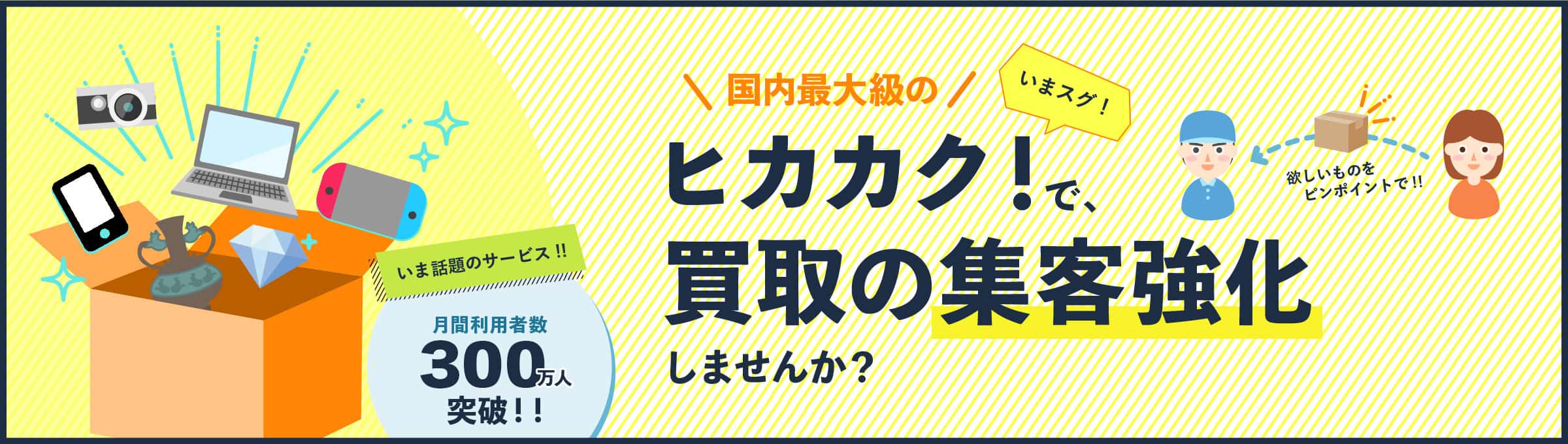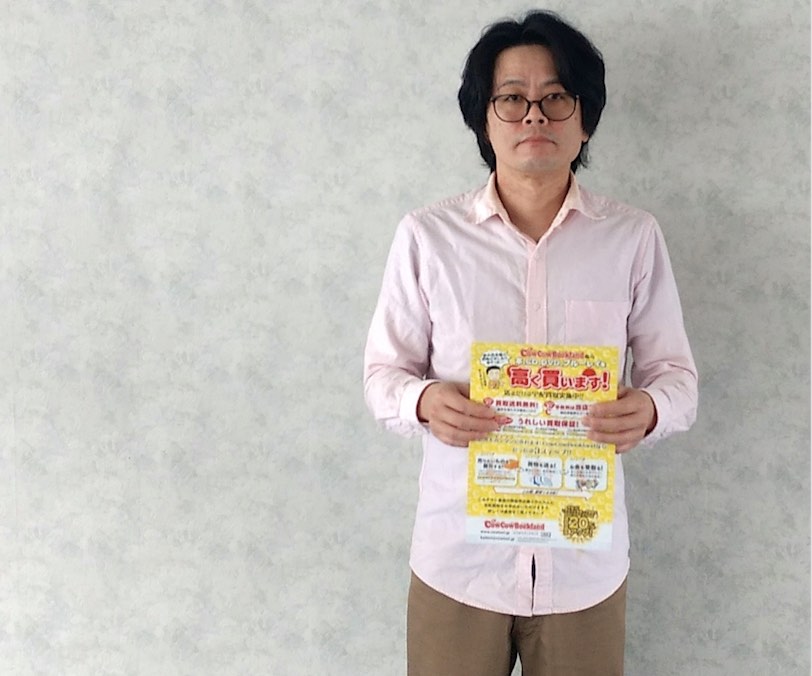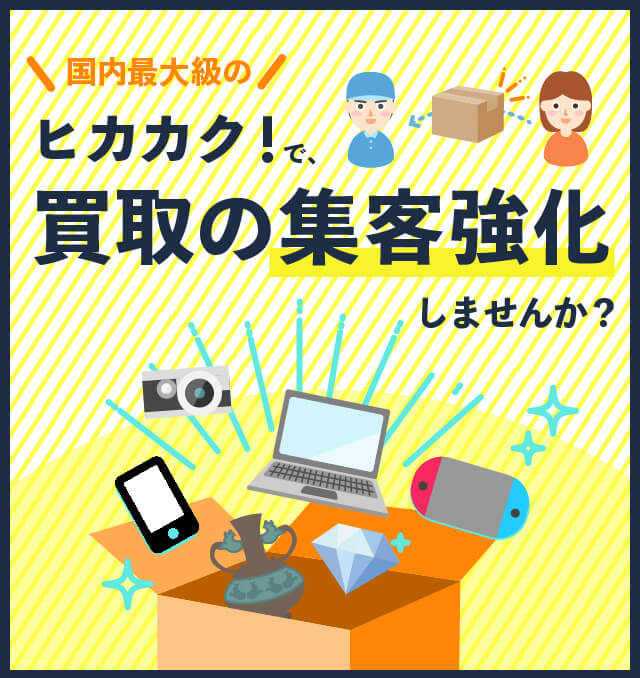本好きな方であれば、1度は古本屋を開業して仕事にしたいと考えたことがあるかもしれない。本の仕入れから販売、本に囲まれて仕事ができて、趣味を仕事にしているイメージが強いのではないだろうか。しかし、古本屋を営むとして年収はどのくらいになるのか、生計がたつのかどうかなどイメージがわきにくい職業だ。
古本屋が儲かる仕事だというイメージはあまりないだろう。しかし、年収がある程度見込めなければ仕事としてやっていくのは厳しい。仕事を始める上で年収は気になるところだ。この記事では古本屋について説明していく。古本屋を開業してみたいと考えている方は、ぜひ目を通してほしい。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
本屋の状況
古本屋についてみていく前に本屋業界全体の状況を確認しよう。近年、電子書籍の普及などにより書籍の売り上げは減少していることは、よく耳にするのではないだろうか。また、書籍を買い求める場合でもインターネット上のサイトで購入するケースが多くなっており、実店舗を持つ本屋の経営状況が良いとは言えない。
書店数は年々減少している。そのため、本屋は戦略的な経営が求められている状況にあると言える。例えば、訪れた人がコーヒーなどを飲みながら本を読むことのできるブックカフェを併設するなどの取り組みがある。本屋の経営で収益を伸ばしたいという場合には、本屋も個性を打ち出していく必要がある時代となっている。
古本屋を開業するには
古本屋を開業すること自体は比較的簡単にできる。古本屋を開業するための手続きとして、古物営業許可申請をおこなう必要がある。開業する店舗の住所を管轄する都道府県の警察署防犯課、あるいは生活安全課に申請する。
申請には約2万円の申請手数料と書類が必要となり、期間は1~2か月ほどかかる。許可が取れた後は屋号をつくり、開業届を出す。
店舗の経営
店舗を持つ場合は立地も重要だ。例えば、オフィス街にある本屋と住宅街にある本屋では訪れる人が求める本も異なる。オフィス街ではビジネス書、住宅街では子育て本や料理本のニーズがあると考えられる。
開店資金が安いという理由で人通りのないところに出店しても長期的に人を呼び込めるのかどうか考えてみた方がいいだろう。また、クレジットカード払いに対応できることが望ましいだろう。
近年はキャッシュレス化が進んでいるため、現金は多く持たずカード払いや電子マネー払いで対応している人も多くなっている。多少値の張る本を買いたいときに現金支払いのみであれば持ち合わせがなくて購入につながらない可能性も出てくる。高額な本を扱う場合には特に導入をおすすめしたい。
インターネット販売
古本屋を開業する際、必ずしも実店舗が必要な訳ではない。実店舗を持つには、やはりそれなりのコストが必要となってくる。物件を取得、内装工事をし、本棚を用意するなどの経費がかかるためだ。
しかし、インターネット上で古本を販売するという方法もある。その場合、初期費用が大幅におさえられる。店舗を持ちたい場合でも、まずインターネットでの販売から始めて、開店資金が貯まったら店舗をオープンさせてもいいだろう。
また、インターネットを利用することのメリットとして、その本について興味のある人の目に届きやすくなる。実店舗を持つにしても、インターネット上にも販路があれば購入される機会は桁違いになるので、導入を検討しておきたい。
古本の仕入れ方法
古本屋を営むためには、商品となる古本を用意しなければならない。もちろん、まずは手元にある自分のコレクションを売っていく方法もある。しかし、それなりの数をそろえるためには仕入作業が必要となる。
古書組合の古書交換会
古本を仕入れる方法として代表的なのは、各都道府県の古書組合に入り古書交換会に参加することだ。古書組合に入るための手続きや金額は各都道府県によって異なる。加入条件を満たし、メンバーの承認を得ることが求められる。
組合員として一定期間以上在籍すれば、他の都道府県の組合での交換会に出入りも可能となる。また、組合で主催する即売会に参加できるなどのメリットがある。
古書組合の加入条件
ここでは、例として東京古書組合の加入条件をみてみよう。
1.古物営業法の規定により、東京都公安委員会から古物商の許可を受け、古書籍類を扱う小規模事業者(*)であること。(*)小規模事業者とは…資本金5,000万円以下かつ従業員数50人以下。
2.東京都の地区内に事業場を有すること。
3.前記1・2を満たした有資格者で、主として古書籍販売業に従事し、あわせてそのための店舗もしくは事務所を設置していなければならない。
4.前記3にかかわらず、名義人もしくは主として営業に従事しようとする者が、引き続き他業からの給与所得によって生計を維持する場合は承認できない。
5.新規に組合員になろうとする者は、加入申込にあたって保証人1名と連名で所定の誓約書を提出しなければならない。
6.組合に加入した後、組合の役職就任を要請されたときには、その役を引き受け、組合の運営に参画する意思があること。
加入申込に際しては、加入書類の提出が求められる。東京古書組合では、加入申込書、履歴書1通、古物許可証、誓約書、印鑑証明書、住民票の提出が求められている。加入時に納入する費用は、出資金10万円、加入金36万円、共済会基金3万円となっている。合わせて50万円ほどだ。
組合加入・脱会は原則自由だが、正当な理由がある場合は組合が加入申込者に対して加入を拒否できることが法で認められている。加入申請をしても、必ず加入できるとは限らないことは頭に置いておこう。
古書交換会
古書交換会とは古本屋同士が古本を交換する市場だ。古本屋はそれぞれの専門分野や個性があり、自店では専門外で需要のない本を交換会に出す。通常は束で出品し、入札制で最高額を出した人が落札できるシステムがとられることが多い。
交換会では出品のみ・入札のみのいずれも可能だ。ここで古本屋は本を安く仕入れて自店で売る、もしくは本を売って利益を出している。ここでも東京古書組合の場合を例に挙げてみよう。
中央市会
毎週月曜日に開催。商品はジャンルに関わらず取り扱っている。漫画、文庫から肉筆ものや和本、紙もの、CDやDVD等多種多様な出品物で埋め尽くされる。出品物の量、点数、参加業者数は交換会の中でも最多だ。
東京古典会
毎週火曜日に開催。明治期以前に書写あるいは印刷されたものを主に取り扱っているが、ありとあらゆる古典関係のものが取り扱われている。いわゆる和本・唐本・書画・古文書などと呼ばれているものだ。国宝重文級のものが取り扱われるケースもある。
東京洋書会
毎週火曜日に開催。商品は日本語と漢字文化圏の言語以外の出版物全てであり、書物は英語が主流だがフランス語やドイツ語、ロシア語も多く扱っている。
東京資料会
毎週水曜日開催。商品は、歴史関係、社会科学、自然科学、美術、学術図書、戦前・戦後の雑誌・報告書から現在発行している専門書までを扱っている。
一新会
毎週水曜日開催。以下の商品を取り扱っている。比較的新しい各分野の学術書や戦前の建築、デザイン、公的機関の報告書、和本、古地図、絵葉書などの紙類、サブカル系映画、音楽、小説、アニメ、美術・博物館カタログ、デザイン書、写真集など。
明治古典会
毎週金曜日開催。近代文学の初刊本、肉筆原稿や書簡、美術・工芸関係、近代資料、錦絵や和本、古文書・古地図などを取り扱っている。
南部支部交換会
毎週月曜日、水曜日に開催。また、毎月第2土曜日は置き入札による市場も開催している。店売り向きの一般書から専門書までを取り扱う。
北部支部交換会
毎週水曜日に開催。コミックから文庫、趣味、美術、雑誌、文学などを取り扱い、他の市場より同じジャンルのものが比較的安価に入手でき、出品者側にとっても取引不成立が少ないことがメリットとなっている。
高円寺市会
毎月第3土曜日、第4火曜日に開催。コミック、文庫、趣味、美術などを取り扱っている。第3土曜日の有料書市には、学術書やポスターなども出品される。有料書市ではネット入札にも対応しており、会場に足を運ばずとも入札が可能だ。
掘り出し物を見つけて販売する
もっと気軽な方法として、古本屋やインターネットのサイトで安く売られている本から掘り出し物を見つける方法もある。本来の価値に見合わず安く販売されている本があれば購入しておき、本の価値に見合う価格をつけて自分の店で販売するのである。
この場合も価値のある本を見極める知識が必要となるので、自分の専門分野に関してだけでも知識をつけておくことは必要だ。
古本屋の年収
古本屋の年収はどれくらいなのだろうか。これは経営状況によって幅があるので、一概に古本屋ではこれくらいの年収を得ることができる、ということは言えない。古本屋で生計を立てられるだけの収入を得られなければ廃業することになるが、儲かっている古本屋も存在しているのは事実だ。
逆に、どれくらいの年収を得たいのかというところから逆算して考えよう。単身の場合は自分が生活できる収入があればいいが、家族を養っていくためには400万円ほど必要だとしよう。古本屋を開業するのであれば、そのくらいの年収を見込めるように計画したい。
例えば副業として古本を販売して月に5~10万円ほどの収入を得たいというのであれば、それほど難しいことではない。しかし、年収400万円ほどの収益を見込むのであれば、月に30万円以上の収益を上げる必要がある。そして、月に30万円以上の収益を上げるには1日あたりどのくらい収益を上げればよいのか、というように売り上げ計画を立てよう。
古本屋は儲かるか?
古本屋には、儲かる仕事というイメージは決してないだろう。しかし、儲かるかどうかについては、どの職業でもそれぞれの手腕によるところが大きい。実際、古本屋の仕事で儲けている人も存在しているのだ。
また、古本屋の仕事に興味があっても、内情がよくわからないと儲かるかどうかのイメージもしにくいだろう。ここでは、古本屋がどのような方法で儲けているかを説明していく。
古本屋はどうやって儲けているか
古本屋は、どうやって儲けを出しているのだろうか。古本屋は大抵の場合、店舗で本を売るだけでなく、古書交換会や通販、古本市で即売会などをおこなっている。つまり、収益は店舗での売り上げだけではなく、店舗以外で収益を伸ばすことも可能である。
以下では、それらの方法について説明していく。古本屋を開業する場合は、こちらで収益を伸ばすことについても考慮に入れておきたい。
目録の通信販売
各店舗が在庫の目録を常連客に年数回送付しているケースがある。常連客はその目録に目を通し、欲しい本を注文する。この目録による通信販売は、特に専門性のある古本屋であれば大きな売上源となる。
古本市の即売会
古本市では何軒かの古本屋が集まり、即売会をおこなう。本好きの人が集まるイベントで、ここで見込める売り上げも大きい。
まとめ
全体的に見て、古本屋を含めた書店を取り巻く状況は苦しいのが現状だ。厳しい状況下だからこそ、経営戦略をしっかり立てていくことが必要だ。そのためには、古本屋がどのように収入を得ているのか知っておかなければならない。
古本屋は書店での売り上げだけではなく、通信販売や古本市の即売会でも収入を得ている。これらも活用していくことを考えておこう。店舗を持つとどうしてもコストがかかり開業のハードルが上がるが、実店舗を持たないで古本屋を開業する方法もある。まずはインターネット上のみでの販売から始めるのもいい方法だろう。
古本屋の仕組みや取り巻く状況をしっかり把握して計画を立てて運営していけば、生計を立てることや儲けることも可能だ。出版不況と言えども本好きな人はいつの時代もいるので、時代に合ったアプローチを考えていこう。