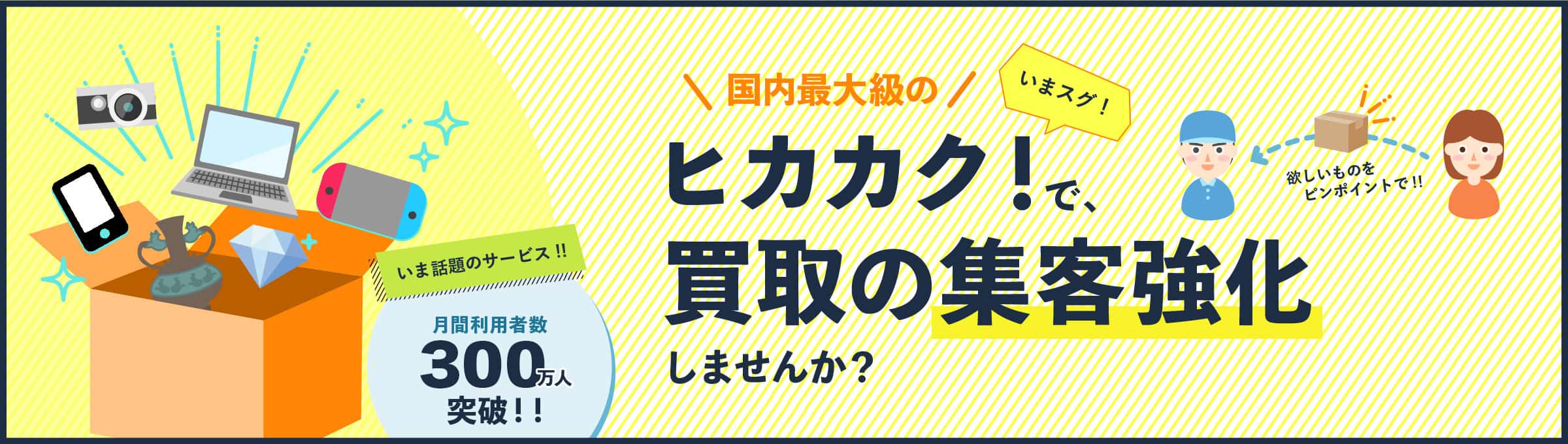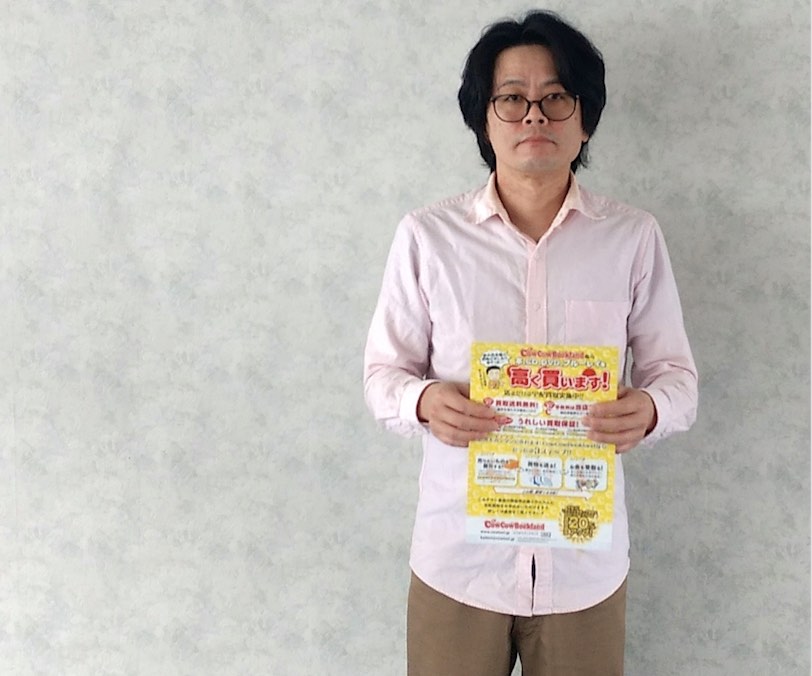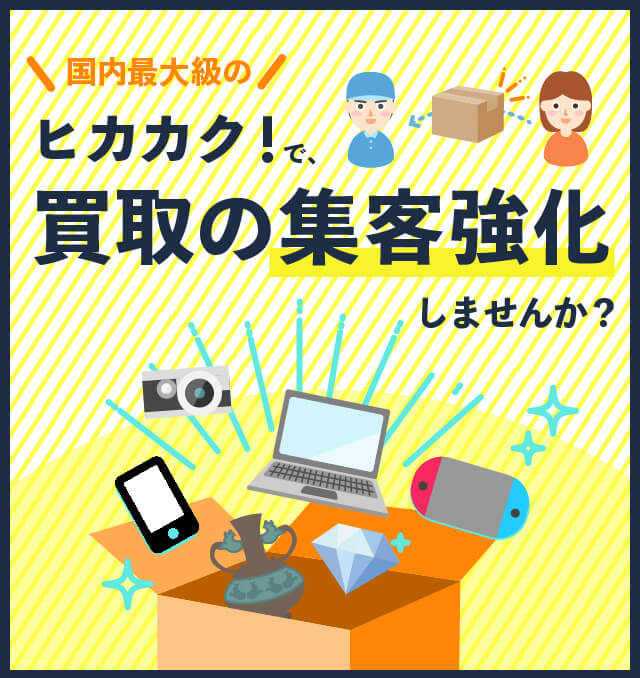古物について定められている古物営業法。古物商であっても「キチンとすべてを把握している」と言い切れる人は少ないのではないだろうか。それほど長い法律では無いが、特有の法律用語や言い回しが理解を難しくしている。「知らなかった」などという言い訳は当然通らないので、不注意からの法律違反をしないようにしたい。
古物営業法には何が書かれているのか、どんなルールがあるのか、そして罰則は何か、について解説していきたい。

CONTENTS
- 古物営業法の全体像を把握
- 古物営業法の用語
- 古物商許可の申請のやり方
-
遵守事項と罰則
- 無許可営業・不正手段による許可取得(三条)
- 虚偽申請・届出(五条一項)
- 届出義務・虚偽届出違反(七条)
- 返納義務違反(八条一項)
- 許可者の死亡又は法人の消滅による返納義務違反(八条三項)
- 名義貸し・営業停止命令違反(九条)
- 許可証の携帯義務違反(十一条)
- 行商従事者証携帯義務違反(十一条二項)
- 標識の掲示義務違反(十二条)
- ホームページへの表示義務違反(十二条二項)
- 管理者の選任義務(十三条)
- 古物商の営業の制限違反(十四条一項)
- 確認義務違反(十五条)
- 古物商の帳簿の記録義務違反(十六条)
- 帳簿等の保存義務違反(十八条一項)
- 破損帳簿の届出義務違反(十八条二項)
- 品触れの到達日記載義務及び保存違反(十九条二項)
- 電磁的方法による品触れの保存義務違反(十九条四項)
- 品触れ該当品の申告義務違反(十九条五項)
- 保管命令違反(二十一条)
- 立ち入り検査妨害、拒否等違反(二十二条一項)
- まとめ
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物営業法の全体像を把握
最初に古物営業法の概要をつかむため、簡単に各章の内容について触れていく。
第一章
古物営業法の目的と、用語の定義が書かれている。ここでは古物営業法は盗品の売買の防止が目的とされている。いわゆる「故買屋」と呼ばれる盗品専門の商売を禁止する目的だ。売り先が無ければ(現金は別として)窃盗等の犯罪の抑止ができるという考えからきている。
ここで定義されている言葉は「古物」「古物営業」「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業者」となっている。
第二章
古物商というのは許可制なので、申請方法や届出先、許可を受けられない場合、関連する細かいルールなどが定められている。これから古物商を始めようと言う方は是非理解しておきたい。加えて「古物競りあっせん業者」についての届出のルールもここだ。
第三章
「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業者」が守らなければならないルールが定められている。これに違反すれば当然罰則。
第四章
警察や公安委員会が「古物商」達を監督するために実施可能な事が定められている。
第五章
関連する事を他の規則で定める、と書かれているだけなので内容はほぼ無い。
第六章
違反者に対する罰則が定められている。
古物営業法の用語
古物営業法で使われる用語について解説していく。第一章で定義されている部分だ。ここを理解しているかどうかで「古物営業」にあたるかの判断が変わってくるので細心の注意を払っておきたい。
古物
「古物」とは、「一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」とされている。中古品だけでは無い事に注意。二つ目の「使用されない物品で使用のために取引されたもの」が非常に分かりにくい。未使用つまり新品であっても取引されたものは「古物」にあたる。
古物営業法が盗品の売買等の防止を目的としている法律である事を思い出そう。一旦流通に乗った物品である以上「転売品」や「盗品」の混入の可能性がある為である。最後の「これらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」は字面通り物品の新旧を問わず、メンテナンスや修理をして手が加わっているものを指す。
「古物」については更に古物営業法施行規則によって、「美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類」の計13の分類がされているが、これは覚える必要は無い。
あくまで例示であって、この分類に該当しないからと言って「古物じゃないから許可なしで取引しても大丈夫」とはならない。警察庁のHPにも該当しない物品は道具類に含まれる旨の記載がある。
古物商
古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う、とされている。売買だけではなく交換や委託による物も古物商の営業内容に含まれる点に注意。
古物市場主
古物市場を経営する者の事。古物市場とは古物商間の古物の売買又は交換のための市場の事。
古物競りあっせん業
「古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う」とされていて、要するにオークションで古物を扱う事。インターネットのオークションサイトも該当する。
古物営業
「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業者」が行う営業の事。
古物商許可の申請のやり方
古物商許可申請のやり方について解説する。「古物市場主」「古物競りあっせん業者」も申請や届出が必要だが割愛する。「営業所」がある場所を管轄する警察署の防犯係が申請の窓口になる。
「営業所」とは古物商として営業を行う場所で、申請時に記入する必要がある。一定期間の契約と独立性が求められるので単に場所を借りただけというのでは不適格。貸店舗やレンタルオフィスなどでは営業所に指定できない。必要書類に所定の手数料を添えて申請すれば、40日以内に許可/不許可の連絡が来る。
問題がこの必要書類で、住民票、身分証明書の他に、許可申請書(個人と法人とで形式が分かれる)、法人の登記事項証明書(個人申請の場合は不要)、法人の定款(個人申請の場合は不要)、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書、営業所の賃貸借契約書のコピー、駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピーと非常に多い。
またURLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピーが必要である。細かい記入方法などは省くが、注意の必要な物を列挙する。
身分証明書
運転免許等の事では無くて「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」事を証明するための書類である。古物商はいくつか許可の条件があり、その一つ。これらの人たちは法律行為を十分に行うことが出来ないとされるので、該当しない事の証明が必要になる。各市町村の戸籍課で発行してくれる。
登記されていないことの証明書
これは「身分証明書」とほぼ同じ内容の書類。ただし管轄が別で、東京法務局後見登録課か全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請可能。郵送も受け付けているが、その場合は東京法務局後見登録課のみが窓口になる。
営業所の賃貸借契約書のコピー
賃貸物件に住んでいる人はこれが最大の難関になる。貸主から「古物商の営業所として使用しても良い」との使用許諾書を添付する必要があるからだ。住居以外の目的に使うと聞いて、大家さんが許可を出してくれるかどうかは難しい所だ。持ち家の場合は当然不要。
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
扱う古物が車などの場合、ちゃんと保管出来る場所があるかどうかの証明書。
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ホームページを開いて営業を行う場合に必要。
許可が受けられないケース
先にも少し触れたが、許可が降りないケース(欠格事由)が存在する。
ざっと書くと「禁治産者(被後見人)・準禁治産者(被保佐人)・破産者」の場合、禁固刑以上の刑を受けて執行から5年が経過していない場合、住所不定、古物商の許可取り消しを受けてから5年が経過していない場合、未成年者、管理者がこれらの欠格事由に該当する場合、法人の場合は役員に欠格事由に該当する者がいる場合である。
遵守事項と罰則
古物営業法に定められている古物商が守るべき遵守事項と罰則についてまとめる。数は多いが罰則の重さで区別すると分かりやすい。無許可で営業したり営業停止命令を無視したり、他人に自分名義で営業させたりする悪質な物は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金で最も重い。
帳簿を作成していなかったり、保存期間を守らなかった場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっていて、次いで重い罰則となっている。届出義務違反や許可証の返納義務違反など、単なる手続き上の問題の物は10万円以下の罰金と軽い罰則になっている。
無許可営業・不正手段による許可取得(三条)
古物商は営業しようとする都道府県毎の都道府県公安委員会の許可を得なければならない。これに違反すると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
虚偽申請・届出(五条一項)
許可を申請した場合の書類に虚偽の内容があった場合は、20万円以下の罰金。
届出義務・虚偽届出違反(七条)
古物商は届出内容に変更が生じた場合は、公安委員会に変更内容を記載した届出書を提出しなければならない。これに違反すると10万円以下の罰金。
返納義務違反(八条一項)
古物商は営業を廃止した時や許可の取り消しを受けた場合は許可を受けた公安委員会に許可証を返納しなければならない。これに違反すると10万円以下の罰金。
許可者の死亡又は法人の消滅による返納義務違反(八条三項)
古物商が死亡した場合は、同居の親族または法定代理人は公安委員会に許可証を返納しなければならない。法人が合併により消滅した場合は、合併後存続する法人の代表者が義務を負う。この違反は5万円の科料。
名義貸し・営業停止命令違反(九条)
古物商は自分の名義で他人に古物商を営業させてはならない。3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっており、無許可営業と並んで重い。
許可証の携帯義務違反(十一条)
古物商は行商をしたり競り売りをする場合に許可証を携行する義務がある。行商とは営業所から離れて商売をする事。コピー不可なので注意が必要。これに違反すると10万円以下の罰金。
行商従事者証携帯義務違反(十一条二項)
古物商は代理人や使用人に行商をさせる場合、行商従業者証を携帯させる義務がある。行商従業者証は自分で作成してもいいが、様式が決まっているので注意。これに違反すると10万円以下の罰金。
標識の掲示義務違反(十二条)
古物商は営業所ごとに見やすい場所に所定の様式の標識を提示する義務がある。これに違反すると10万円以下の罰金。
ホームページへの表示義務違反(十二条二項)
古物商がホームページを利用して古物の取引を行う場合は、「氏名又は名称」「許可をした公安委員会の名称」「許可証の番号」を表示する義務がある。これに違反すると10万円以下の罰金。
管理者の選任義務(十三条)
古物商は営業所ごとに管理者を1人選任する義務がある。
古物商の営業の制限違反(十四条一項)
古物商は所定の場所以外で古物を古物商以外から受け取ってはならない。これに違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
確認義務違反(十五条)
古物商は古物の取引を行う際に、相手方の真偽を確認する義務がある。これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
古物商の帳簿の記録義務違反(十六条)
古物商は取引の際の所定の事項を帳簿等または電磁的記録方法により残しておかなければならない。これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
帳簿等の保存義務違反(十八条一項)
古物商は取引の記録を行ってから3年間はその保存をする義務がある。これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
破損帳簿の届出義務違反(十八条二項)
古物商は取引を記録した帳簿等を破損した場合は直ちに所轄の警察署署長に届けなければならない。これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
品触れの到達日記載義務及び保存違反(十九条二項)
品触れとは、警察が盗品等の発見を容易にするため質屋・古物商に特徴を触れ示す事。これを受けとった古物商は関連書類に到達の日付を記載し6ヶ月保存する義務がある。これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
電磁的方法による品触れの保存義務違反(十九条四項)
電磁的方法による品触れについても、古物商は到達から6ヶ月保存する義務がある。これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
品触れ該当品の申告義務違反(十九条五項)
古物商は品触れのあった古物を保持していた場合、また保存期間内に該当する古物を受け取った場合は、直ちに所轄の警察署長に届けなければならない。これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
保管命令違反(二十一条)
盗品と疑いうる十分な理由のある古物については警察本部長等は三十日以内の期間を設けて保管を命じる事が出来る。これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
立ち入り検査妨害、拒否等違反(二十二条一項)
警察は必要な場合、古物商の営業所・古物の保管場所等に立ち入り、検査、質問する事が出来る。これに違反すると10万円以下の罰金。
まとめ
古物営業法には何が書かれていて、どんなルールや罰則があるか解説した。もちろん、「知らなかった」では通用しないので、現在古物商の人もこれから営もうとしている人も、きちんと内容を理解しておこう。