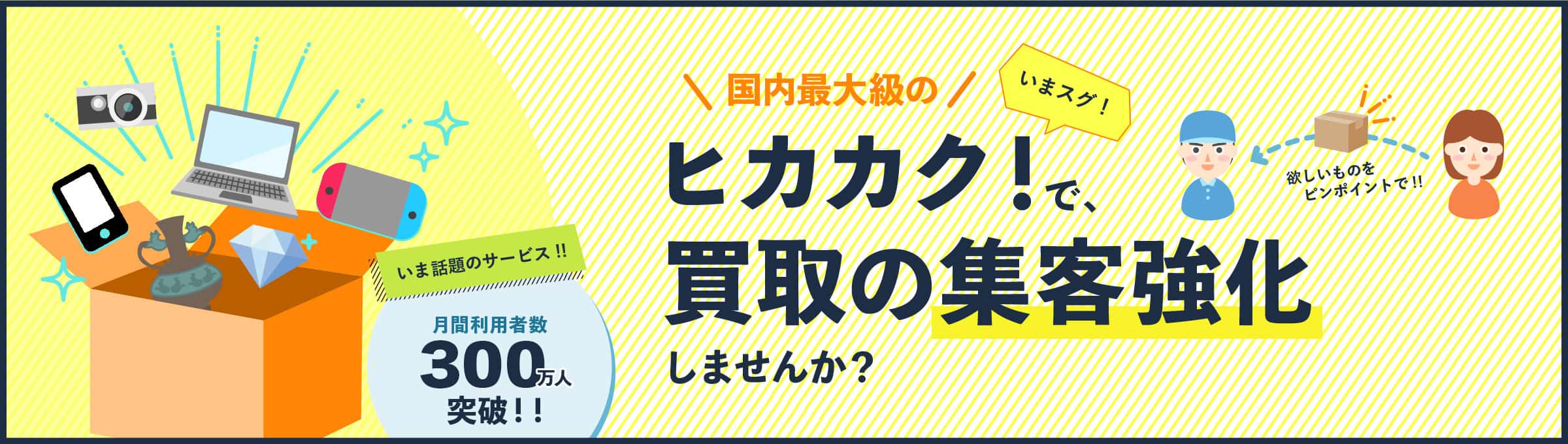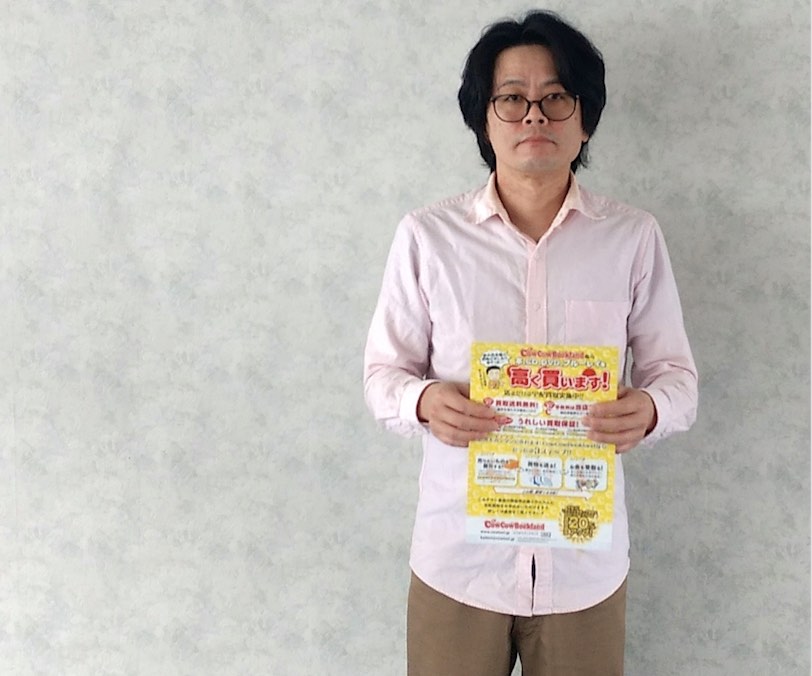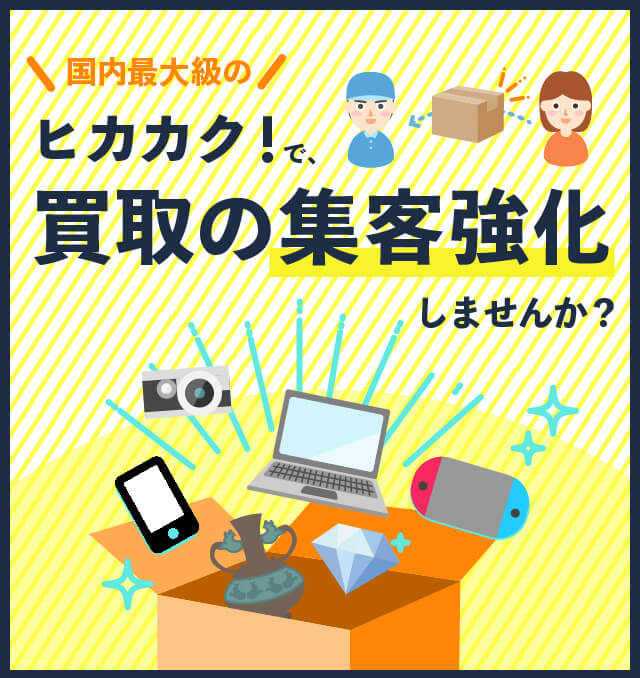古物商許可申請書に「行商する・しない」という欄が出てくる。この記事では、行商する・しないのどちらを選ぶべきか、古物商許可申請の流れや行商の定義も含めて説明していく。古物商を営む際、どちらを選択するかでビジネスの幅に違いが出てくるので要チェック項目となっている。以下をぜひ参考にしてほしい。

CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物商とは
古物商とは、古物(中古品)を売買したりレンタル・交換をおこなったりする個人や法人のことだ。日本で古物商となるためには、古物商許可申請という行政手続きが必要となる。
なお、古物商許可を取得せずに古物取引をおこなった場合、無許可営業として3年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金が科される場合がある。また罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなるので注意だ。
古物とは
次に、そもそも古物とは何かというところについても確認しておこう。古物の定義は、一度使用したもの、使用されないもので使用のために取引されたもの、そしてそのようなものに幾分の手入れをしたものとなっている。
また、古物は法律で以下の13種類に分類されている。古物商の許可を得る場合、以下から自分が扱うものを選択することになる。自分に扱うものがどれか判断に迷う場合は、警察署に確認しよう。
- 1.美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品など
- 2.衣服:洋服類、和服、その他衣類
- 3.時計・宝飾品:貴金属、装身具、宝石類
- 4.自動車(部品含む):中古車、ホイールなどの部品
- 5.自動二輪、原動付き自転車(部品含む):中古のオートバイ、カウルなどの部品
- 6.自転車(部品含む):中古自転車
- 7.写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズなど
- 8.事務機器類:オフィス機器全般
- 9.機械工具類:工作機械、土木機械、工具類
- 10.皮革・ゴム製品:鞄、靴など
- 11.書籍類:中古本、マンガ、雑誌
- 12.道具類:家具、雑貨、楽器など
- 13.金券類:商品券や乗車券など
以下のものは古物ではないので、合わせて確認しておこう。
- ・20トン以上の船舶、鉄道車両、航空機、5トンを超える機械など(船舶を除く)
- ・庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類
- ・古銭、趣味で収集された切手やテレフォンカード類
古物商許可申請の方法
ここでは、古物商許可申請の方法を紹介する。まず、古物商許可が必要かどうかを確認しておこう。古物を取り扱う場合でも、例外的に以下のケースは古物商を取得する必要がない。
- ・自分で使用するために購入したものを売却する
- ・無償でもらったものを売却する
- ・海外で購入したものを売却する
- ・自分が売却した相手から、その商品を買い戻す
古物商を取得するためには、警察署を経由して都道府県の公安委員会に許可申請をおこなう必要がある。申請場所は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係だ。手数料は19,000円で、申請時に警察署会計係窓口で納入する。不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返却は不可能だ。
申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡が入る。なお、40日という期間は申請日翌日から起算したもので、土日祝日・年末年始は含まれない。書類の不備や不足、差し替えなどがあれば、遅れる可能性がある。申請には、以下の書類が必要となる。
法人の定款
法人として古物営業をおこなう意思確認のため、法人の目的欄に古物営業を営む旨の内容が読み取れる記載が必要となる。例えば、「〇〇の買取、販売」「〇〇の売買」といった記載だ。
法人の目的欄に古物営業をおこなう旨が読み取れる文章がない場合や、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある役員会議の議事録の写し、あるいは代表取締役の署名押印のある書面(確認書)をあわせて提出する。
定款はコピーでも可能だが、その場合は末尾に「以上、原文と相違ありません 令和〇年〇月〇日 代表取締役〇〇(代表者氏名) 代表者印」と朱書・押印する必要がある。
住民票の写し(外国の方は外国人登録証明書の写し)
本籍(外国人の場合は国籍)が記載されたもので、個人番号の記載がないものを提出する。
身分証明書
ここで言う身分証明書は免許証や保険証明書ではないので注意だ。禁治産者(成年後見人)や準禁治産者(被保佐人)、破産者でないことを証明するためのものとなっている。各市区町村の戸籍課などで取り扱っている。
登記されていないことの証明書
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)で取得できる。支局では取得できないので注意だ。郵送で申請できるのは、東京法務局後見登録課のみとなっている。住民票を参考にして手書きで記入する。
誓約書
古物営業法第4条に該当しない旨を誓約する書面だ。個人許可申請で、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を提出する。個人用と管理者用の2種類を提出する必要はない。
法人許可申請で、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる人物がいる場合、管理者用の誓約書を提出する。これについても、その人物については役員用と管理者用の2種類を提出する必要はない。
本人が内容確認の上、本人の署名または記名押印をする。外国人の場合は、母国語の訳文をつけるか、本人署名欄の下に「上記誓約内容を〇〇語で通訳し、理解した上で本人が署名しました 通訳人〇〇(署名)印」という記載が必要となる。
5年間の略歴書
最近5年間の略歴を記載するものだ。本人の署名または記名押印が必要となる。5年以上前から経歴に変更がない場合は、以後変更ない・現在に至るなど記載しておく。
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業所が正規に確保されているかどうかを確認するためのものだ。営業所が自己所有でない場合は、賃貸契約書のコピーが必要となる。
なお、分譲・賃貸に関わらず、マンションや集合住宅など目的が居住のみに限られている場合や、営業活動が禁止されている場合は営業所として申請することができないので注意だ。その場合、所有者や管理者から古物営業の営業所としての使用承諾書を作成して添付しなければならない。
駐輪場など保管場所の賃貸借契約書のコピー
自動車などの買取の場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものだ。賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真など保管場所が確認できる資料を添付する。
プロパイダなどからの資料のコピー(URLを届け出る場合)
インターネットを利用して古物を売買し、独自のドメインやオークションサイト内にサイトを開設する場合は、URLを届け出なければならない。URLの使用権限を証明するために、プロパイダやオークションサイト運営者からURLの割りあてを受けたことの通知書を入手する必要がある。
プロパイダなどから交付されたURLの割りあてを受けた通知書などのコピー、あるいはインターネットでドメイン検索かwhois検索を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付する。
いずれの場合も、ドメインの登録内容が個人の場合は本人、法人の場合は法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容でなければならない。URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も必要となる。
委任状
行政書士など第三者に申請を依頼する際に必要となる。法人許可申請で社員が申請書を持参する場合は、社員証も持参する必要がある。申請者は、営業内容などについて答えられる人物でなければならない。
行商とは
行商とは、自分のお店(営業所)以外の場所で古物営業をすることだ。例えば、デパートの催事場や露店で販売したり、お客様の家を訪問して販売したりする行為は行商にあたる。また、中古市場での取引も行商行為となっている。古物営業法では、行商の出張エリアは制限されておらず、営業所のある都道府県外でも行商をおこなうことが可能だ。
行商の際の注意点
古物の買取や売買の委託などに関しては、自分の営業所か取引相手の住所・居所でおこなわなければならない。つまり、売却に関してはどこでもできるが、買取は自分の営業所か取引相手の住所・居所でおこなう必要があるので注意だ。なお、行商の買取の制限は古物商間では適用されないので、古物商同士であればどこで古物を買い取ってもよい。
また、行商をおこなう際には古物商許可証を携帯する必要がある。これはコピーは認められない。従業員が行商をおこなう場合は行商従業者証を携帯しなければならない。行商従業者証は自分で作成可能だが、他から入手することも可能となっている。しかし、以下の様式が定められている。
- ・サイズは縦5センチ、横8.5センチ。
- ・材質はプラスチック、あるいはこれと同程度の耐久性が必要。
- ・氏名および生年月日の欄には、行商する代理人の氏名および生年月日を記載する。
- ・写真の欄には、行商する代理人の写真(縦2.5センチ以上、横2センチ以上)を張り付ける。
「行商する・しない」どっちがいい?
古物商許可申請書に「行商する・しない」の欄がある。自分が行商するかどうかわからない場合は、「行商する」に〇をつけておくことをおすすめする。知らずに行商していたというリスクを回避することができるし、ビジネスチャンスを広げることもできるからだ。
「行商しない」を選択した場合
では、「行商しない」を選択した場合は、どのような事態が予測されるのだろうか。「行商しない」を選択するということは、営業所以外では古物取引ができなくなるということだ。営業所、つまり店舗で一般の客から買取をすることは可能である。しかし、これだけでは品ぞろえに苦労する可能性が高いし、ほしい品物が手に入るとも限らない。
「行商しない」を選択すると、卸業者や引越し業者などに出向いて品物を仕入れることができない。また、古物市場で仕入れることや在庫を売却することもできなくなってしまう。
古物市場は定期的に開催され、安い値段で大量に仕入れることができるため、仕入れ先としてぜひ利用したいところだ。まとめると、「行商しない」を選択した場合、安く大量に品物を仕入れることが難しくなり、古物商を営む上でネックとなる可能性が高くなると言える。
「行商しない」から「行商する」に変更する方法
では、「行商しない」を選択してしまった場合はどうすればいいのだろうか。実は、「行商しない」を選択した場合でも、「行商する」に変更することは可能だ。そのためには、変更申請と古物許可証の書き換えの申請が必要となる。
窓口は、許可証の交付を受けた警察署の防犯係だ。ただし、許可取得後に営業所を移転して届け出をしている場合は、届け出後の営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要がある。
申請は変更があった日から14日以内におこなう。書き換えの申請には、許可証の書き換えや申請手数料の納入などの手続きが必要なので、時間に余裕を持っていくことをおすすめする。手数料は一通1,500円であり、警察署会計係の窓口で納入する。
他に変更したい項目がない場合は、変更届出書・書換申請書の1枚のみを記入する。記入したものは2枚提出する必要があるが、そのうち1枚はコピーでもよい。
まとめ
以上の内容から、古物商を営む上で行商は大事な要素だということがわかっていただけただろう。「行商する・しない」の欄では、申請どきには行商を考えていない場合でも「行商する」を選んでおくことをおすすめする。
もし「行商しない」を選択した場合、商売の幅が限られてしまい、「行商する」に変更するにも変更申請の手間がかかってしまう。「行商する」を選択して、行商行為でビジネスチャンスを広げておきたい。