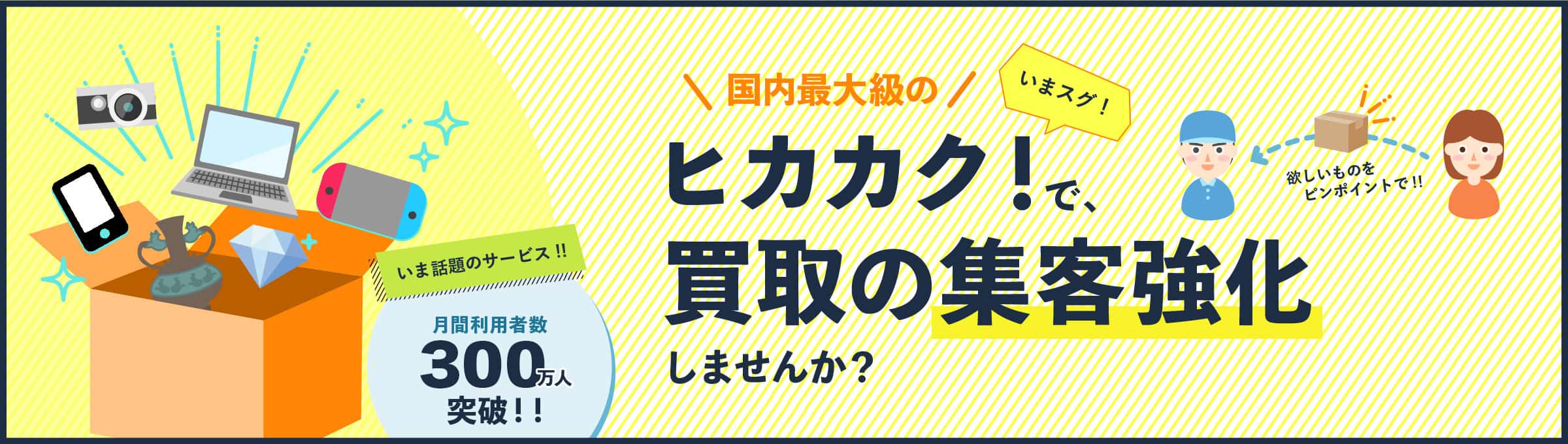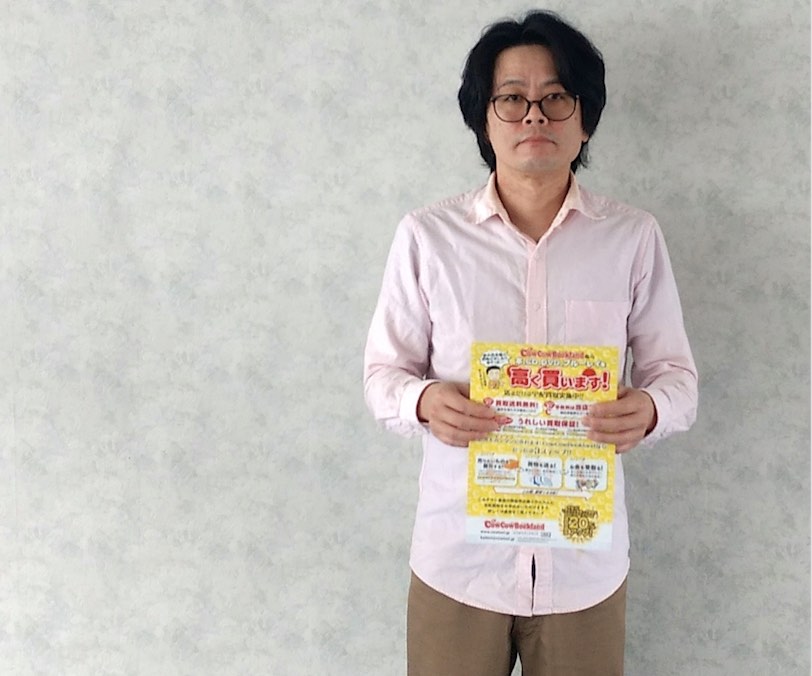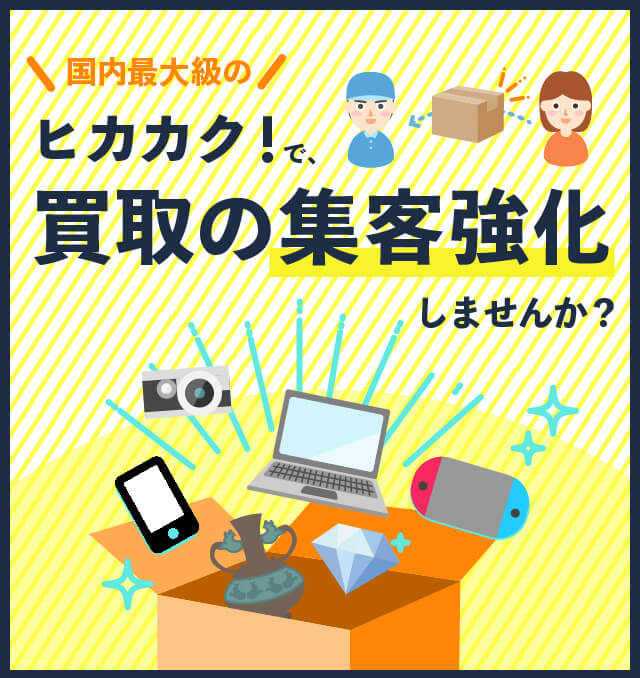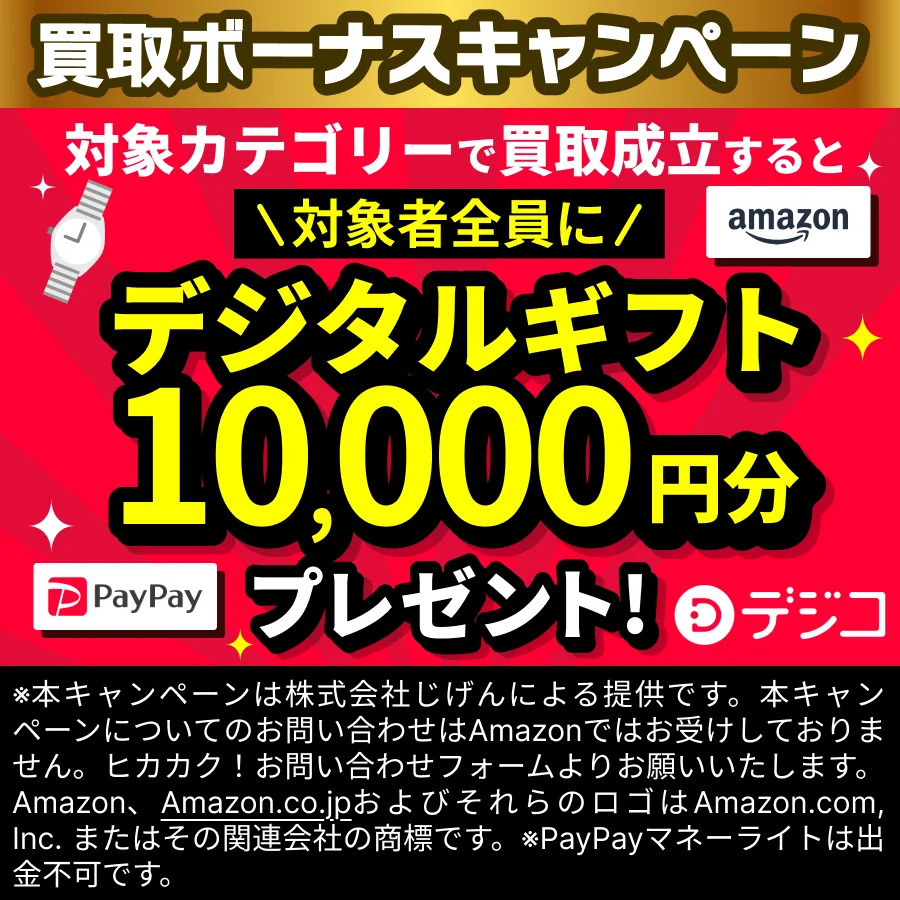中古品として多く買い取られている物の代表といえば書籍ではないだろうか。古書店が多く存在する東京都の神田町には100を超える古書店がある。
身近な所で書籍の買取を行っている店舗としてすぐに思い浮かべるのが、「ブックオフ」だが、インターネットや電子書籍の普及によって紙の書籍を扱う書店は経営が難しくなっている。リユース販売とはいえど書籍を扱う業界全体の問題といえるだろう。
そんな状況の中、老舗書店さえも苦戦を強いられるにも拘らず「ブックオン」という屋号を掲げて新たに新刊書店を始めた企業がある。この名前を聞いた人はすぐに「ブックオフ」を思い浮かべるのではないだろうか。

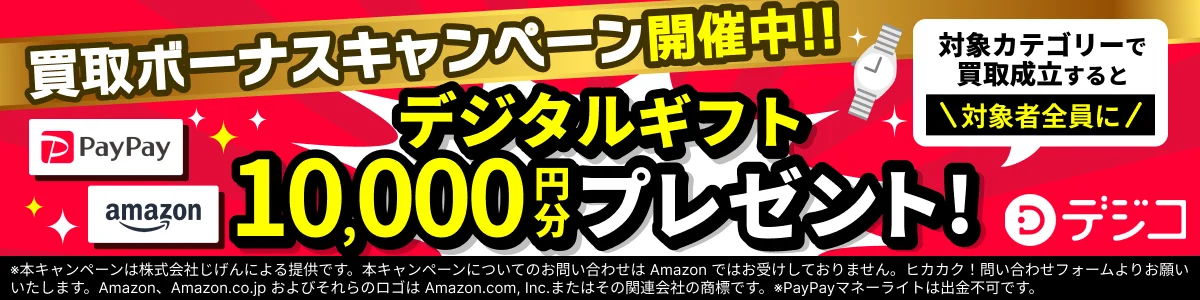
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
中古品リサイクルの「ハードオフ」が新刊書店を開業
あえて苦戦を強いられる業界に挑んでいるのは、全国で中古リサイクル販売業を展開している「ハードオフ」だ。2017年11月10日に新刊書籍を販売する「ブックオン」を千葉県四街道市に1号店を出店した。児童書5,000冊を含む33,000冊の蔵書数で、年中無休、10時〜20時まで営業する。
新刊書籍を新たな収益源にすることが目的としているが、現在進行形で業績が苦しい書店業界に活路を見い出したのはなぜなのだろうか?
ネットアプリの台頭で「ハードオフ」は業績悪化
中古品の売買もネットを経由して個人同士で取引ができるようになり、メルカリなどのフリマアプリもどんどんと進化を続け、問題を抱えながらも利用者数が増えている。
中古品の売買は個人間の取引へ移行しており、出品価格も出品者が決めるのを前提としており、店舗に言われるままの価格でしか買い取ってもらえなかったものだが、参考とする価格はある程度自分で調べなければならないが、自分で価格を決める以上、店舗で買い取ってもらうよりも高い価格を提示することも可能だ。
もちろんそれで売れなければ、値下げ要請されて下げざるを得なくなるわけだが、何よりスマホを使って好きな時に好きなように売れる手軽さが受けている。
店舗に足を運ばなければならないリサイクル店にとってスマホを使った手軽さは脅威であり、業績にしっかりと反映されている。
ハードオフとブックオフの関係
「ハードオフ」は新刊書店の屋号を「ブックオン」としたのはなぜだろうか?
もちろん意識して似せただけではなく、読み終えた本を「ブックオフ」へ売ってもらう所までイメージしているためだ。
しかし、「ハードオフ」と「ブックオフ」は創業者同士が個人的に親しかった間柄というだけで、あくまで別企業であってしかも友好関係は保っているがライバル企業である。
だが、「ハードオフ」のリユース販売には「ブックオフ」のアイデアを多く取り入れているため、店舗の看板であるロゴマークや店内の作りも似通っている部分が多い。中には同じ建物内や隣接地にブックオフ系列の店舗が出店しているため、扱っている物が違うだけで、同じ企業が運営していると思っている人も多いだろう。
「ブックオン」1号店である「ブックオン四街道店」は総合リユースショップとして1階に今回のメインである新刊書籍販売の「ブックオン」と古書買取販売の「ブックオフ」、2階には「ハードオフ」と「オフハウス」が入っている。
「思いがけない本との出会い」
今でこそネットで書籍を買うことは当たり前となっているが、実店舗しかなかった頃はどうやって新しい本と出会っていただろう。
暇つぶしに本屋で立ち読みをしていると思わぬタイトルが目に付く。思いがけない出会いが人生を変える大きな1冊となることもある。リアル店舗の良さは多く本を読む人こそ知っている。「思いがけない本との出会い」という思いは、リアル店舗のほとんどが掲げる理念ともいえよう。
「ブックオン」はネット書店とリアル書店の違いをあげて、より良い本との出会いを提供するという。
しかし、すでに目的の本が決まっている場合にはネット書店が便利である。本屋に行って目的の本が置かれていなかった時の脱力感は計り知れない。ネット書店ではよっぽどの売れ筋商品でない限り、常に在庫があり、早ければ次の日には手に入る。
リアル店舗が増えるのは大変に良いことだと思うが、それでも苦戦を強いられている現状にリサイクルを付随して、自分の家の本棚のように気軽に利用してもらいたいというコンセプトだけでは書店業界に悪影響となりかねない。
リアル書店に求められる付加価値とは
佐賀県にはある「TSUTAYA」を展開している株式会社カルチュア・コンビニエンス・クラブが指定管理者となっている武雄市図書館には「スターバックス」を含む「蔦屋書店」が併設されており、館内の「スターバックス」で購入した飲み物は図書館閲覧スペースにも持ち込みが可能だ。
新刊書籍の購入したい場合には「蔦屋書店」へと足を運べばいい。図書館の新しい利用方法を打ち出したともいえる。借りた本の中に自分の手元に置いておきたい本が出てきた場合には便利である。
その他にもBook&Cafe形式の書店は全国に49店舗(2017年12月時点)あり、椅子やソファに座って購入前の本を読める書店はすでに当たり前になりつつある。
昔は立ち読みさえも毛嫌いされたものだが、本を探していると思った以上に時間がたってしまい、立ったままでは足も疲れてしまう。特に高齢者の来店が多い店舗では椅子が置いてあると喜ばれる。
居心地の良さを前面に出し、まずは「あそこなら行ってもいい」と思わせる必要があり、足を運んでもらって有意義な時間を過ごしてもらうためには、来店者が喜ぶ付加価値が必要である。
「ブックオン」の付加価値は?
総合リユースショップとして1つの建物の中で中古品を多く扱う中で、新刊書籍の存在はどのような位置になるのだろうか?
中古品の購入に抵抗もなく、慣れているならば、安く手に入れられるのは大変にありがたい。書籍のメディア化が多くなり、原作本が多数店頭に並ぶが、放送が終われば今度は中古品として店頭に並ぶ。放送中には新刊を扱う書店でさえも注文が追い付かなかったのに、流行はすぐに過ぎてしまう。
だが、流行に乗り遅れた人は時間さえ気にしなければ、中古品で安く手に入れられるのだ。では、もし中古と新刊どちらにも欲しい書籍があったなら、どちらを選ぶか。それは個人の考え方次第ではあるが、「ブックオン」と「ブックオフ」が同じ建物の内にある場合となると、売り上げに関わってくるだろう。
「行きたい時に立ち寄れる」ような魅力を作れるかにかかっている
断捨離や大掃除をする時に、場所を取っている読まなくなった本を売りに行くのはすでに当たり前になっている。有元のスペースの中でリサイクルを活用しながら折り合いを付けるしかない。
苦戦を強いられている書店業界に挑んでいくからにはそれなりの魅力がなければ生き残りは厳しいと言わざるを得ない。「行きたい」と思わせる魅力が既存の中古リサイクル販売だけではなく、さらなる発展を願いたいものだ。

その後
「ブックオン」は2017年に千葉県四街道市で初出店され、当時は新刊書籍と中古書籍の両方を扱うハイブリッド型の店舗として注目を集めた。この店舗は、中古品販売で成功している「ブックオフ」と「ハードオフ」のノウハウを活かし、新刊書籍を手に取る楽しさを提供しつつ、読み終わった本をその場で売却できるというユニークなコンセプトを打ち出した。
しかし、ネット書店の台頭により、リアル店舗の新刊書籍販売は依然として厳しい競争にさらされている。「ブックオン」は、当初予定された他地域への拡大が限定的で、拡大戦略は進展していないようだ。新刊書籍を扱うリアル書店の維持には、カフェ併設やリラックスできる空間の提供といった新たな付加価値が求められており、その点で「ブックオン」の展開は厳しい状況に直面している。
結果として、当初のビジネスモデルは拡大に苦戦を強いられ、リアル書店全体の生き残り戦略が問われる中、さらなる進化が必要とされている。