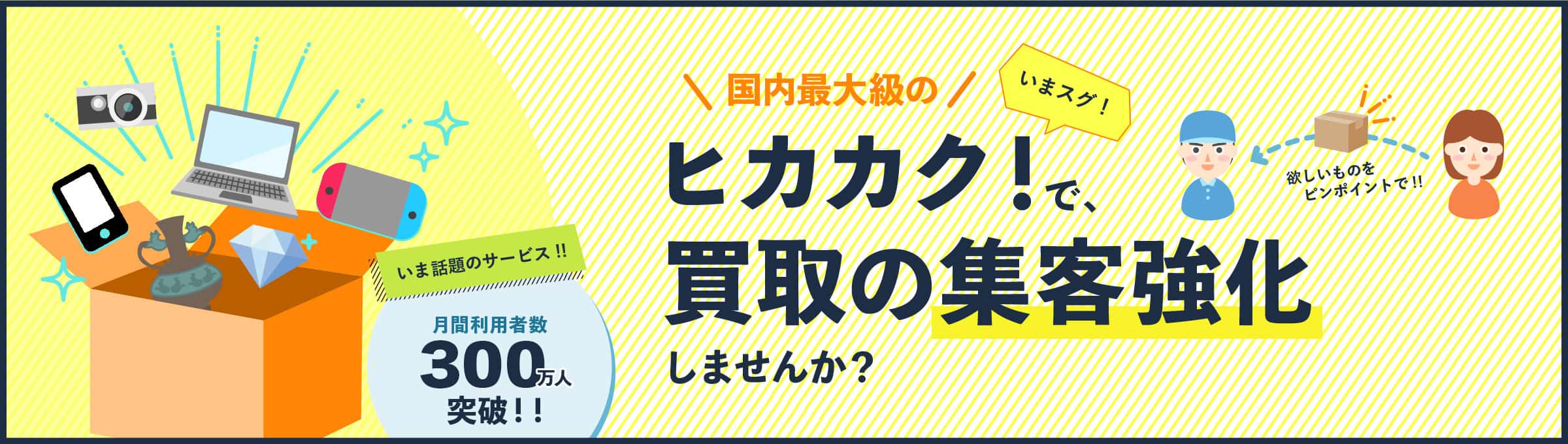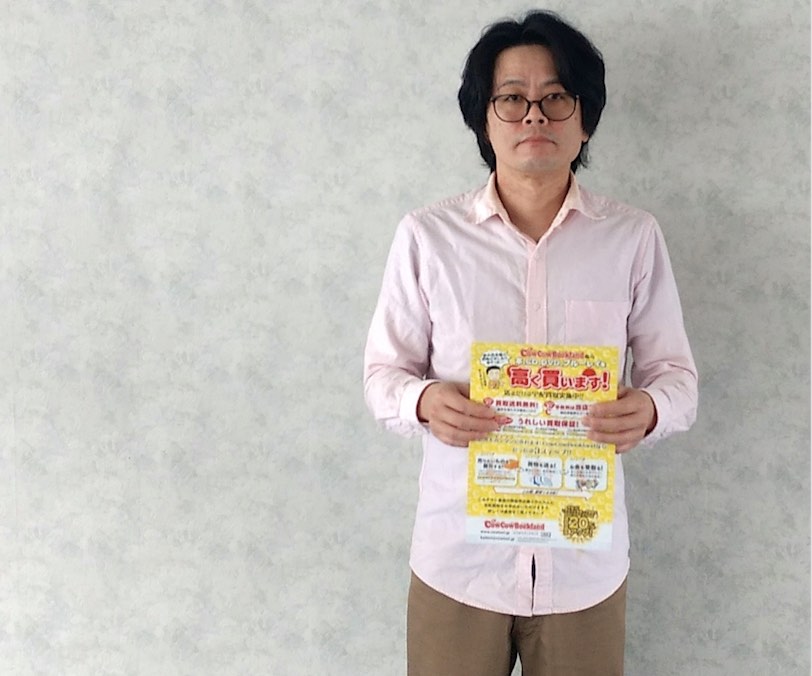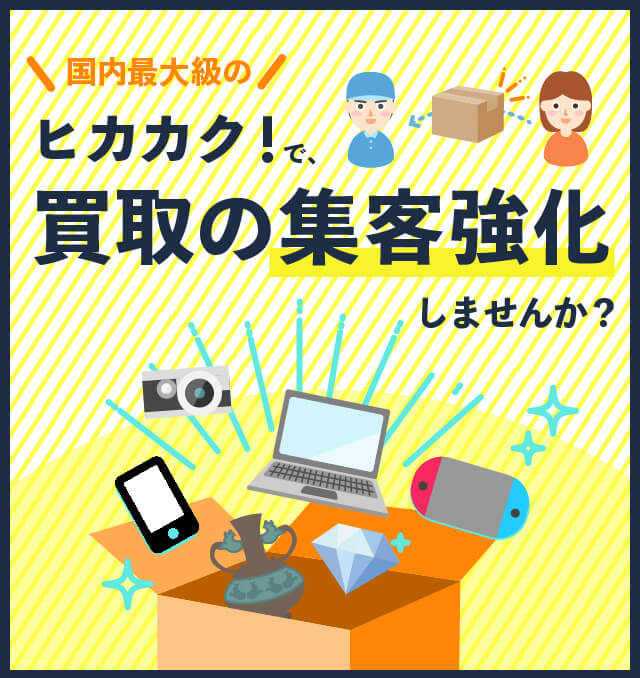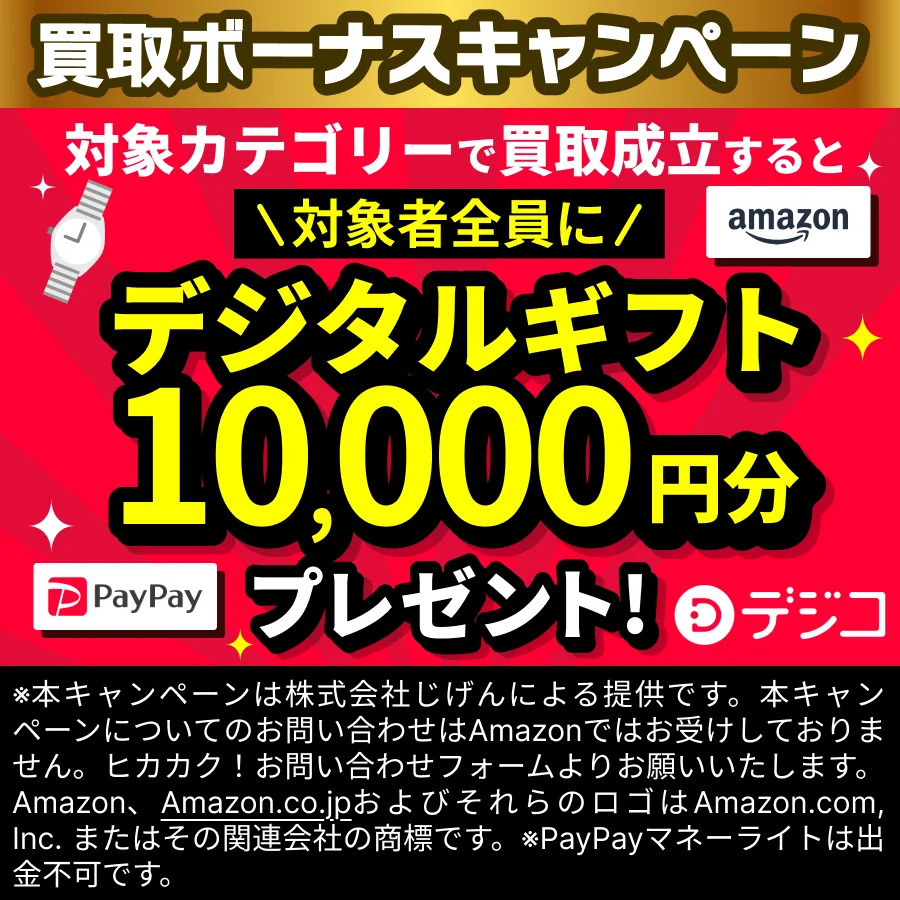ネットショップも含めた中古品を扱う事業者にとって欠かせないのが古物市場だ。中古品を安く入手する手段としてはもちろん、抱えている在庫の中古品を処分する場としても役立つだけに利益アップと経営の安定化両方にとって大きな意味を持つ。
古物営業許可証の資格を持っている者だけが参加できるシステムなのだが、ジャンルや地域によってそれぞれ古物市場があるため、事前に情報収集を行ったうえで自分のビジネスに役立つところを探し出して賢く利用できる環境づくりが欠かせない。

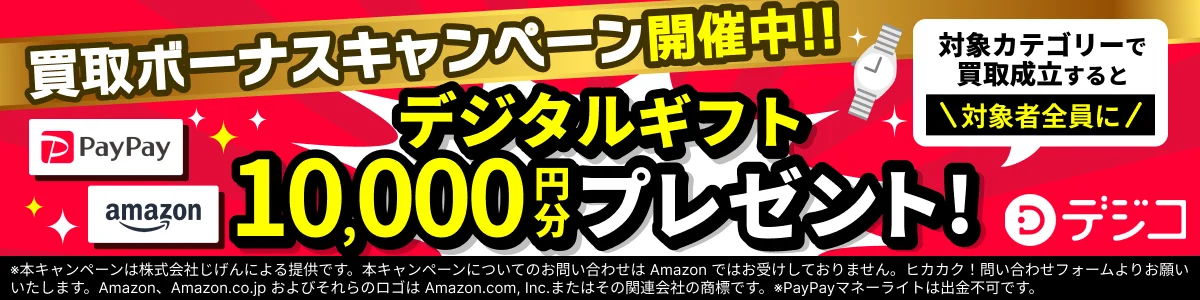
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物市場とは?
古物市場とは古物商同士が集まって扱っている在庫品を売買する場だ。そのため古物商としての資格を持っていることが参加の大前提となる。しかしそれだけではなく、その市場を主催している主催者の承認を受けないと参加できない。
基本的には事前に参加条件を設定し、それをクリアした古物商のみが参加できる形をとっている。そのため古物市場の情報を集める場合にはこうした条件についても確認しておきたい。
この古物市場に参加する条件としてはまず業歴が挙げられる。古物市場では古物商同士の信用が大きくモノを言う。売りにだされている古物が盗品など怪しいルートから入手されたものではないこと、ニセモノやキズモノなどの問題をごまかしていないことなどが大前提となるのは言うまでもない。
貴金属などこうした問題をその場で確認しやすいものもあれば、美術品・骨董品など専門家でさえ判断を誤ってしまうものもある。
それだけにその分野できちんとした業歴があり、これまでトラブルを起こしていないかどうかが問われることが多いのだ。同じ理由で過去に参加したことがある古物商の推薦・紹介を受けないと参加できない古物市場などもある。
インターネットで古物市場の情報を入手する
このように開業したばかりや参加したことがない古物商にとっては少々ハードルが高い面もある古物市場だが、うまく参加して活用できれば価値のある中古品を市場価値よりもかなり安く購入することもできるし、希少価値のある商品を入手できるチャンスも広がる。
古物商の中にはもっぱら利用客からの買取で在庫確保しているケースも見られるが、古物市場を利用することで扱う商品の幅が大幅に広がるのは間違いないだろう。
また、在庫がだぶついてしまった場合、古物市場で売りに出すことで調節することもできる。価値があってもなかなか買い手がつかない商品だと維持費も無視できないだけにこれも古物市場の見逃せないメリットだ。
情報収集
開業したばかり、古物市場に参加したことがない場合にはまずどんな古物市場があるのかを調べる必要がある。古物商同士が集まり、一定の参加資格を満たしていないと参加できない世界ゆえ狭く閉鎖的な面もあるため、ネットで検索すればすぐに見つかるというわけにはいかないのだ。
開業するまで古物市場の存在そのものを知らなかったという方も多いだろう。まずは情報収集の方法から確認しておきたい。
インターネットで情報収集する
もっとも簡単なのはインターネットで確認する方法だ。といっても先述のように検索エンジンで検索すれば見つかるといったものではない。古物市場を開催するためには主催者は開催する地の都道府県公安委員会の許可を得る必要がある。逆に言えば各都道府県ではどんな古物市場が地域内で開催されているのか把握しているのだ。
そして都道府県の中には古物市場のリストをホームページ上で公開しているところもある。具体的には神奈川県、群馬県、山梨県、静岡県、長野県、和歌山県、宮崎県、長崎県、香川県、高知県だ。これらの県内で開催されている古物市場を調べようと思ったらネットで確認することができるわけだ。もっとも手軽にリストを入手できる選択肢だろう。
当サイトでは「古物市場カレンダー」という無料のページを公開しており、日本全国の古物市場の予定を調べることが出来るようになっているので、お気に入り・ブックマークに登録を是非してみて欲しい。
開示請求をして古物市場の情報を入手する
残りの都道府県では開催されている古物市場の情報・リストをネットで調べるだけでは入手できない。その場合、警察の情報公開制度を利用すれば入手が可能だ。
つまり調べたい都道府県の警察に「古物市場のリストを公開してくれ」と請求する形になる。警察に請求するとなると不安を感じてしまう方も多いかもしれないが、情報公開は国民の権利でもあるわけだから、堂々と利用したい。
情報公開の請求
こうした官公庁の手続きは面倒なイメージがつきまとうが、古物市場の情報公開の請求はそれほど面倒ではない。まず調べたい都道府県の警察のホームページで情報公開制度に関する情報を確認しておこう。基本的には所定の用紙に必要事項を記入したうえで警察署に提出する形になる。
形式上では古物市場の情報は各都道府県の警察本部長(警視総監)が持っているため、警察本部長に請求する形となる。請求に必要な用紙に関しては各都道府県の警察署に出向けば入手できるほか、ホームページ上からダウンロードできるところもある。
それを印刷したうえで必要事項を記入・提出するわけだ。この点は各都道府県で対応が異なるのであらかじめ確認しておきたい。たとえば東京では警視庁のホームページから用紙をダウンロードし、必要事項を入力したうえで郵送すればOKだ。
情報公開請求の方法
必要事項に関してはとくに難しい部分はなく、自分の氏名・電話番号、公開して欲しい情報(この場合は古物市場主名簿)、そして請求する理由などが必要になる。請求理由に関しては必ずしも詳細な内容を書く必要はなく、調査や古物商としての情報収集などでもOKだ。
初めてなので不安という場合にはホームページ上で記入例を掲載している都道府県もあるのでそれを参考にして記入する、それがない場合には直接出向くかコールセンターに問い合わせれば説明を受けながら記入していくことができるので利用しよう。よほど初歩的なミスさえしなければ問題なく請求できるはずだ。
情報公開請求をした後
その後請求が受け入れられるかどうかの連絡が警察から来る。請求が通った場合には直接出向いてコピーをとって入手することになる。
東京や神奈川など多くの古物市場が存在するところならリストが数枚にわたることもあるが、いずれにしろそれほど多額の費用はかからないだろう。なお郵送でリストを送ってもらう方法もあるが、その場合はプラス郵送料金もかかる。
基本的には自分が営業している都道府県で開示請求を行うことになるが、より広範囲でビジネス展開をしたい場合や古物市場の数が少ない都道府県の場合は参加できる範囲内で近隣の都道府県のリストも入手しておくとよいだろう。その場合はリストの入手は郵送になるので方法を確認しておくことも大事だ。
業者からリストを入手する方法
情報開示請求でリストを入手するのが一番確実な方法だが、もうひとつ選択肢もある。古物市場のリストを販売している業者から買い取る方法だ。
こうした販売されているリストでは全国の古物市場を対象にしているものもあるので全国単位で古物市場をチェックしたい場合には向いているかもしれない。ただ情報開示請求に比べると当然費用がかかるので注意したい。
すでに他の古物商との付き合いがある場合には教えてもらうという方法もあるだろう。この方法のメリットはお金がかからないことと、自分が必要としている古物市場の情報だけを入手しやすい点だ。
付き合いのある古物商は自分と同じジャンルを扱っていることが多いわけだから、当然参加する古物市場も似通ったものになる。
先述のように東京や神奈川などでは古物市場の数が非常に多く、その中から自分が利用するとメリットが得られるところを選び出すのにも時間と手間がかかってしまう面もある。他の古物商から参加したことがある古物市場の雰囲気や傾向などのアドバイスを受けるチャンスがあるのも大きな魅力だ。
情報の見極めも重要
全国には1500もの古物市場があるといわれている。そこでは古物商が一般人が知らないところで中古品を売買し、ビジネスに役立てているのだ。
市場価格に比べてかなり安い価格で取引されるだけでなく、プロの古物商が売りに出しているだけあって質の高い商品を揃えやすい。こうした古物商のメリットを最大限に活かせるようになることで経営の環境を大きく改善することもできるはずだ。
初心者にオススメな古物市場
古物市場の情報やリストを入手するだけでは十分ではない。情報をいかに上手く活用できるか、そして厳選できるかも重要なポイントだ。それぞれの古物市場は参加条件だけでなく、雰囲気や傾向などにも違いが見られる。
たとえば古物市場には値の付け方などによって「平場」や「大会」「本ヤリ」といった種類に分類されることもある。
「平場」はまだ経験が浅い古物商でも比較的落札しやすい面がある一方、「大会」「本ヤリ」ではある程度の鑑定眼・相場感がないとなかなか落札できない面がある。古物商としての経験によって向いている古物市場とそうでない古物市場が出でくるわけだ。
古物商を始める際は
情報開示請求で入手したリストには主催者(営業者)や営業所の所在地、名称のほか連絡先の電話番号や扱っている古物の種類などの情報が掲載されている。まずは自分とかかわりのある古物を扱っている古物市場をピックアップし、主催者の連絡先に参加条件などを問い合わせることになるだろう。
付き合いのある古物商がいる場合には雰囲気などの情報も入手したうえで参加したいところだが、そうしたツテがない場合には実際に参加してみないとわからない部分もある。
そこが難しい部分でもあるわけだが、一度参加してみて雰囲気や扱っている商品をチェックすれば自分に向いているかどうか確認することもできるだろうし、よい商品をうまく落札するためにどういったコツが必要なのかも学んでいくことができる。
そして何よりベテランの古物商の値段の付け方、鑑定する様子を実際に目にすることで自らの眼も鍛えていくことができるだろう。
まとめ
古物商はどうしても閉鎖的な環境でビジネスを行う傾向が強い、とくにネットショップにそれが強いため、古物市場への参加はビジネスの幅を広げるだけでなく自らの視野も広げ、交流の機会を作っていく意味でも大きな意味を持っている。
リストの入手そのものは難しくないだけに、よい情報を見極めることができるか、入手したリストの中から自分に向いた古物市場を見つけ出すことができるかといった工夫も意識しておきたい。