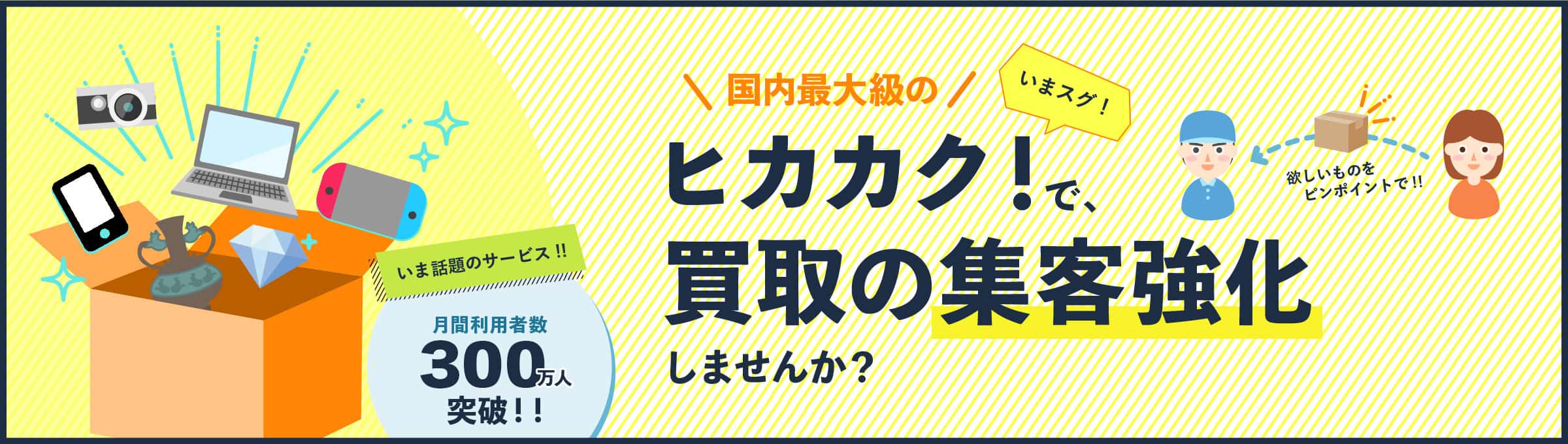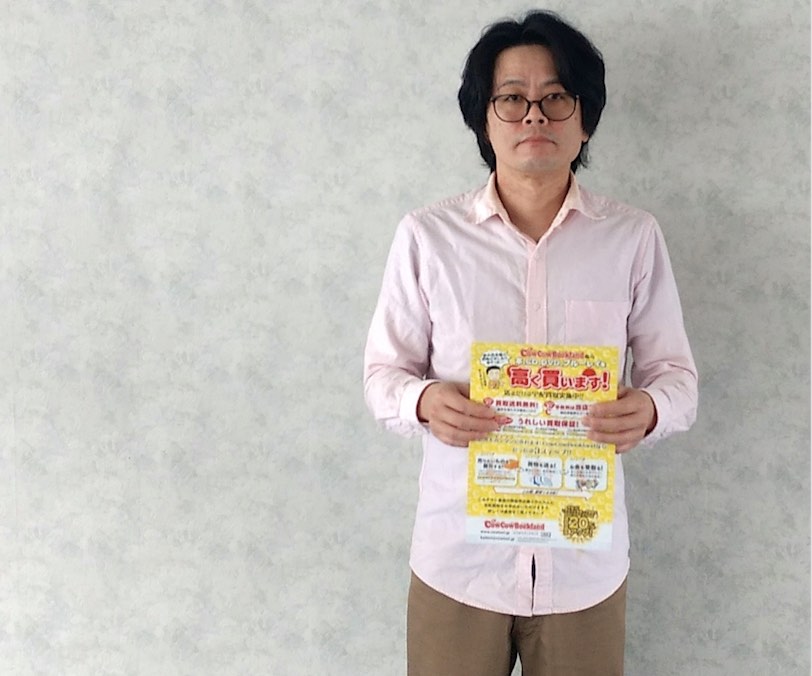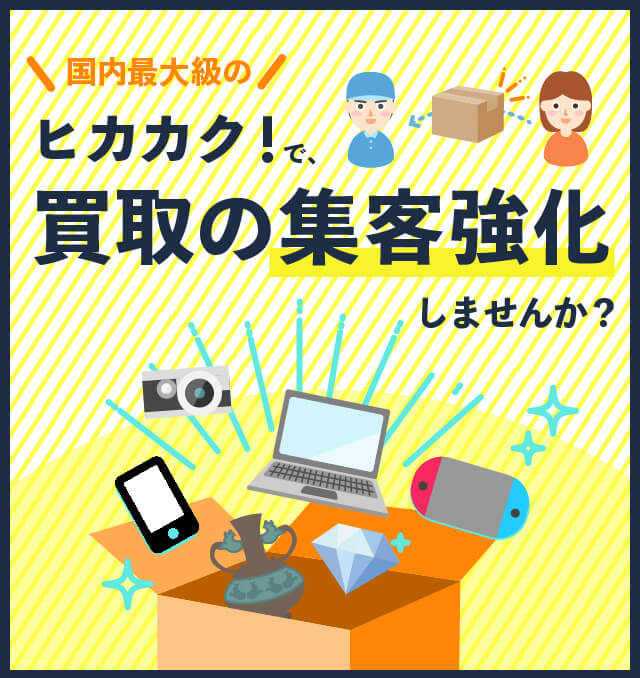最近では、インターネットで簡単に物の売買ができるようになり、たくさんの人が古物業界に参入している。リサイクルショップだけでなく、インターネットのオークションサイトで転売・古物営業をする場合にも、古物商の許可が必要だ。そして、許可を取得した後も申請した内容に変更があれば、変更届を出さなければいけない。
しかし、その変更届の申請の期限が過ぎてしまったら、一体どうなるのだろうか。今回は、変更許可申請が遅れてしまった場合の遅延理由書の書き方や内容、注意点などをわかりやすく解説する。

本記事のポイント
- 変更届の期限を過ぎた場合には遅延理由書が必要
- フォーマットがないが、何を書けば良い?
- 変更届を提出しない場合に罰則があるため注意が必要

CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
遅延理由書とは何か?書くべき理由とは
まずは遅延理由書の内容や書くべき理由、どのようなときに必要になるのかを確認しておこう。
遅延理由書とは?
遅延理由書とは、古物を取り扱う事業に関し一定の変更が生じた場合で、期間内に変更届を提出できなかったときに、変更届に添えて提出するものである。前提として古物商をおこなう際は、登録内容に変更があった場合には管轄警察署に届出をする必要がある。具体的には、営業所の住所が変わった場合などが挙げられる。
変更届の期限は当該内容の変更があった日から2週間以内となっている。登記事項に変更がある場合は、20日間に変更期限が伸びることも覚えておこう。
しかし、2週間というのは意外とすぐに過ぎ去るため、うっかり変更届の期限が切れてしまったというケースが出てくる。このような人は意外にも多く、焦って期限切れのまま変更届を提出しようとする人もいる。
しかし警察署では期限切れの場合は遅延理由書を添えるように促される。以上から、遅延理由書にはその名の通りなぜ変更届の提出が遅れてしまったのかを書く必要がある。
変更届が必要な事情
遅延理由書は、変更届を出す必要がない場合はそもそも必要のないものだ。では、変更届を出す必要がある事情にはどのような内容があるのだろうか。
古物営業の変更に関することについては、古物営業法というものに規定がある。古物営業法第5条では、「変更…があったときは、公安委員会に国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない」と規定されており、国家公安委員会規則では、以下の内容が定められている。
- ・氏名や名称、住所。法人の場合には代表者の名前の変更
- ・主たる営業所・古物市場、その他の営業所・古物市場の名称や所在地が変わった場合
- ・取り扱おうとする品目の変更
- ・営業所の管理者の氏名、管理者の住所変更
- ・行商について変更
- ・サイトのURLの変更
- ・法人の場合には役員の変更、役員の住所の変更
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。……
引用:(古物営業法第5条)
事業内容などに上記のような変更が生じた場合は、管轄の警察署に届け出を提出しなければならない。営業所が変わった場合のみならず、サイトやホームページのURLを変更した場合でも同様である。取り扱っている商品の他に別の品目を追加する場合も変更届を提出する必要がある。

変更届には手数料はかからない。また、個人事業から法人へ変更する場合には、一から許可を得る必要があるため、変更届は必要ない。変更届ではなく、許可手続きをおこなうようにしよう。
このように、変更届を出す事情は多岐に渡る。これくらい大丈夫だろうと放置していたら、大変なことになるため頭に入れておこう。
遅延理由書を提出しなかったら?
最後に遅延理由書を提出しなかった場合にどうなるのかについてご説明する。変更届自体が面倒で完全に忘れていた、知らなかったというケースもあるだろう。仮にずっと放置していた場合には面倒なことになる。というのも変更届と遅延理由書を提出しない場合には、以下のような不利益が発生するからだ。
罰金が科される
古物営業法35条では、変更届を提出しなかった場合の罰則について定めている。同条では10万円以下の罰金が規定されているため、もし変更届自体を忘れてしまっていた場合には、罰金が科される可能性がある。
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
引用:(古物営業法第7条)
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
引用:(古物営業法第35条)
「知らなかった」だけで10万円の出費は辛いものがある。変更届、そして遅延している場合には遅延理由証明書の両方を添えて、できるだけ早めに提出しよう。
古物商の営業許可が取り消される
遅延理由書を含めた変更届を提出しない場合、最悪の場合は営業できなくなってしまう可能性もある。同法は簡易取消制度というものを2018年から導入しているため、古物商の営業所の場所が確認できない場合には官報で広告後、30日で許可を取り消すことができる。
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
引用:(古物営業法第6条2項)
同年の法改正がおこなわれるまでは、3ヶ月以上の所在不明であったことなどが条件とされていたが、1ヶ月で許可を取り消すことができるようになった。盗難品流通防止のため、実体がない古物商はすぐに営業許可を取り消されてしまう。住所を変更したようなケースでは、特に注意すべきだろう。
以上から、面倒だという理由で変更届や遅延理由書を放置すべきではないことがわかっていただけただろう。余計な不利益が発生しないようにするためにも、うっかりミスを防ぐように心がけよう。
遅延理由書をなぜ書く必要があるのか
変更届の期限が過ぎてしまった場合に遅延理由書が必要なのは理解できる。しかし、何のために遅延理由書を書くのだろうか。
遅延理由書を必要とするのは、届出義務のある者に対し確実に義務を履行してもらうためである。変更は一度で済むとは限らず、今後事業内容や取扱い分野に変更があれば、再度、変更届を提出しなければいけない。
しかし、その度に期限を守らない人がいれば、警察は手続きを円滑に進められず、管理が難しくなる。このような事態を防ぐために、届出の遅延があった場合には、遅延理由書を書かせるようにしているということだ。

変更届が期限内に提出できない場合は、原則として変更届の提出は認められない。この場合事業に支障が出る可能性がある。そのため、温情措置として例外的に、遅延理由書を書けば変更届を受け付けていると言える。
遅延理由書があるということは、実際に遅延してしまう古物商が多いということだ。だからといって遅延しても理由を言えば大丈夫だと安易に考えるべきではなく、次回からはきちんと期限を守るようにしよう。2度目の変更届の遅延は受け入れてもらえない可能性もある。
このように、遅延理由書を書けば例外的に変更届を受理してもらえる。しかし、遅延理由書の趣旨を考えると、次回からは気をつけるようにするべきだろう。
遅延理由書の書き方
次に、遅延理由書の書き方をご紹介する。必要な書式や記載すべき事項、内容までしっかり確認しておこう。
遅延理由書に決まった形式は存在しない
遅延理由書をいざ書こうと思っても申請書みたいなものに書くのか、決まった形式があるのかなどと不安にある方も多いだろう。実際に遅延理由書に決まった書式や形式などはあるのだろうか。
結論から言って、遅延理由書に決まった形式は存在しない。遅延理由書は、先にお伝えしたように今後しっかり規則を守ってもらうためのものだ。いわば「もう遅延しません」という宣誓書のようなもののため、各自自分なりの形式で書いてもらって構わない。
しかし何に書いても良いからといって、ノートの切れ端に書くのは望ましくないだろう。例外的な措置を認めてもらわなければいけないため、真摯に反省しているようにみえる体裁を整えるべきだ。
だからといって特にかしこまる必要はなく、白い紙に遅延理由を書けば良いだろう。手書きでなければいけないのかという疑問もあるかもしれないが、特に指定はないので丁寧に描かれていればタイプした文書でも特に問題はないだろう。
このように、遅延理由書の形式に特に指定はない。それぞれが自分なりの遅れた内容を書けば特に問題はないということだ。
遅延理由書に書くべき内容
書くべき内容については、必要最低限の記載事項が定まっており、これがないと遅延理由書も受理してもらえないため、先に確認しておこう。遅延理由書の記載として必要なものは以下の通りだ。以下の順番に記載していけば問題ないだろう。
作成年月日
まず、文書の右上部に作成年月日を記載する。通常のビジネス文書と同様に考えればわかりやすいだろう。
誰宛か
次に、左側上部に◯◯公安委員会様と管轄の公安委員会名を書く。お住まいの都道府県名になるのが一般的だろう。わからない場合は、警察署で確認してほしい。
タイトル
宛先を書いたら、遅延理由書と中央上部にタイトルを書く。これがないと何のための文書かわからないため、タイトルは書くようにしよう。
遅延理由
タイトルの下に、遅延したことに対するお詫びと遅延した理由を簡潔に書こう。長々と書く必要はないのため、端的に遅延した理由があれば大丈夫だ。
申請者の住所・氏名・押印
最後に、用紙の下部にあなたの住所と氏名を書いて押印しよう。法人の場合は法人名と代表者の役職、名前を書いて押印する。
以上が、遅延理由書の内容として記載すべき事項だ。遅延理由以外は、一般的なビジネス文書と同じであるため、難しく考える必要はない。
遅延理由書の本文の例文
形式と記載事項がわかったところで安心と言いたいが、実際は遅延理由の内容や本文の書き方に困り果てる方が多いのではないだろうか。そこで実際に書くべき内容についてアドバイスをしておきたい。
遅延してしまったことを反省していると受け取ってもらうために、遅延理由書の本文は必ずお詫びから始めよう。そして、その後に理由を述べれば問題ない。実際のところ、たいした事情ではない、忘れていただけということも多いだろう。その場合は、変更の際に必要なその他の手続きで多忙であった旨を書けば良い。
知らなかったという場合でも、「失念していた」「必要な手続きにしっかりと目を通していなかった」など正直に書けば問題ない。具体的には、例文を用意したので以下を参考にしてほしい。
本文の例文
この度古物商変更届について、定められた期限である令和元年◯月◯日までに提出すべきであったところ、提出できませんでした。理由としては、事業所の変更に伴いさまざまな手続きが必要であり多忙であったためです。今後はしっかりと提出期限を確認し、遅れないように努める所存です。今後このようなことがないよう気をつけますので、変更届の受理を認めていただけますと幸いです。
内容としては上記の通りで問題ない。それぞれ遅れた事情は異なると思うので、例文をそのままコピーペーストするのではなく、自分の言葉で表現するようにしてほしい。
以上が、遅延理由書の書き方だ。書式がないというと不安に思うかもしれないが実際はそんなに難しいものではない。最低限の必要事項を記入して反省の弁と遅延理由を述べれば大丈夫なため過度に心配する必要はないだろう。

遅延理由書の作成に関する注意点
最後に、遅延理由書を作成する際の注意点についてお伝えする。以下の3点に気をつけるようにしよう。
できるだけ早く提出する
先にお伝えした通り、変更届は2週間以内に提出するのが原則だ。数日遅れる程度なら、遅延理由書を提出すれば特に問題とならないが、大幅に遅れている場合には、問題があると考えられてしまうだろう。そのため、気付いた時点でできる限り早めに提出することを心がけよう。
法人は特に要注意
また、個人営業ではなく、法人の場合はもっと注意が必要だ。役員などの変更があった場合には、登記を変更した上で古物商許可の変更届をしなければいけない。
この場合事務手続きが増えるため、遅延理由書を提出するまでに時間的ロスが大きい。登記の関係でさらに遅延してしまう場合は、その旨も遅延理由書に記載しよう。
遅延理由書は何度も受理されない
遅延理由書は何度も受理してもらえる類のものではないということを念押ししておきたい。変更する度に遅れていては、そのうち受理してもらえないどころか罰則の対象になってしまう可能性もある。
古物商許可が取り消されてしまうかもしれないため、遅延理由書が通るのは1度だけと考えておこう。このように遅延理由書を提出する場合は、できる限り早い段階でおこなうべきだ。気付いたらすぐに行動を起こそう。

まとめ
古物商許可の変更届はできる限り、期限内に提出したいところだ。本文でも指摘したが、変更のたびに何度も遅延していると、受理してもらえなくなったり、許可を取り消されてしまったりする可能性もある。事業に影響が出ないよう、スムーズに手続きを済ませておこう。
また遅延理由書は難しいものではなく、遅延の理由さえしっかりと記入すれば変更届とともに受理してもらえるはずだ。今回のことを、教訓に次回は提出しないで済むようにしよう。