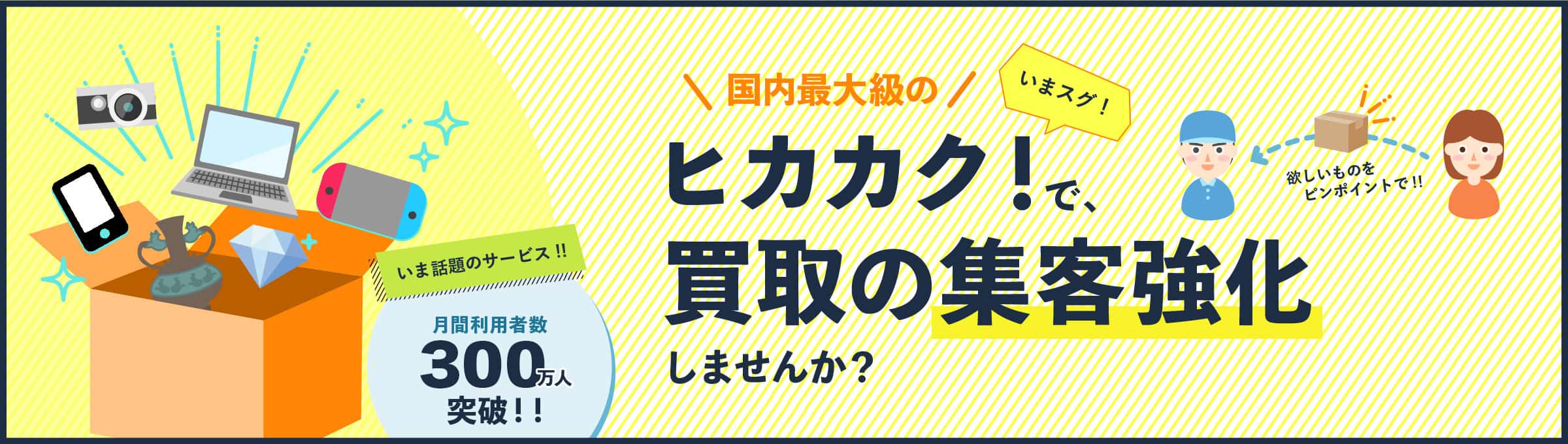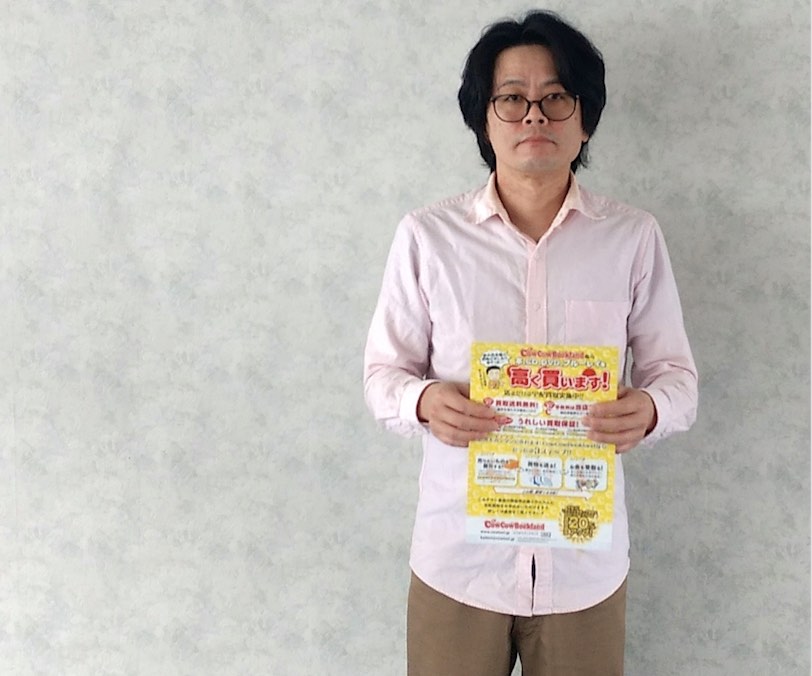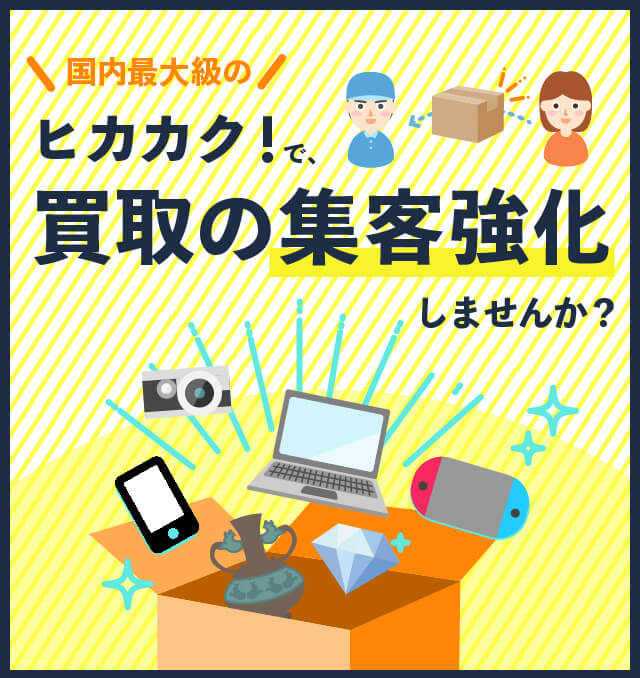古物商の許可を申請するうえで、管理者の選定は非常に重要だといえるだろう。なぜなら営業所には、かならず管理者を1人設置しなくてはならないからだ。また、取り扱う品目に関する対する専門的な知識や法令に対する知見も必要となるため、その責任は非常に重い。
そこで今回は、古物商の管理者になれるのは誰か、また講習参加は必須なのかどうかについて解説していく。古物商になりたいと考えている方はこの記事を参考に、適切な管理者選びをしよう。

本記事のポイント
- 管理者は誰でもなれるものではない
- 品目により非常に知識が求められるが、その知識はどこで身につける?
- 複数で営業をする場合は特に管理者選びに注意が必要

CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物商の管理者の役割
まずはじめに古物商の管理者の役割について解説していく。盗品などの売買の防止、および不正行為の発見を目的とする古物営業法では次のように定められている。
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
堅苦しい言葉なので少々わかりづらいかもしれないが、要するにこれは、古物を扱う営業所では、盗品などの売買や不正行為を未然に防ぐために、専門的な知識をもった責任者を設置し、従業員への指導にあたれ、といっているのである。
これが古物商の管理者に与えられた役割である。当然、古物商の管理者は、従業員を指導できる地位についていなくてはならず、また法令に対する正しい知識をもっていなくてはならない。

古物商が受けるべき講習とは
では、古物商の管理者が受けるべき講習とは何なのだろうか。結論からいうと、古物商の管理者が受けなくてはならない講習というものは存在しない。しかし先ほども述べたとおり、古物商の管理者は盗難品や不正品を見抜くための専門的な知識をもっている必要がある。
たとえば、車を扱う古物商の管理者については、古物営業法施行規則14条において、次のように定められている。
第十四条 法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
つまり、古物商の管理者が受けるべき講習とは、古物商の管理者になるための講習ではなく、取り扱う品目の専門的知識を養うための講習なのだ。
もちろん、各都道府県の警察署では、古物商等新規許可業者法令講習会や古物営業許可関係の法令講習会、警察署別法令講習会などがおこなわれている。しかし、古物商の管理者はこれらの講習に参加する義務はない。それどころか、これらの講習を受けずとも、古物商の管理者にはなれるのである。

古物商の許可が必要となる品目
古物営業法施行規則第2条では、以下の13種類の品目が古物として指定・分類されている。しかし、この区分はあくまでも古物商の許可が必要かどうかに関わるものである。

美術品類
古物商の許可が必要となる品目1つ目が、美術品類である。これは主に、書画や彫刻、絵画、工芸品などが該当する。これらの品目は専門的な知識が求められるが、時代を問わず常に一定の需要があるのがメリットだ。
衣類
古物商の許可が必要となる品目2つ目が、衣類である。これは主に和服類や洋服類、その他の衣料品などが該当する。このジャンルは競争が激しいが、同時に高い利益率をもっており、また自分のセンスや個性などを発揮してセルフブランディングしやすいといえるだろう。
時計・宝飾品類
古物商の許可が必要となる品目3つ目が、時計・宝飾品類である。これは主に眼鏡や時計、宝石類、装身具類、貴金属類などが該当する。これらの品目はいずれも単価が高く、利益率も高くなりやすい傾向にある。
自動車
古物商の許可が必要となる品目4つ目が、自動車である。これは自動車本体以外にもタイヤやバンパー、カーナビ、サイドミラーといった部品も含まれている。
実は自動車は、この13品目のなかでもっとも取得が難しいといわれている。理由は簡単で、取引金額が大きく、なおかつ盗難車や改造車といった不正品が流通しやすいジャンルだからだ。そのため、自動車商になる場合は、それ相応の経験や勉強量が求められる。

自動二輪車および原動機付自転車
古物商の許可が必要となる品目5つ目が、自動二輪車および原動機付自転車である。これはバイク本体以外にもタイヤやマフラー、エンジンといった部品も含まれている。こちらも自動車と同じく不正品が流通しやすいため、取得するのが難しいといわれている。
自転車類
古物商の許可が必要となる品目6つ目が自転車類である。これは自転車本体以外にも空気入れやかご、カバーなど、自転車の部品や周辺用品が含まれている。こちらも自動車やバイクと同じく、不正品が流通しやすいので取得難易度が高い。
写真機類
古物商の許可が必要となる品目7つ目が、写真機類である。これは、写真機本体の他に、レンズや望遠鏡、双眼鏡、光学機器など、レンズや反射板を利用した機器などが該当している。これらの品目は、メーカーと商品さえ知っていれば扱えるため、初心者にはおすすめだといえるだろう。
OA機器類
古物商の許可が必要となる品目8つ目が、OA機器類である。これは主に、ビジネスフォンやレジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機などが該当している。
近年、これらの品目を取り扱うリース会社などが、サービスを終了して中古販売市場に流すケースが増えている。そのため、OA機器類は在庫が豊富で、参入した際は高い売り上げが見込める。
機械工具類
古物商の許可が必要となる品目9つ目が、機械工具類である。これは主に、電機類や工作機械、土木機械、化学機械、工具などが該当している。さらにこちらはテレビや冷蔵庫などの家庭用電化製品も含まれるため、非常に幅広い知識が必要になる。
道具類
古物商の許可が必要となる品目10つ目が、道具類である。これは主に家具や運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、CD、DVDなどが該当している。道具類は取り扱うジャンルが幅広く、セットで取り扱いたい物品がほかの品目に分類されていることが多い。
皮革・ゴム製品類
古物商の許可が必要となる品目11つ目が、皮革・ゴム製品類である。これは主に、鞄や靴などが該当している。こちらはエルメスやルイ・ヴィトンといったブランド品も取扱うため、鑑定士レベルの知識が必要だ。

書籍
古物商の許可が必要となる品目12つ目が、書籍である。これは主に文庫やコミック、雑誌、専門書などが該当している。こちらは比較的難易度が低いジャンルだが、古書などについては高い専門性が求められる。
金券類
古物商の許可が必要となる品目13つ目が、金券類である。これは主に商品券や乗車券、航空券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券などが該当している。こちらは薄利多売なジャンルであるため、商品回転率を高めるのが重要だ。
古物商の管理者になれるのは誰?
ここまでで、古物商の管理者になるためには、不正品の疑いがあるものを見極めるための講習をうけていること、従業員を指導できる地位についていること、法令に対する正しい知識をもっていることなどが必要だとわかった。では逆に、古物商になれない人とは誰なのだろうか。
古物商の管理者になれない人
古物商の管理者になれない人は、古物営業法第4条に定められている。まとめると以下のとおりだ。
- ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- ・禁固以上の刑、または特定の犯罪で罰金刑に処せられ5年経過していないもの
- ・暴力団員及びその関係者など
- ・住居の定まらないもの
- ・古物営業の許可を取り消されてから、あるいは返納してから5年経過していないもの
- ・心身の故障により、適正に業務を実施できないと判断されるもの
- ・未成年者(相続人であり法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除く)
- ・管理者を選任すると認められない相当な理由がある者
これら8つは、欠格事由や欠格要件などと呼ばれている。上から6つの欠格事由に該当する人や法人役員のなかに該当する人がいる場合、残念ながら古物商の管理者にはなれない。

2019年の法改正により、それ以前は欠格事由に該当していた成年被後見人・被保佐人も古物商許可をとったり、管理者になったりすることができるようになりました。
古物商自身も管理者になれる?
ここまでで、古物商の管理者になることの大変さがよくおわかりいただけたのではないだろうか。人によっては、他人に管理者を任せるよりも自分で管理者になってしまったほうが早いと感じる方もいるだろう。そこで疑問になるのが、古物商自身も管理者になれるのかどうかである。
実は、個人で古物商を立ちあげた人や古物商許可を個人で申請したいと考えている人も古物商の管理者にはなれる。これは法人であっても例外ではない。また、取締役1名で立ちあげた会社であっても、その代表者が管理者を兼務することは可能である。
古物商の管理者の交代などについて
仮に、古物商の管理者が決まったとして、転勤などの理由で管理者を交代しなくてはならない場合、変更届出を提出する必要性がある。提出先は、古物商許可申請手続きをした警察署だ。
変更届出の提出期限は原則14日以内である。期限が守れないと10万円以下の罰金が科される場合があるため注意してほしい。届出手数料自体はどの都道府県でも無料であるため、管理者の交代が決まった際は迅速に動くようにしよう。
古物商の管理者を選ぶ際の注意事項
最後に、古物商の管理者を選ぶ際の注意事項について解説していく。古物商の許可を申請するうえで重要なのは事前の準備だ。ここに記載されている知識を身につければ、とっさのときのトラブルも回避しやすくなるだろう。
管理者は1つの営業所につき1人
古物商の管理者は、各営業所ごとにかならず1名必要となるため、営業所が複数あればその数だけ管理者を選ぶ必要がある。ここで注意しなくてはならないのは、仮に1人でも証明資料に不備があると全営業所の許可申請手続きがストップしてしまうことだ。
また、責任者は1度許可申請すればそれでおしまいというわけでなく、管理者が交代した場合などは変更届出をだす必要がある。そのため、管理者を選ぶ際は入れ替わりの少ない役職者を責任者として選ぶか、全営業所の責任者を管理する仕組みを作っておくのが重要である。
管理者は営業所に常勤しなくてはならない
古物商の管理者は、営業所内の業務を適正に実施するために、営業所に常勤する必要性がある。通勤が困難な場所に住んでいる人を管理者に選任することはできない。
また通勤の目安は片道約1時間半程度とされており、これ以上の時間がかかってしまうと常勤しているかどうか疑われてしまう恐れがある。仮に遠方に住んでいる人を管理者に選びたい場合は、あらかじめ管轄の警察署に相談するのがおすすめだ。

管理者の兼任は認められない
古物商の管理者は、原則として兼任が認められていない。ただし、常勤が求められるための決まりであるため、同じ土地に建物が2つあったり、同じビル内に営業所が複数あったりする場合は、例外的に管理者の兼任が可能だ。こういったケースに該当する場合は、あらかじめ管轄の警察署に相談してみよう。

ネットオークションやフリマアプリでも許可は必要
ネットオークションやフリマアプリで商品を販売する際は、古物商の許可は必要ないという意見がまかり通っているが、これは誤りだ。古物営業法第2条では、以下のように定められている。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
引用:(古物営業法第2条)
つまり、最初から転売目的で購入した商品は立派な古物であり、それを販売する以上は古物商の許可が必要になる。転売自体は決して悪いことではないが、商売目的でこれらのサイトを使う場合は許可が必要になることを十分に理解してほしい。
まとめ
この記事では、古物商の管理者になれるのは誰か、また講習参加は必須なのかどうかについて解説した。古物商の管理者の責任はとても重いが、だからこそ誰を選任するかが重要となる。古物商になりたいと考えている方はこの記事を参考に、適切な管理者選びをしてほしい。