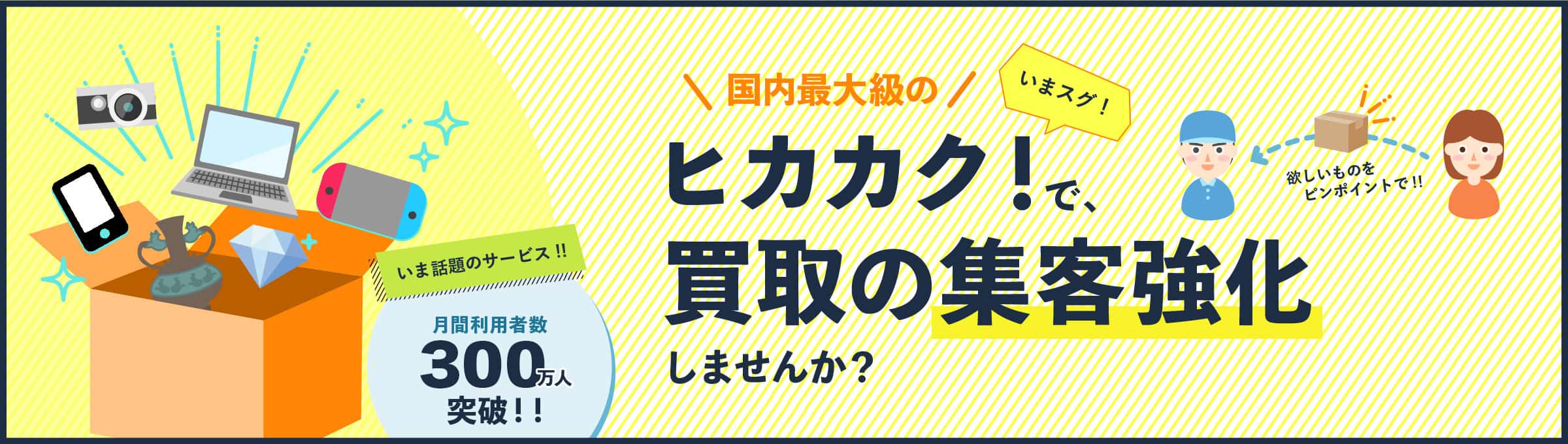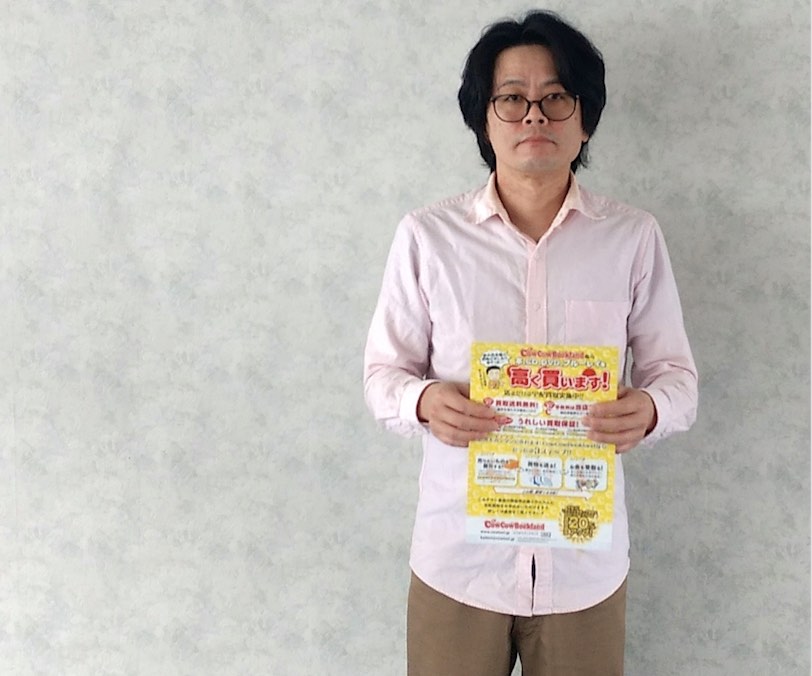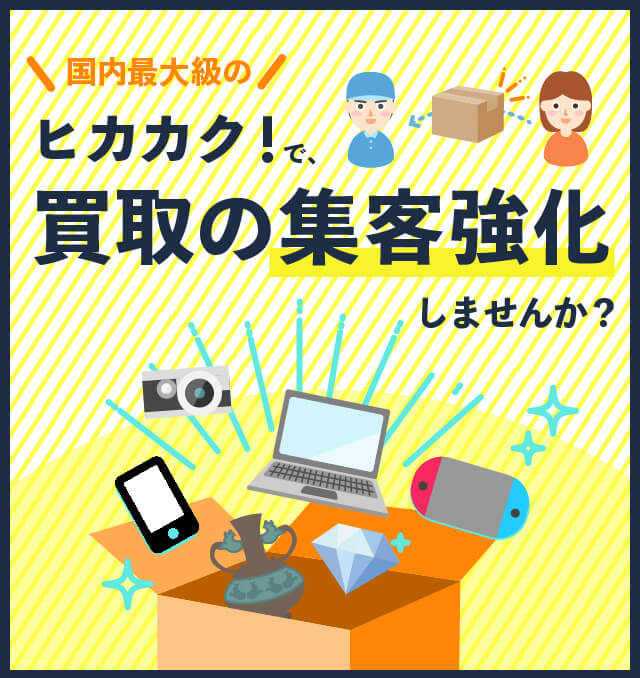『メルカリ』や『ラクマ』といったインターネットの普及で、古物業界に参入し、中古売買をおこなう人も増えてきている。古物商許可申請は、多くの資料を必要とする。許可の可否がわかるまでに40日ほどと日数を要することからも、早めに準備をしておく必要があるだろう。しかし、段取りさえ分かっていれば、資料の用意自体は難しくない。
今回は、古物許可申請に必要な資料を確認した上で、開業届と古物商許可申請のどちらを先にすべきか解説していきたい。

本記事のポイント
- 古物商許可や開業準備、開業届などやることは膨大
- 優先順位はどうやってつけていく?
- 青色申告など他にも重要な届出がある

CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
開業届を提出するにあたって必要な準備とは?
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる。これは、開業する人は絶対に提出しなければならない。まずは、開業届に必要な準備について解説する。
開業届を提出するにあたって必要な記入事項
開業届は、税務署に取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードすることで入手することができる。
必要となる記入事項は、納税地、氏名、生年月日、職業、屋号、マイナンバーなどの基本事項のほか、届出の区分、所得の種類、開業日、事業の概要である。所得の種類は不動産所得、山林所得、事業(農業)所得の中から選択する。また、事業の概要については、可能な限り詳細に書く必要がある。
また、青色申告者になる場合には、「青色申告承認申請書」が必要となる。開業時から従業員がいる場合にも、「青色事業専従者給料に関する届出書」を用意し、従業員数や給料などを記載する必要がある。「給料支払い事務所等の解説届出書」に関しても提出が必要だ。

さらに、従業員に給料から源泉徴収した所得税は、原則、その給料を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があるが、従業員が9名以下に場合に、特例として半年分納めることが可能である。この特例を受ける場合には、「源泉所得の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要がある。
他にも、場合によっては、「労働保険関係成立届」や「雇用保険適用事業所設置数届」などの届けが必要となる場合があり、これらは提出先が異なり、期限も違う。
このように、開業届の他に合わせて提出する必要がある書類は多いため、節税を考えていたり、従業員を雇うことを想定している場合には、自分が提出する必要のある書類はしっかり確認しておきたい。また、提出にあたっては、本人確認や押印もあるため、本人確認ができる書類や、印鑑を用意しておく必要がある。
提出期限は事業開始から1ヶ月以内
期限は、事業開始などの日から1ヶ月以内とされ、期限が土日の場合には繰り越され、翌日の最初の平日までと定められている。この届出は、納税地を所轄する管轄の税務署へ署長宛に提出することになっている。手続きに関して、手数料などはかからない。記入事項は多くないため、すぐに提出することができるだろう。

古物商許可申請にあたって必要な準備とは?
開業届と古物許可申請の優先順位をつけるのにあたっては、どういうプロセスが必要になるか確認しておくべきだろう。古物許可申請にあたって必要となる資料と書く内容、具体的な登録方法を解説する。
古物商許可申請に必要な資料一覧
許可申請をするにあたり、多くの資料が必要となる。警察署でもらう必要のある書類は、個人の場合に以下の3つだ。
- ・別記様式第1号その1〔ア〕
- ・別記様式第1号その2
- ・別記様式第1号その3
この他、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書を添付資料として用意する必要がある。
また、賃貸である場合に、営業所の賃貸借契約書のコピーや駐車場など保管場所の賃貸借契約書のコピーが必要になる場合が多い。また、使用承諾書が求められる。


インターネット上で売買をおこなう場合には、URLの登録が必要であり、その証明となる「URLの使用権原疎明資料」も別途用意しなければならない。本人名義ではない場合、こちらも使用承諾書が求められる。
さらに、法人の場合に、これに加えて、別記様式第1号その1〔イ〕の書類への記載が必要となり、法人の定款の添付資料も必要となる。個人か法人か、営業所が賃貸か、インターネットで売買するかによっても、用意する資料が異なるため注意したい。

各提出書類で具体的に書く内容
別記様式第1号その1(ア)は、許可の種類や個人情報の記載が大まかな内容だ。ここに「主として取り扱おうとする古物の区分」も記載する必要がある。この詳細については、次に述べたい。
次に、別記様式第1号その1(イ)だが、これは代表者の個人情報を記入する書類である。これは書類1枚につき3名までしか記入ができないため、人数に合わせて必要枚数をそろえる必要がある。
そして、別記様式第1号その2は、営業所や古物市場を記入する。これに関しても、複数営業所がある場合に、営業所の数だけ枚数が必要となる。
最後に、別記様式第1号その3は、「電気通信回路に接続しておこなう自動公衆送信により、公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうか」記載するものである。用いる場合には、送信源識別符号を活字体で記載しなければならない。
こう聞くと難しそうに聞こえるが、端的に言えば、先ほども触れたホームページなどを利用するか否かの事項を指している。「送信源識別符号」というのも、要はホームページのURLのことだ。これを理解していれば、手順は煩雑なものの、何一つ難しい書類はないはずだ。
各書類の記載例を徹底解説・参考サイトも掲載
別記様式第1号その1〜その3は、警視庁のサイトより入手が可能だ。
また、警視庁では、各資料の記入・記載例が掲載されている。これに関して、徹底的に解説していきたい。見ながら進めていけば、スムーズに資料作成ができるはずだ。
また警視庁のサイトでは、別記様式第1号その1〔イ〕を除いた記載例を見ることができる。別記様式第1号その1〔イ〕は〔ア〕の代表者欄と同じ内容なので、そこを見ながら記載すれば良いだろう。
別記様式第1号その1〔ア〕
ここでは、許可の種類(古物商もしくは古物市場主)と、氏名または名称、法人の種別、生年月日。住所または居所、行商をするものであるかどうか、主として取り扱おうとする古物、代表者の個人情報などを記載する。代表者の欄に関しては、個人の場合記載する必要がない。
別記様式第1号その1〔イ〕
イは、法人の場合に書く必要がある書類だ。ここでは代表者の種別、氏名、生年月日、住所を記載する。別記様式第1号その1〔ア〕と同じ内容なので、代表者が1名の法人の場合には記載する必要がない。
別記様式第1号その2
ここでは営業の形態と営業所(古物市場)の名称及び所在地、主として取り扱おうとする古物、管理者を記載する。
別記様式第1号その3
ここでは、インターネット上で古物売買をおこなう場合、そのURLのアルファベットや記号を一字ずつ所定の場所に記載する。
ブログカードがロードできませんでした。
登記されていないことの証明 ※法改正で不要に
「登記されていないことの証明」は業務能力の有無を確認するもので、法務局でしかもらうことができず、ここでも住民票などの添付が求められるため、1番最初に入手しておくとスマートにことが運ぶだろう。記入例も合わせて書いてあるので、確認しながら記載すると良いだろう。
証明書を取り寄せるにあたっては、戸籍謄本・抄本、住民票などの写しを添付する必要である。また、郵送で取り寄せる場合には返信用封筒(長形3号)に82円切手を貼ったものも用意する必要がある。料金は300円の収入印紙が必要だ。これは法務局でも販売されている。
略歴書・誓約書
「略歴書」は個人情報と職歴を記入する欄だ。警察署のサイトから入手することができ、普段書く履歴書とあまり変わりない。法人の場合に、全員分記載する必要があるため、注意が必要だ。
また、「誓約書」は人的欠落事由に該当しないことを制約する書面で、個人と法人で書類が異なる。同リンクから入手し、該当する方の誓約書に記載すれば良い。なお、申請者または申請法人役員以外が管理者となる場合には、別途管理者の誓約書も必要となる。

法人に必要な「定款」
古物商の許可を得るには、事業目的が古物商に関わるものでなくてはならない。それを確認するために、定款は必要となる。したがって、事業に古物商に関わるものの記載がなくてはならない。
また、古物商の許可は、販売をおこなうのみである場合に不要であることから、売り買いに関する記載も必要となる。スムーズに申請をおこなうには、扱う古物の品目についても記載しておくと良いだろう。
登録の方法と手数料
これらの書類を提出するには、営業所を管轄する都道府県の警察署に行く必要がある。そこで、具体的な場所を含め、各注意点を確認して行く。
場所と申請時間
許可を得るために書類を提出する場所は、営業所の所在市を管轄する警察署の防犯係のところである。最近は申請場所の間違いが多いようで、警視庁の方では管轄警察署を確認するよう注意喚起もなされている。2度手間にならないよう注意したいところだ。
また、管轄が警視庁のサイトで所在地から簡単に調べることができる。事前に調べてから警察署の防犯係へ行くことをお勧めする。
この申請は時間が決まっているため、その点も注意しておきたい。申請時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっている。書類の確認や業務内容の確認もおこなわれるため、時間には余裕を持つ必要があるだろう。また、申請が通らないと開業ができないため、提出も当然、開業より前におこなわなければならない。

手数料と注意点
手数料は19,000円かかるが、不許可になった場合も手数料は取られてしまう。その上、許可・不許可の通達に関しては当日中におこなわれない。この点は留意しておきたい。
具体的には、通達されるのが申請からおおむね40日となっているため、計算して開業までに余裕を持って提出しておく必要がある。また、古物市場主の場合には、おおむね50日となっている。

開業届より古物商許可申請を先にすべき
もし仮に開業に間に合わない場合も、例外なく古物営業を始めることが許されていない。また、開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出すれば良い。そのため、古物商許可申請は時間がかかることからも、開業届より先に申請の準備をすべきだろう。開業届は、確実に営業できる日がわかってから提出するのでも遅くはない。
かといって、開業届より先に古物商の許可を絶対に先に取らなければならないというわけではない。ただし、古物商許可申請手をつけたほうが、スムーズにことが運ぶと思われる。
また、個人の場合であっても、税制面において大きなメリットが受けられるため、高額の利益を生む予定があれば、開業届は出しておくべきである。

なお、時間がない場合に、人に申請を頼むことも可能である。しかし、本人以外の者が申請する場合には委任状が必要だ。法人申請の場合には、社員証など、社員であることを証明するものも持参する必要がある。その上、前述の通り、業務内容の確認がおこなわれるため、それに回答できる者が行く必要がある。
また、営業所に勤務できる範囲で、かつ古物取引に関して管理・監督・指導ができる管理者を選任する必要があるため、これもあらかじめ決めておく必要がある。

まとめ
開業届は、開業などをしてから1ヶ月以内に提出すれば良い一方で、古物商許可申請は、許可が下りていないと開業することができず、必然的に開業前の提出となる。
そのため、優先順位をつけるなら、まずは古物商許可申請の方から手をつけるべきであろう。古物商の許可の可否に関する通達がおおむね40日(もしくはおおむね50日)と時間がかかる上、開業に間に合わない場合でも許可が下りていないと業務をおこなえないため、可能であれば早めに行動した方が良い。

古物許可申請は書類の数は非常に多いが、サイトを見ながら手順通りに進めれば、難しいことはないはずだ。各書類の注意事項を確認し、着実に書類をそろえていきたい。
しかし、営業所を自宅に据えたり、代理人に手続きを頼んだりする場合、別途資料が必要になることが多い。そのため、複雑な申請になることが想定される場合には、あらかじめ必要となる資料を確認しておくとスムーズにことが運ぶと考えられる。許可が下りなかった場合のことも想定して、時間に余裕を持って資料を作成したいところだ。
ブログカードがロードできませんでした。