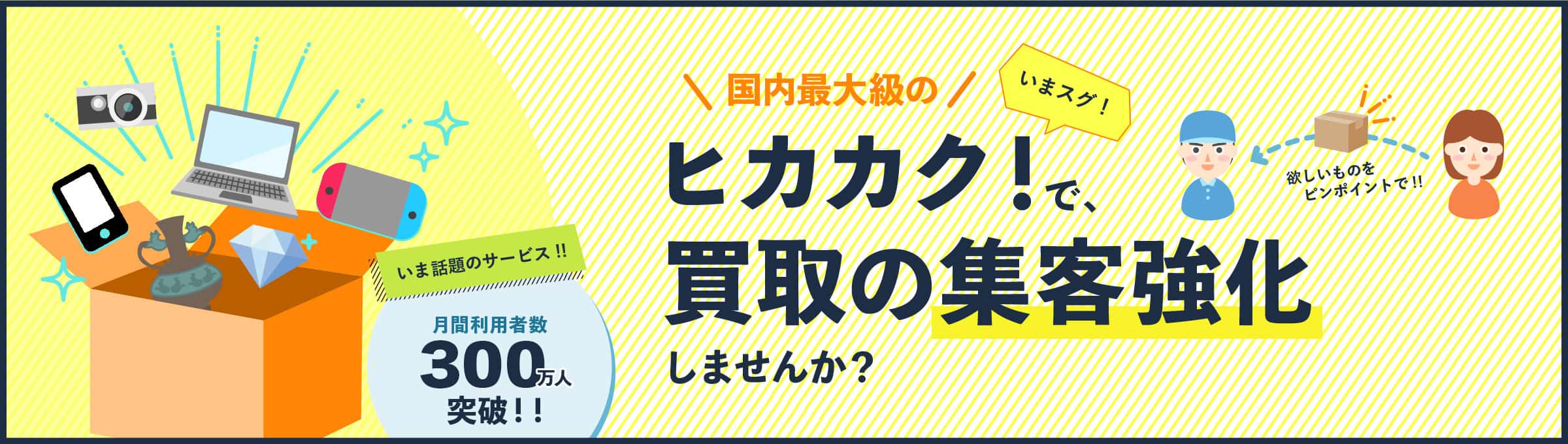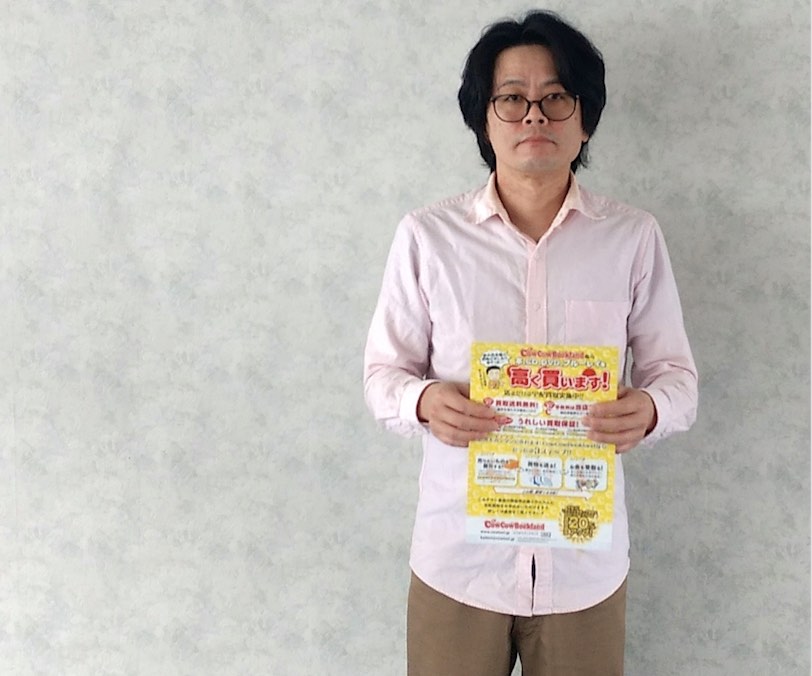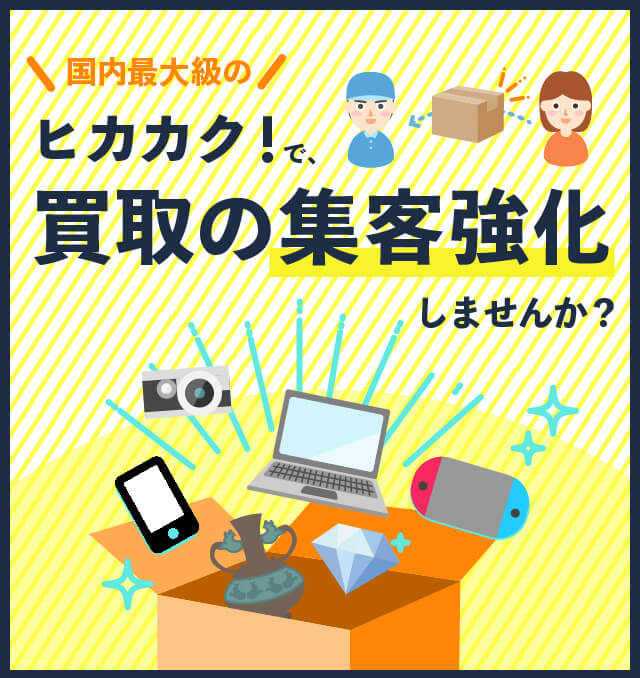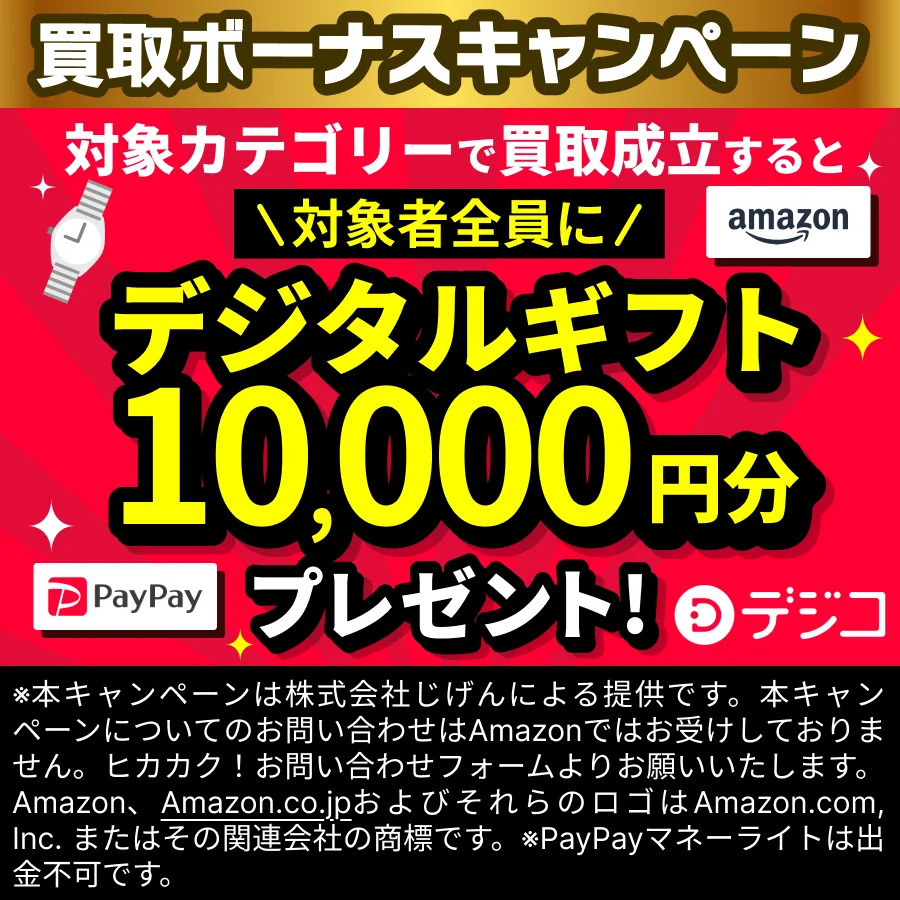最近はインターネットオークションなどのCtoCによって、転売をおこなう人が増えている。しかし、常に古物営業法違反として逮捕されるリスクがあることは考えておく必要がある。また、仮に古物許可を得ていても古物営業法やその他の方に抵触し、逮捕される古物商が存在する。
法をよく理解しないまま開業し、営業をおこなうのは危険であると考えて良いだろう。そこで古物営業法違反に該当する内容や罰則、古物商が気をつけなければならない法律を紹介した上で実際の逮捕事例や違法行為を取り締まるためのサービスについて確認していきたい。
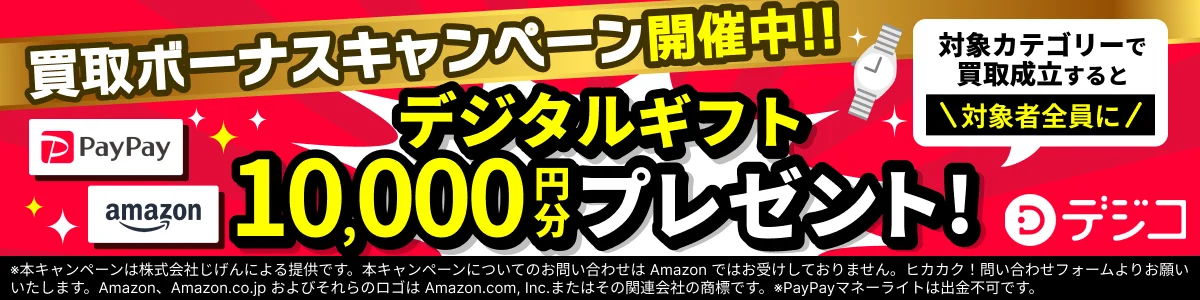
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物営業法違反による罰則
古物営業法違反により取り締まられるケースは往往にしてある。この古物営業法違反とはなんなのか。罰則について確認していきたい。
古物許可を得ていない場合に抵触する可能性が高いもの
フリマアプリやインターネットオークションで個人間取引をおこなっていた場合でも、古物営業法違反とみなされる。違反とみなされた例については後ほど確認していくが、まずは抵触する主な条文について確認したい。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役は100万円以下の罰金に処する。
- 1:第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者
- 2:偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
- 3:第9条の規定に違反した者
- 4:第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者
無許可で古物に関する営業をおこなった場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される。(古物営業法)
古物許可を得ている場合に抵触する可能性が高いもの
古物許可を得ている場合に関しては、主に古物営業法第32条~39条に該当すると古物営業法違反とみなされる。主だった内容としては以下のものである。
- ・営業所または買取相手の住所もしくは居住以外の場所で古物商以外から古物を受け取ってしまう(あらかじめ公安委員会に届け出た場合を除く)
- ・古物市場で古物商間以外で売買をおこなう
- ・帳簿に必要項目を明記しない
- ・品触れに応じず、6ヶ月の間書面を保存しない
- ・盗品と疑わしいものを30日間手元に保存しない、また、盗品と怪しいものに対し、あっせん業者は競りをおこなってしまう
- ・許可申請に対して規約に違反して添付書類を出さなかったり、虚偽を記載していたりする
- ・古物営業を廃止しているにも関わらず、公安委員会に返納していない
- ・競り売りで許可証を携帯していなかったり、行商で従業員に行商従業員証を携帯させていなかったりする
- ・警察の立ち入りや帳簿の検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりする
- ・品触れに該当するものを報告しなかったり、警察が求めた盗品報告に関して報告しなかったり、虚偽の報告をしたりする
- ・不正で古物許可を得る
古物商としての義務を怠ったり、不正をおこなうことで古物営業法違反とみなされると考えて良いだろう。
古物商が気をつけなければならない法
古物商は古物営業法以外にも数々の法を守る必要がある。例としては以下のものだ。
買取にあたって注意すべき法は種の保存法、銃砲刀剣類所持等取締法、ワシントン条約のほか、景品表示法、特定商取引に関する法律、不正競争防止法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律など。犯罪防止、早期発見に関わる法には犯罪収益移転防止法など。その他、取り扱う古物によって家電リサイクル法や電気用安全法、消費生活用製品安全法などが関わってくる。
法の一部を分かりやすく紹介
景品表示法や特定商取引に関する法律は、一般消費者の利益の保護を目的とした法律だ。そのため、過大な景品付販売や誇大広告、不正表示、適正価格でない価格での売買によって違法とみなされることがある。
そして、不正競争防止法は、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としているため、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示などの不正行為や不法行為などをおこなうことで違法とみなされることがある。
消費者契約法は、事業者との情報や交渉力の差があることを受け、消費者が対等に契約できることを目的としているため、買取において消費者に対して不当な契約をおこなった場合に違法とみなされることがある。
個人情報の保護に関する法律は、個人の権利利益を保護することを目的とした法律である。そのため、買取などによって得た個人情報の取り扱いを十分におこなわない場合に違法とみなされることがある。
古物許可申請を得ていないことによる逮捕事例
フリマアプリやインターネットオークションで普通に取引をしている場合に逮捕されることはほとんどない。しかし、場合によって古物営業法違反にみなされ、逮捕されることもある。そこで、古物許可申請を得ていないことで古物営業法違反とされ、実際に逮捕された事例を確認していきたい。
宝塚チケットをチケット販売店で購入し転売
2017年には、宝塚のチケット転売をおこなったことで56歳の男性と83歳の女性らが逮捕された。この親子は路上生活者と共謀し、転売目的で大量のチケットを購入していた。当時の調べによれば、問題になった2017年の2月~4月にわたって東京都渋谷区などのチケット販売店でチケット52枚を転売目的で購入。チケット売り場へは路上生活者を並ばせていたと言う。
同様の方法で、2009年~2017年の8年間にわたって2000万の利益を得ていたと考えられている。また、これによる最大価格は定価の17倍であったとされている。チケットの転売そのものは違反行為ではないものの、原則的には行くつもりで行けなくなったチケットを売ることのみが許されているため、定価程度で売る場合に取り締まられることはないと考えて良いだろう。
しかし、明らかに定価以上で販売したことが、古物営業法違反に該当する。また、この価格を見るに古物営業法違反のほか、高額で転売することによる物価統制令に抵触していた可能性が考えられる。チケット購入の代行は報酬が数千円程度で、1人で10枚~20枚購入させられていた。最もリスクのある部分を路上生活者に押し付けて、逮捕から逃れようとしていたのかもしれない。
嵐チケットをオークションで転売
2016年には、国民的アイドルグループ嵐のコンサートチケットをネット上で転売したことを受け、北海道警察が古物営業法違反の疑いで当時25歳の女性を逮捕している。当時の調べによれば、問題になった2015年の11月~12月にわたって、嵐のチケット5枚をインターネットオークションにて転売。約7万円の利益を上げていたとされる。
また、同様の方法を用いて女性はチケットを2014年10月~2016年4月の約2年間にわたって約300万枚売りさばき、1000万円の利益を得たと考えられている。本件が古物営業法違反にみなされたのは、無許可で金券に関して売買をしたためである。最近はチケットに関する取り締まりが厳しくなっているため、ファンの抽選を営利目的で妨げるためにダブ屋の行為を禁止する迷惑防止条例違反や高額で転売することによる物価統制令など別のものに抵触して取り締まられることもある。
しかし、当時の状況と古物営業法違反とみなされたことを考えると今回取り締まられるに至った理由は、利益を1000万円も上げていたことで、規模が大きく、個人間の域を超えているため、営業とみなされたことによるものだろう。
オークションで手に入れたチケットを金券ショップに転売
逆に、インターネットオークションに転売するのではなく、インターネットオークションで仕入れたものを古物許可を得ている金券ショップに転売したことで捕まった事例もある。
2008年に古物営業法違反で取り締まられた。当時39歳の女性は、アイドルグループSMAPの瞼の母の入場券4枚を東京都渋谷区の金券ショップに転売したことで捕まっている。この時には、正規料金が7000円だったのに対してインターネットショップでは41,000円で落札。チケットショップで60,000万円で買い取ってもらうことで、19,000円の利益を得ていた。
これもまた同様の方法を用いて、SMAP演劇チケットを2006年11月から2018年の約2年間にわたって約350枚のチケットを転売し、220万円の利益を出していた。インターネットオークションで販売するだけでなく、古物商に買い取ってもらうことでも営業とみなされ、古物営業法違反になることがあるため、注意が必要だ。
古物許可申請を得ていた古物商の逮捕事例
古物を業として扱う許可を得ているにも関わらず、逮捕されることもある。そこで、古物商の逮捕事例について確認していきたい。
チケット販売サイトのチケットキャンプ
2017年にミクシィの子会社であるフンサが運営するチケット売買サービスのチケットキャンプが、サイト上の表示について商標法違反・不正競争防止法違反の容疑で新規会員登録、新規出品、購入申し込みなどを停止。取引が始まっていないチケットは出品取り消しをおこなうなどして業務を停止した。2018年にはサービス自体が終了している。
タレント名の無断使用によるジャニーズ事務所の抗議を無視したことやはるかに市場価格を上回る売買をおこなっていたことが問題になったと考えられている。しかし当時、株式会社ミクシィの取締役の萩野泰西弘氏は、チケットに100万円払ってでも価値があると思う人がいる、何が高額なのか話し合いたいなどと発言していた。不正競争防止法は、弱者となりやすい消費者を保護することを目的として定められており、適正価格に関して言われているため、萩野泰西弘氏のような主張はまず通らないだろう。
このサイトは、スパム的な詐欺的手法でSEOを強化し、ネットの検索上位に引っかかるようにしていたことが、荻野泰弘氏の口から語られている。当時、チケットキャンプは転売ヤーによる悪質ネットチケット転売がおこなわれていたことからも警察署などから注目されていたと考えられるかもしれない。
また、チケットキャンプは古物商許可申請を得ていなかったのではないかという憶測が立っているが明確な情報は見当たらない。古物営業法違反で逮捕されていないことから、今回は古物許可を得ているものとして扱っている。
客の日本刀を勝手に販売
2019年には、顧客から預かっていた日本刀を借金返済のために現金を用意することを目的として、勝手に売却したことで70歳の古物商の男性が業務上横領の疑いで逮捕された。
当時の調べによると、男性が刀剣商の店長だった2013年2月に知人から1,450万円で販売を委託された日本刀を預かり、その翌日に質屋で1,000万円で販売していたという。これ以外にも少なくとも約20人から刀の売却を依頼されていたものの、中には所在がわからなくなっているものもある。その総額は2億にのぼると言われている。男性の供述によれば、2011年ごろから預かった刀を転売。顧客からの問い合わせなどをきっかけとして、2013年5月には解雇されていたという。
違法を通報できるシステムも存在
こうした数々の逮捕を受けて、違法と思われるものを通報できるシステムを開発した人もいる。その詳細について紹介したい。
違法を一斉送信できるチケキャン
チケットの転売に関しては、特に悪質な事例が多いとされていた。そのため悪質不正高額転売チケットに関して、簡単に通報できるアプリ・チケキャンなどが登場した。違法通知を一気にまとめて送信できるため、チケットキャンプなど、ファンにとって迷惑のかかるようなサイトを運営している会社を営業停止に追い込むこともできそうだ。
まとめ
インターネットの普及により、フリマアプリやインターネットオークションなどのCtoC取引が盛んになっている。そのため、フリマアプリで安く中古品を仕入れ、それより高く中古品を売る人やチケットなどを転売する人が増えてきている。しかし、こういった行為は黒に近いグレーゾーンであると考えられ、高額の利益を得た場合には営業とみなされ、古物営業法違反で取り締まられることが往往にしてある。
営利目的や事業として成り立つ程度に売り上げる場合には、古物許可申請を取っておくべきだろう。でなければ常にリスクがつきまとうと考えて良い。また古物許可を取っても義務を怠ったり、虚偽をおこなった場合に逮捕されることがある。そして、古物営業法以外にも遵守しなければならない法律は多い。
その一例が種の保存法、銃砲刀剣類所持等取締法、ワシントン条約のほか、景品表示法、特定商取引に関する法律、不正競争防止法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、犯罪収益移転防止法だ。また、扱う区分(品目)によっては家電リサイクル法、電気用安全法、消費生活用製品安全法にも注意が必要である。知らずに違法行為をおこなわないためにも、よく法律を理解して、注意して営業していきたいところだ。
この記事を監修した専門家