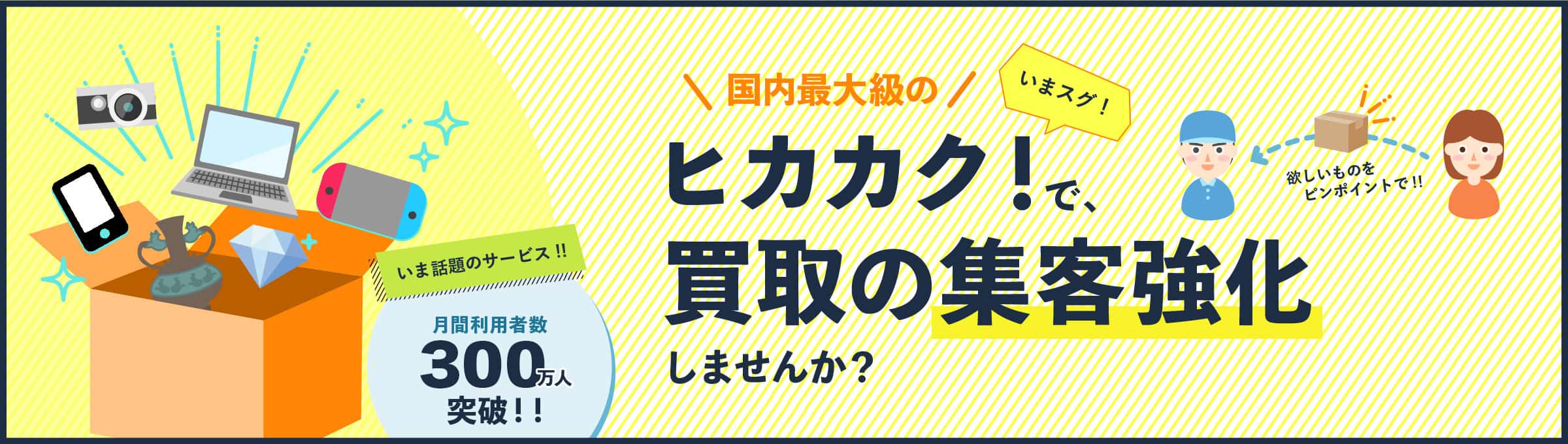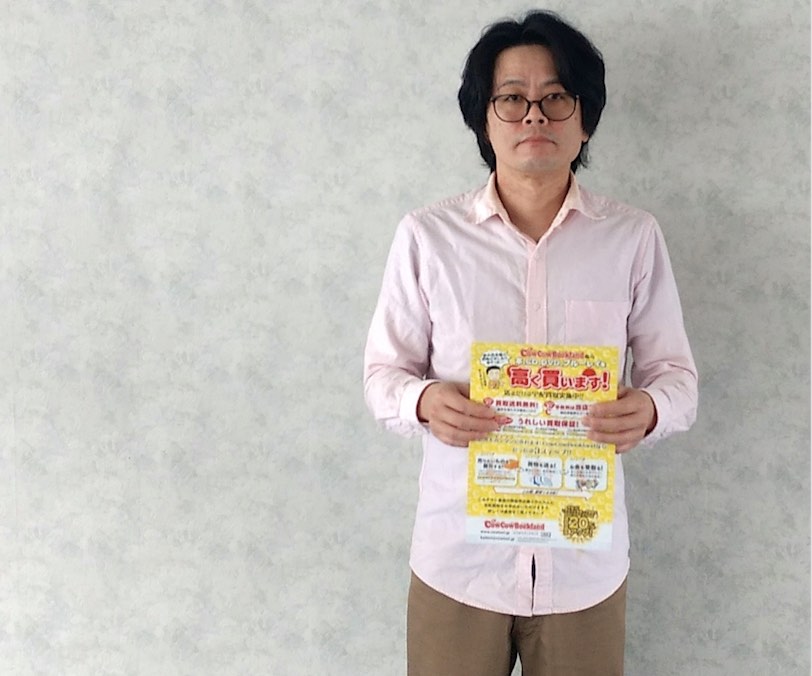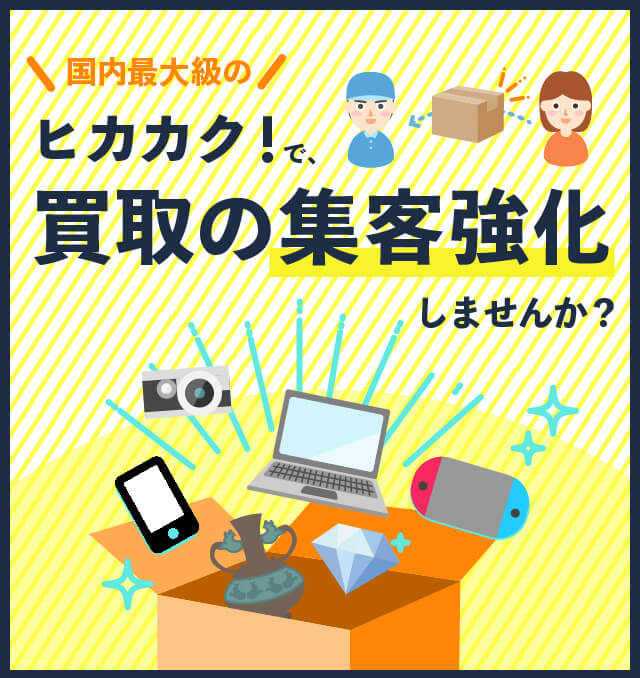古物商の許可を申請するにあたって営業所は必要だ。厳密には営業所のある・なしを記載する項があるのだが、営業所なしで古物商をおこなうケースは極めて少なく、調べても情報が出てこない。警察署に聞いても明確な回答が得られないという話を聞くこともある。
最近は、インターネットが普及し、サイトでの販売に限定し実店舗を持たないケースやヤフオク・メルカリといったCtoCを活用した転売で稼ぐケースも少なくないと思われるが、こういったケースでも営業所として登録していることが大半である。
そのため、古物商の営業所として登録する場はよく検討する必要があるだろう。ここでは、営業所の要件とともに認められるケースや認めなれないケース、特定の書類を用意すれば認められる可能性のあるケースなどを説明していく。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物商の営業所とは
古物商を始める為に許可を申請するが、事前に資金、人、場所を確保しなければならない。場所というのは営業所という業務をおこなうところを意味とし、事務手続きや古物を買い取る場所のことである。この場所というものには要件があり、これをクリアできなければ許可が取れないということになる。
そして古物商許可申請書の中に、営業所のあり・なしを記載するところがある。けれど、営業所がない例は極めて珍しいケースで原則ないと考えて良い。つまり、なしを選択すればほぼ許可はおりないというのが実情である。結局古物商を営むには、営業所は必ず必要であるということになる。警察署の見解による営業所の要件をクリアしなければならないのである。
営業所の要件とは
営業所は同じ都道府県なら設置数に限りはない。その場合、営業所ごとに必ず管理者1名が必要となる。もしも営業所が他県にまたがる場合は、其々の都道府県ごとに許可を取らなければならない。そして営業所と認められる為には、さまざまな要件を満たす必要がある。ここでは、営業所と認められる上で必要な要件について確認をおこなっていく。
営業所には管理者が必ず1人必要
古物商を営む上で管理者というのはとても大事なポストであり、重要な役割を担っている。よって複数の営業所を持つ場合でも、管理者は営業所ごとに必ず1人必要ということである。複数の営業所の管理者を兼任することはできないのである。なお、例外として、同じ敷地内に2つの営業所を持っている場合は兼任できることもある。
管理者になれない人もいる
管理者は誰でもがなれるわけではなく、古物営業法第13条第2項に管理者の欠格事由が定められている。つまり、申請者だけでなく、管理者も欠格自由を意識しなければならないということである。具体的には以下のような例がある。
- ・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- ・古物営業法で定める刑罰を受け5年経過していない者
- ・暴力団関係者や常習的に暴力行為をおこなっているとみなされる者
- ・住所が定まらない人
- ・古物許可が取り消されてから5年経過しない者
- ・聞聴から取り消し決定する前に自主的に返納して5年経過しない者
- ・未成年(一定の条件を満たしている場合は欠格事由とならない)
欠格事由の他に管理者になれないケース
ほかにも、管理者になれないケースというのは存在する。欠格事由以外で想定できるものを解説する。
営業所から著しく離れた場所に住んでいる
管理者として毎日通勤できるかというのも判断され、営業所のある都道府県以外に住んでいる場合は通勤に時間が掛かる恐れがある。このようなケースは避けた方がよく、人選がとても大事である。
常勤できない場合
他の会社などで働いていて、管理者としての勤務時間がほとんど取れない人は許可されない。
管理者の能力が十分でない
営業所の管理者は、古物営業法に関する知識を持たなければならない。これは、古物営業法第14条に定められている。
第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般 財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする
引用:古物営業法 第14条
営業所として認められる要件
営業所として認められる上では、使用権限があって周辺の関係者の理解を得ていることが重要となる。賃貸物件の場合や自社物件についても、賃貸契約書や建物の登記簿謄本、売買契約書のコピー等の提出が求められることもある。なお、賃貸契約書において、重要視される部分は以下の通りだ。
使用目的
使用目的が事務所となっている場合問題はないが、住居専用となっている場合は営業所としては認められない。但し賃借人から古物商の営業所として使用承諾書を得ることができるなら、住居専用であっても受理して貰える可能性が高い。
契約者
その物件を貸している人、借りている人が確認される。この確認は、使用承諾書を貰うべき相手が誰なのかということと、古物商許可の申請者と借りている人が同一人物であるかどうかということである。別の人物の名前があると受理してもらえない。このような場合にも使用承諾書を得ることが必要となってくる。
契約期間
契約期間が余り短いと受理されるのは難しい。もしも賃貸借契約期間が満了となる場合は、更新する意思があることを証明することが必要である。自動更新の場合もその旨を伝える内容の書面を添付することで受理は可能となる。
また、営業所が独立性を持っていることも項目として重要になる。独立性とは独立管理できる構造のことで、他社と共同使用している場合は、どの部分が申請したスペースなのかを明確にしておかなければならない。
同じフロアに複数の法人が入居していることも少なくないからである。自宅の場合においても、家族数人がネットショップを別々に運営するのは難しいとされる。其々独立した空間を必要とする為で確保は困難である。
レンタルオフィスを利用することは可能か
賃貸借契約書を提出することで、レンタルオフィスを営業所として使用することが可能である。ただ、ある程度の継続が求められているので数ヶ月以上の賃貸借契約期間が必要となる。これは都道府県によって変わってくるので事前のリサーチが必須である。
また、使用承諾書が求められることが多く、この書類が得られない為に古物商の許可が取れないというケースが少なくない。よく見られるケースとしては、賃貸契約書の使用目的欄が住居専用となっていて営業を認める記述がないことである。こういった際には、所有者から古物商の営業所として認めてもらわなければならない。
つまり使用承諾書を作成してもらうこととなるのである。そして、実家を営業所にする場合は、その所有者である親や兄弟の承諾書が必要となってくる。例えばマンションの場合では、管理組合に認めてもらうのが必須である。
使用承諾書はその建物の登記簿上の所有者からもらうことになる。その建物の管理会社や管理組合ではないので注意が必要である。所有者が分からないときには、法務局でその建物の登記簿を取得する。
営業所を新設する場合について
これまで、すでに営業所に据えようとしている場がある場合について解説してきた。ここでは、古物営業をおこなうにあたって、新たに営業所を新設する場合について確認していく。
同一都道府県に新設する場合
既存店舗がある都道府県内に新設する場合は、変更届によって店舗の新設の届出をおこなう。届出は店舗所在地の所轄警察署を経由して公安委員会へ出すことになる。届出期限は新設のあった日から14日以内となり、登記事項証明書の添付が必要となる場合は、20日以内となる。
他の都道府県に新設する場合
他の都道府県に新設する場合は、改めて古物商の許可申請をおこなう。そして同じようにその地域の所轄警察署に許可申請をおこなって公安委員会の許可を受ける。
古物商の営業所として認められないケース
先ほど、古物商の営業所としての要件を述べたが、その要件を満たしていないと営業所としては認めて貰えない。ここでは、営業所として認められないケースをいくつか紹介する。
自宅を営業所にする場合
古物の取引きをネットでおこなう人が増え、実店舗を必要としないため自宅を営業所にする場合が少なくない。この場合は簡単なようであるが、いくつかの注意点があり営業所として認めて貰えないケースも存在する。
住居専用の賃貸物件の場合も困難
賃貸の使用目的の多くは居住専用となっていて、あくまで居住する為に借りているということになっている。それを古物商を始めるからと言って、営業所として申請するのはルール違反となる。従ってこの場合は認めて貰えないケースとなる。
また、不特定多数の来客を前提とし、店舗のような使い方をすれば周辺住民とのトラブルが予想される。特にマンション、アパートなどの共同住宅では問題が生じる可能性は大である。このことから結果、認めて貰えないだろう。
公営住宅や寮の場合も困難
公営住宅の場合は、営業行為を規約で禁止しているので承諾を得られることはまずないようである。ただ、使用承諾書を大家さんなどに作成して貰えれば、認められる可能性は高くなる。学生が寮などに住んでいてネット販売をしようとするときは、居住期間が限定されているので認められない可能性がさらに高まる。
自宅が使用賃借物件(賃料無し)で書類を集められない場合
所有者の好意によって賃料なしで貸して貰っている場合もあるが、このようなケースでは、貸主の建物登記簿謄本、無償での使用に関する契約書、使用承諾書の提出がなければ認めて貰えない。
自己所有で所有の証拠が出せない場合や独立性のない場合
この場合はスムーズにいきそうだが、本当に所有しているという証拠がなければ認められない。つまり登記簿謄本などの添付が求められるということである。又既に家族が同じ建物で古物商を営んでいる場合は、独立性が求められるため受理してもらえないケースもある。事前に警察署で相談するのが望ましい。
レンタルオフィスも難しいケースが多い
古物商許可を取得するには営業所を必ず設けなければならない。しかし、費用の面などからレンタルオフィスを借りる人も少なくない。自宅を営業所にしたくても使用承諾書を得られない人もいるわけである。
こういうとき、レンタルオフィスを営業所に出来るかどうかである。レンタルオフィスはさまざまで簡単に区切られただけのスペースなどは独立性があるとは言えない。従ってこの場合は認めて貰えないことになる。
また、契約期間も大事で長期契約をしていなければ認めて貰えないケースが多い。短期契約にすることで信用性がなくなるということである。ただ、この場合も完全な個室であるレンタルオフィスなら認めて貰える可能性は大きい。
レンタルスペースを古物商の営業所にする場合
レンタルスペースとは、会議や研修、イベントなどの用途で使用することが多く、ほとんど時間ごとの料金設定になっている。これは営業所としては認められない。
バーチャルオフィスを古物商の営業所にする場合
バーチャルオフィスというのは、住所、電話番号等のみを借りて、業務は別の場所でおこなうスタイルを言う。電話は転送というのがほとんどで、実態の備えていない架空の空間とみなされる。これは論外であって、店舗は必要でなくても営業所の役割がある以上、架空は認められない。
警察署が営業所として確認する内容
警察は建物の外から物件を確認することが多く、室内確認をするのは稀である。しかし、地域によっては、立入検査があったり、予告なしに営業所を訪問することもあるため注意が必要だ。その際、古物台帳の有無のチェックや調査などが実施されることが少なくない。警察署によっては、見取り図や外観の写真、営業所の賃貸契約書、信用承諾書などの提出を求めるケースもある。
まとめ
営業所を据えるにあたっては、住居の使用目的や契約者、契約期間などが重視される。しかし、仮に使用目的が住居限定であっても、周りからの協力が得られたり、大家から許可を書面を持って得ることができれば営業所として認められる可能性が高まる。
また、営業所を構える条件を満たしているかだけではなく、管理者にも欠格事由でないことやすぐに駆けつけたり常勤できるか、専門知識を有しているかなどが問われるため、適切な人材を検討していく必要がある。複雑な事情のある建物については、なかなか一般の人が許可を得るにあたって準備をしたり、可能かどうかの判断をしたりするのは難しいと言われている。
そういったケースについては行政書士に相談する方が、結果的にスムーズになることが多い。行政書士も仕事である以上、有料になってしまうが営業所としたい場所に複雑な事情がある場合については、行政書士への相談も視野に入れた方が良いだろう。
この記事を監修した専門家