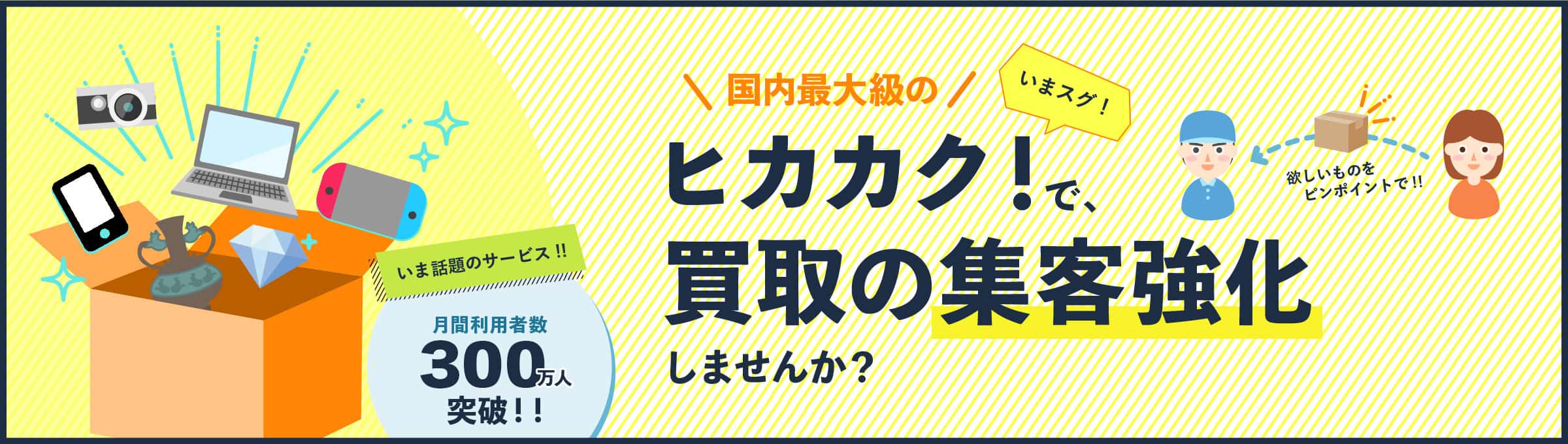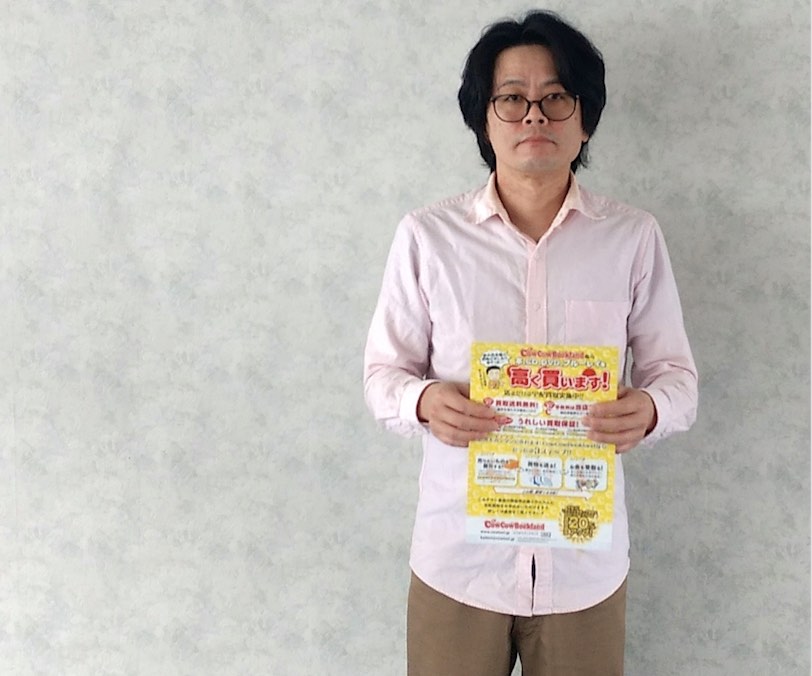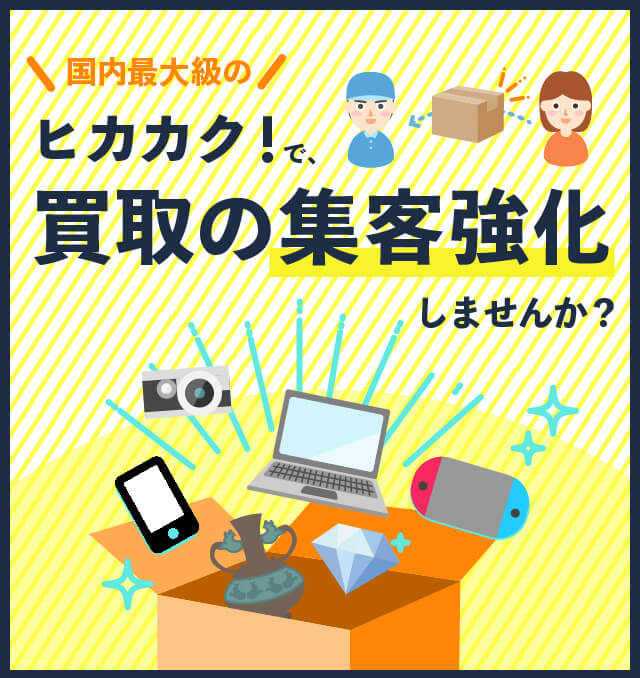古物商は1度許可を受けると変更届が提出であったり、2018年の法改正では、主たる営業所等届出」が必要になったりするものの、ずっと古物商として営業をおこなうことができる。しかし、誰でも永続的に使用できるわけではなく、一定の条件で古物商許可が取り消されたり、返納を求められたりすることがある。
使っていないと許可が取り消されるという話を耳にしたことがある人も多いのではないだろうか。また、その使っていない期間を明確に知りたい人もいることだろう。使っていないと取り消されるのかという点を含め、古物商許可が取り消される条件や期間、返納が必要なケースを中心に解説していく。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物商に関するルール
古物商のルールは古物営業法という法律によって定められている。その構成は、古物営業の許可に関わる手続きなどの規定は第4条から第8条となり、その他さまざまな規定を含めると第39条までとなっている。この全ての規定を熟知する必要はないが、できれば理解しておくにこしたことはない。
古物商に関するルールがある理由
古物営業法の目的は第1条に定められており、以下のように記載されている。
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る為、古物営業にかかる業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資することを目的とする
引用:古物営業法第1条
つまり、古物商のルールがある理由は古物の売買で犯罪被害品を扱ってしまった場合、犯罪を助長してしまう恐れがあるからである。
古物営業法の改正
2018年4月17日古物営業法が改正され、4月25日に公布された。今回の改正では4点の変更が施工され、すでに始まっているものもある。
許可単位の見直し(2020年4月頃までに施工)
- ・改正前:複数の都道府県に出店する場合、都道府県ごとに許可を受ける必要がある。
- ・改正後:複数都道府県に出店する場合でも、主たる営業所で許可を受ければ、他の都道府県では届出だけでよい。
主たる営業所について
改正により、主たる営業所の所在地で許可を受ければ、他の都道府県では届出だけで営業所を設けることができる。今まで営業所がある都道府県ごとに古物商許可が必要であったため、手間や時間がかなり掛かっていた。そのため、新たな許可申請は不要とする措置の要望が多くあったことにより改正されることになった。
施工は2020年4月頃であるが、現在許可を受けている全ての古物商などは、引き続き営業をおこなう場合、この改正法の施工前に、主たる営業所等届出書を主たる営業所等の所在地を管轄の警察署へ提出する必要がある。
複数の都道府県で古物商を営んでいる場合や1つの都道府県内で複数の営業所がある場合は、自社の主たる営業所をどこにするか決定する必要がある。この届出は、1つの都道府県からのみ許可を受けている古物商や営業所を1つしか持たない古物商などもおこなう必要がある。
届出期間
2018年10月24日から法改正全面施工日まで(施行日予定は2020年4月24日まで)に主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に届け出る必要がある。
営業制限の見直し(2018年10月24日より施行)
- ・改正前:買い取った古物を受取れる場所は、営業所か相手方の居所のみ
- ・改正後:事前に届出をすれば、仮設店舗で買取ができ古物も受取ることができる。
仮説店舗について…仮の店舗を設けることになったが、仮設店舗にあたるのかあたらないのかという問題が生じてくる。この判断は難しいと言える。
簡易取消し制度の新設(2018年10月24日より施行)
- ・改正前:許可取消しには、3ヵ月以上所在不明であることなどを公安委員会が立証し、聴聞の手続きを経る必要がある。
- ・改正後:古物商などの所在を確知できないなどの場合、官報に公告をおこない、30日を経過すれば許可取消しができる。
欠格事由の追加(2018年10月24日より施行)
- ・改正前:暴力団員や窃盗罪で罰金刑を受けた者でも、古物営業許可の制限はない。
- ・改正後:暴力団員や窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除する許可の欠格事由の追加
上記4点が変更点であるが、法律だけでなく施行規則も改正され施工されている。
本人確認方法の追加(2018年10月24日より追加)
古物買取の際に必要な本人確認に5つの方法が追加された。
- ・2種類以上の身分証明書などで確認
- ・スマートフォンなどで撮影した身分証明書などの画像の送付を受けて確認
- ・身分証明書などのICチップ情報の送信を受けて確認
- ・売主の容貌の画像+顔写真付き身分証明書の画像で確認
- ・売主の容貌の画像+身分証明書のICチップ情報で確認
古物商許可を取る前の注意点
古物商の許可を得る際には、いくつかの注意点がある。ここでは確認したいポイントをピックアップしていく。
個人の許可か法人の許可か
古物商の許可は、個人で取る場合と法人で取る場合がある。会社として古物商を営むなら法人としての許可を取らなければならない。たとえ社長や従業員が古物商許可証を持っていても、会社に使用することはできない。
反対に会社が古物商許可を取っていれば、役員など個人が取得していなくても営業はできる。もし社長が個人で古物営業をしようとしても、個人で取得していない限り営業できない。個人か法人かは事前に確認しなければならない。
法人で申請する場合の必要書類
法人の申請は、個人の申請より必要書類が多くなり、以下のものが必要となる。
- ・法人の登記簿(履歴事項証明書)
- ・役員全員の略歴書
- ・役員全員の住民票などの書類
- ・定款の写し(会社を運営していく上での基本的原則を定めたもの)
申請先をしっかり把握しておこなう
古物商の許可の申請は、古物営業をおこなう営業所の所在地を管轄する警察署でおこなう。各警察署を通して、最終的には各都道府県の公安委員会が許可か不許可の決定をする。自宅の住所ではなく、営業所の住所が基準となる。
申請窓口は警察署ごとに異なり、防犯係か生活安全部などでおこなう。警察署の申請窓口は平日のみで、土日祝日や夜間は受け付けて貰えない。東京都の場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっている。本人以外の家族が申請する場合は、委任状を提出する必要がある。
しかし書類の不備があれば手続きが難しく遅れる場合がある。代理の場合は行政書士などの専門家に依頼した方がスムーズに手続きができる。できれば事前に予約をしておいた方が無難である。古物営業許可申請の手数料は19,000円で、申請を取り下げたり、不認可になったとしても返還はされない。
古物商許可は返納・取り消しもあり得る
古物商は申請時に注意を払えばそれで終わりというわけではない。許可を得たあとの注意点についても確認していく。
古物商を返納しなければならないケース
古物商許可は、1度取得すると更新の必要はなく使い続けることが可能である。しかし、許可証を返納しなければいけないときがある。
古物商の営業を辞める場合
古物商の営業を自ら辞めてしまう場合は、許可証は返納しなければならない。有効期限がないといっても、廃業した後も持ち続けることはできない。また、許可を取った人が死亡、許可を受けた会社が消滅した場合も返納の必要がある。
個人で古物商許可を得ていた人が亡くなると許可証は返納しなければならない。またこの許可証を家族に相続させることはできない。法人で取得していた場合、別の会社と合併したり、会社自体が消滅したときには返納しなければならない。
許可を取得後、状況が変化した場合
最初正当な手段で許可を取ったが、その後状態が変化した場合返納しなければならないケースが出てくる。例えば許可を取ったときには破産者でなかったが、後に破産者になると返納する義務がある。そのほか、聴聞が取り消しされる前に自ら返納するケースも見られるが、この場合には返納してから5年間は古物商の許可を得ることができないため注意が必要だ。
古物商許可が取り消しになるケース
古物商許可は1度許可が下りれば永続的にできるとされているが、許可が取り消しになるケースもある。取り消された場合に再度許可を得ることができない限りは、古物商をおこなうことができない。ここでは、取り消しになるケースとして想定できるものを説明していく。
古物営業法違反をおこなった場合
法律違反などをした場合などに古物商が取り消しになる。想定できるケースは以下のとおりだ。
- ・他都道府県で無許可営業をおこなった
- ・名義を貸す(免許を貸して古物の売買をおこなわせた)
- ・営業停止命令などに従わない
- ・自身の犯罪歴などを隠したり嘘をついて許可を取得した
- ・三ヶ月以上所在が不明
なお届出を怠っていると、所在不明と判断される可能性がある。
許可を受けてから6ヵ月以内に営業を開始しない場合
古物商許可を取ってもなかなか営業を開始しないと許可が取り消されてしまう。許可を取って6ヶ月間も営業を開始しないのは、古物商の営業をできない可能性が高いと判断される。営業許可を取得するのには40日~50日程かかるため、計画性をもって許可を申請することが大事である。許可を取得したら直ちに営業を開始するのが望ましい。
営業を6ヶ月以上休んでいる場合
営業を開始してから、何らかの理由で店を6ヶ月以上閉めている場合も返納しなければならない。営業活動がされているかどうかが判断基準になる。また連絡が取れない時や住所が分からないなど、公安委員会が所在を3ヵ月以上把握できない場合も取消しになる可能性がある。
また、個人で古物商許可を取っている人が引っ越しをするとき、営業所の移転とみなされるため、住所の移転届が必要となる。これを怠ると所在不明とみなされ許可を取り消される可能性が出てくる。取り消されたことを知らずに営業を続けていると、無許可営業になってしまうので注意しなければならない。
仮に個人で許可を取得した人が死亡した場合に、親族または法定代理人に返納義務が課せられるため注意が必要だ。義務違反とみなされないためにも、あらかじめ親族や法定代理人には、死亡の際には返納義務が生じることを説明しておくと良いかもしれない。
古物商が所在不明で一定条件を満たした場合
古物商が所在不明となり、所在地等を確知できないときには、公安委員会が官報により公告し、公告後30日を経過しても古物商からの申出がない場合に取り消しがおこなわれる。公安委員会は、古物営業法第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明した時は、その許可を取り消すことができる。
許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと
引用:古物営業法第6条第3項
この上記の古物営業法により許可が取り消される可能性は大きいため、とりあえず取っておこうという安易な考えはしない方が賢明である。申請時にそのようなニュアンスを伝えることで、申請が拒否される可能性がある。営業をどのようにおこなっていくかという計画性を持ち、ある程度煮詰まってからの申請が望まれる。
古物商許可証の返納の仕方
返納するには、取得した警察署に届出を出すことになる。手順としては以下のとおりだ。
- 1.警察署担当者へ返納する旨を電話連絡する。
- 2.返納理由書の記入(各都道府県の所定の様式)
- 3.ホームページを用いて営業していた場合、ホームページの閉鎖の届(所定の様式)
- 4.担当者と打ち合わせた日時に警察署で返納書などを提出
- 5.古物商許可証を返納
なお、古物商許可の標識に関しては、返納する必要がなく自身で廃棄しても構わない。古物台帳も返却しなくてよいが、3年間保存しておく義務がある。何故なら営んでいたときに扱った物が盗品だった場合、警察の捜査の重要な手掛かりになるからである。
返納する必要があるにも関わらずしなかった場合
返納しなければいけない要因があるのに返納しなかった場合、義務違反として10万円以下の罰金が科せられる。仮に許可者の死亡または法人の消滅による返納義務を怠った場合には、5万円以下の科料となる。
第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。 一 その古物営業を廃止したとき。 二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
引用:古物営業法第8条
しっかり把握して違反や罰則がないようにしなければならない。
古物商許可を取り消された後について
古物商営業許可を取り消された場合、以降5年間は新たに許可を取得できなくなることがある。法や規則をしっかり把握するのは必須である。
第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む
引用:古物営業法第4条第6号
まとめ
古物商を使っていないケースで許可が取り消される条件を考えると許可を受けてから6ヶ月の間、開業をしていないか、6ヶ月間休業している場合に取り消されることになる。古物商許可の申請が1発で通るとは限らないため、早めに許可申請を出す人もいると思われるが、許可を受けてから6ヶ月以内に開業できそうかについても検討しておいた方が良いだろう。ちなみに販売サイトの準備など、活動をしていれば取り消されることがないらしい。
なお、古物商をおこなっていた人が亡くなったときは、個人で登録していた場合に引き継ぎができないため、古物商の返納をおこなう必要がある。この場合、返納は親族や法定代理人がおこなう義務が発生し、おこなわない場合に違反と見なされ、刑に処される。また、古物商が所在不明になり公告が出され30日放置したり、古物営業法違反によって許可を取り消されることがある。
2018年の法改正で提出を求められている、主たる営業所等届出も提出しないと、全面施行日の2020年4月ごろ以降は無許可営業とみなされた結果、刑に処され、許可を取り消される危険性もある。そうなると古物営業法に基づき、現在営業をおこなっている古物商は間違えなく提出をおこなっておきたいところだ。
返納が求められるケースもあるが、これは主に古物営業を止める場合や破産者になってしまうなど許可申請時と状況が変わってしまった場合になる。欠格事由に該当してしまったら返納すると考えて良いだろう。また聴聞が取り消される前に自ら返納するケースも見られるが、この場合には5年間は改めて許可申請をおこない古物商許可が得られないため注意が必要である。
この記事を監修した専門家