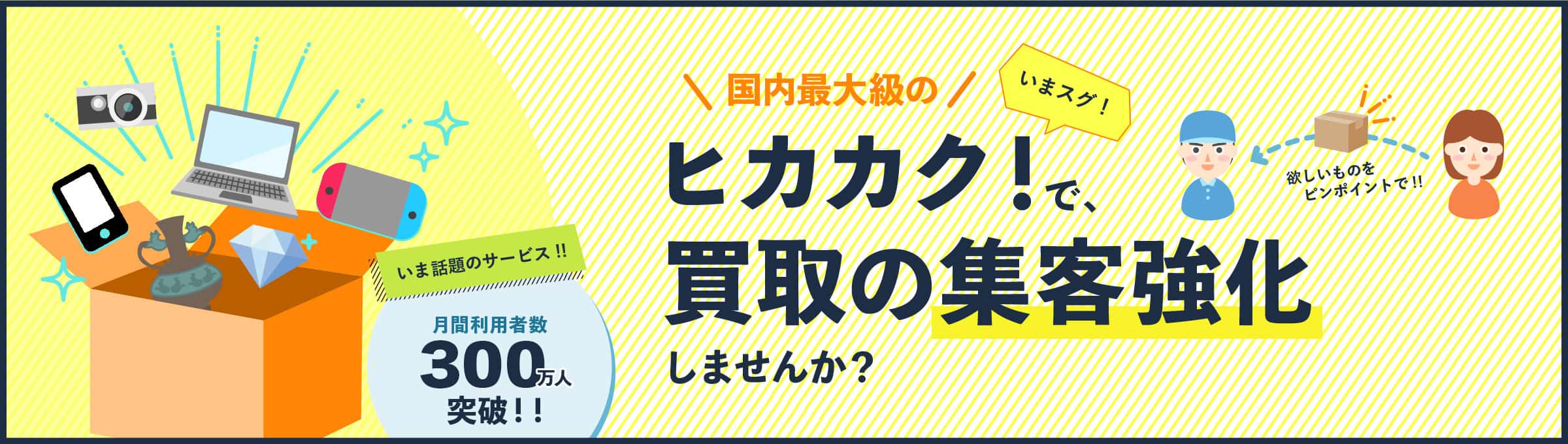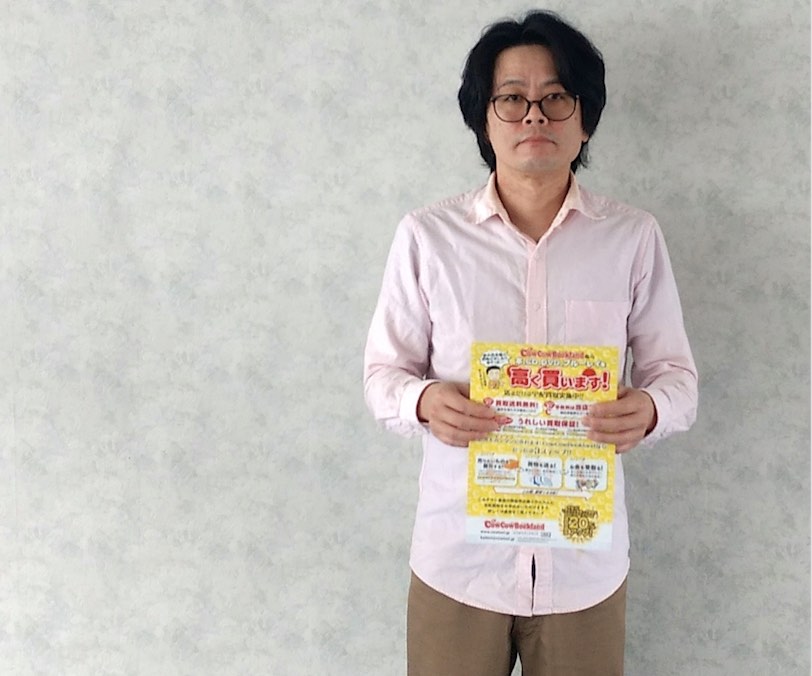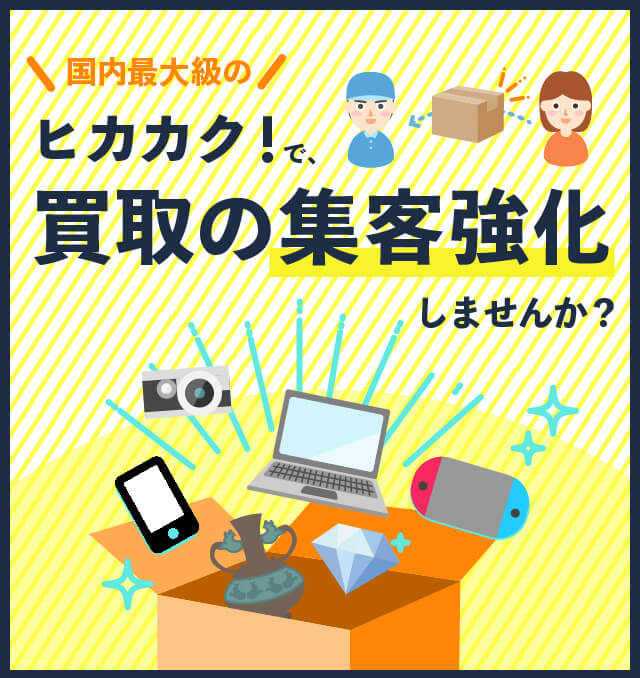古物商許可は誰でも取得できるわけではなく、一定の欠格要件に当てはまる人は許可を取得することができない。古物商の許可を得ようと思って書類をそろえて提出しても、確実に落ちてしまう人というのが存在する。この条件を欠格事由と言い、これに当てはまる限り、許可が降りることはない。
古物商許可の審査にかかる標準処理期間はおよそ40日間とされており、その間警察署では申請者が欠格要件に当てはまらないかを確認している。
つまり、欠格要件に当てはまっている場合に、許可申請が通ることはまずない。これは、古物の盗品などの流通を阻止するためにおこなわれていることであり、例外はない。
古物商は許可申請を得るために膨大な資料を集め、小難しい内容を見ていく必要があるため、欠落事由を抑えていないと、かなり費用や時間を無駄にしてしまうこともある。その上、古物商許可と開業準備を同時進行でおこなっていることが多いと思われるが、その開業準備が全て無駄になってしまうこともあると考えられる。
したがって、まずは欠格要件を確認すべきと言えるだろう。ここでは、法律の条文のままではわかりにくい部分に関して解説を加えなながら、噛み砕いて欠格要件とその適用範囲を確認していく。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
古物商許可の欠格要件とは
古物営業法第4条では以下のように記載されている。
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない(古物営業法第4条)
つまり、古物商の欠格要件というのは、古物営業法に基づき、厳格に定義されているのである。ここから、欠格要件を1つ1つ確認していくこととする。
成年被後見人、破産者で復権を得ない人
古物営業法第4条第1号では以下のように書かれている。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(古物営業法第4条第1号)
成年被後見人や被保佐人とは、判断能力が不十分な方、サポートが必要な方のことを指す。具体的には、認知症をわずらっている方、精神上の障害により判断能力が不十分な人などが該当する。
古物商は大切な商品の取引をしたり、大金を扱ったりするケースも少なくない。そのため判断能力が不十分で、自分で適切な判断ができない方は有効な契約行為をすることができないと考えられ、古物商許可を取得できないようになっている。
そして、破産者で復権を得ない者とは、破産手続きを開始してから免責許可の決定が確定するまでの方のことを指す。つまり、破産者であっても免責決定が確定していれば、復権を得ている状態になるため、欠格要件にはならない。
通常、破産手続きの申し立てと免責手続きの申し立ては同時におこなうので、破産手続きが終了して破産手続き中でなければ欠格要件には該当しないということになる。
所定の刑罰を受け、5年を経過していない人
古物営業法第4条第2号であるが、以下のように記載されている。
禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者(古物営業法第4条第2号)
過去5年以内に禁錮以上の刑を受けたり、特定の犯罪で罰金を課されたりした者は、古物商許可を取得することができない。
禁錮以上の刑を受けた者には、執行猶予付きも含まれるため、刑務所に入った者だけではない。しかし、執行猶予期間が満了すれば、5年の経過を待つことなく、ただちに古物商許可を取得できるようになる。
特定の犯罪とは、古物商に深く関係する犯罪を指す。窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪、盗品等有償譲受け罪や古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反。これらの犯罪の罰金刑を受けた者も5年間は古物営業許可を与えないことになっている。なお、窃盗罪に関しては、2018年10月24日より施行された新しい要件である。
暴力団関係者など
古物営業法第4条第3号及び第4号では、以下のように記載されている。
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものをおこなうおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(古物営業法第4条第3号)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条もしくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(古物営業法第4条第4号)
第3号、第4号とは
第3号、第4号は次の者を指す。
- ・暴力団員または暴力団でなくなった日から5年を経過しない者
- ・暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的または常習的に暴力的不法行為等をおこなうおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等をおこなったことがある者)
- ・暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令または指示を受けてから3年を経過しない者
つまり、暴力団関係者であったり、暴力的不法行為を常習的におこなっていると判断されると、古物商許可を取得することはできない。また、すでに古物商許可を取得していた者が、この欠格要件に該当することが発覚した場合、古物商許可は取り消しの対象となる。
追加された欠格要件
なお、「暴力団組織」と「暴力団以外の犯罪組織」に関する欠格要件は2018年10月24日より施行された新しい要件である。
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等流通の防止、盗難品の早期発見により、迅速な被害回復、その他の犯罪を防止することを目的としている。
そのため、前述のように窃盗罪で罰金を受けた者に加え、暴力団関係者は犯罪に利用するおそれがあって古物商・古物市場主として適切でないことから、欠格要件に追加された。
住所が定まらない人
古物営業法第4条第5号では、以下のように記載されている。
住居の定まらない者(古物営業法第4条第5号)
住所のない者は古物商許可を取得することができない。許可申請をするときに住民票を提出する必要があるため、実際に審査中に欠落要因であることが判明して問題となるケースはほとんどないと思われる。
しかし、引っ越しをしたあとに住民票の移動ができていない事実が発覚した場合は、古物商許可が取得できないため住民票の移動は忘れずおこなわなければならない。
古物許可の取消から5年経過していない人
古物営業法第4条第6号では、以下のように記載されている。
第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)(古物営業法第4条第6号)
古物商許可は取得後であっても、罪を犯すと取り消される。古物営業許可の取り消し処分を受けると、その後5年間は古物商許可を取得することができない。個人でも法人でも同様で、法人営業の場合は、その法人の役員をやっていた者も5年間古物商許可の取得ができなくなる。
この場合の役員には許可を取り消された当日に役員だった者はもちろん、処分前に聴聞の日が公示された日の60日前まで役員だった者も含まれる。ちなみに、聴聞とは、許可取り消しになる違反をして、取り消しが正式に決定する前に行政から調査のために意見を聞かれることである。
聴聞取消決定前に返納して5年経過していない人
古物営業法第4条第7号では以下のように記載されている。
第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの(古物営業法第4条第7号)
聴聞があると知り、古物商の許可を取り消される可能性があると思い、聴聞から取り消しが決定するまでの間に、自ら許可を返納したとしても許可取り消し処分と同じ扱いになる。そのため、5年間は古物商許可を取得することはできない。
一部例外を除いた未成年
古物営業法第4条第8号では以下のように記載されている。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする(古物営業法第4条第8号)
未成年者とは満20歳に達しない者のこと。ただし、未成年者でも古物商許可を取得できる3つの例外がある。それが以下の通りとなる。
婚姻した者
民法には、未成年者が婚姻をした場合には成年者とみなす旨の規定がある。よって、結婚すると成年者と同じとみなされ、古物商許可を取得することができる。
法定代理人から営業を許され、その登記がある
相続は関係なく、法定代理人(一般的には親権者である親)が古物営業について同意した場合、未成年者であっても古物商許可を取得することができる。この場合の古物商許可の申請には、法定代理人の同意書と未成年者登記簿が必要だ。
未成年者登記簿には、申請者が未成年であることや、古物の売買をおこなうこと等が記載される。これにより、取引相手に対して自身が未成年であるということを伝え、安心して取引をおこなえるようにするのである。
古物商の相続人である者
古物商の相続人が未成年者であっても、法定代理人が古物営業の欠格要件に該当する者でないときは古物商許可を取得することができる。
例えば、父親が古物商をしており、亡くなった場合などが想定される。父親の相続人である子が、営業を引き継ぎたいときは、相続人が未成年であっても欠格要件に当てはまらない。
しかし、未成年者は一人で契約などをおこなえないため、法定代理人を立てないといけない。この法定代理人が欠格要件に当てはまらなければ未成年でも古物商許可を取得することができる。
ただし、未成年者本人が営業所の管理者となることはできないため、最低1人成年者の管理者が必要となる。
遠すぎる管理者を立てている場合
古物営業法第4条第9号では以下のように記載されている。
営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者(古物営業法第4条第9号)
古物商許可を取得するとき、かならず営業所の管理者を選ばなければならない。管理者とは、営業所で古物の適正な管理や、従業員の指導や監督をするなどの役割を担う。この業務を適正にできない者、つまり欠格要件に当てはまる者を管理者に選んでいると、古物商許可を取得することはできない。
また、管理者は営業所に常勤している必要があり、管理者が営業所に通勤・常勤できない場合は、管理者になることはできない。よって、住所が営業所から著しく離れている者も管理者の業務を適正におこなえない者とみなされ、古物商許可を取得することはできない。
役員に欠格要件に該当する人がいる場合
古物営業方第4条第10号では以下のように記載されている。
法人で、その役員のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの(古物営業法第4条第10号)
会社・法人が営業許可を得る場合は、その役員に上記の欠格要件に該当する者がいれば、古物商許可を取得することができない。社長だけでなく役員全員が対象であるが、その役員が未成年者であっても問題はない。
欠格要件は申請者だけの適用ではない
古物商許可は、適用範囲が申請者だけではない。許可に当たって重要となる適用範囲について、個人と法人とで改めて整理する。欠格要件に関して、個人と法人はそれぞれ、下記の者も欠格要件に該当しないことを確認しなければならない。
個人の場合
古物営業法第4条第9条にあるように、申請者本人だけではなく、古物商の管理者も欠格要件に当てはまらないよう注意が必要である。
法人の場合
古物営業法第4条第10号にあるように、代表取締役、取締役、監査役などの役員全員と古物商の管理者が欠格要件に当てはまらないよう注意が必要である。
まとめ
古物商における欠格要件は、
- ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人
- ・所定の刑罰を受け、5年を経過していない人
- ・暴力団関係者や常習的に暴力的不法行為をおこなっている人
- ・住所が定まらない人
- ・古物許可の取り消しから5年経過していない人
- ・聴聞から取り消しが決定する前に自ら返納して5年経過しない人
- ・一部例外を除いた未成年
- ・欠格要件に該当する管理者や営業所から遠すぎる管理者を立てている場合
- ・役員に欠格要件に該当する人がいる場合
となる。
つまり、申請者1人だけが欠格要件に該当しないことを注意しばければ良いのではなく、個人の場合には管理者、法人の場合には役員全員が要件に当てはまっていないことを確認しなければならない。この確認を怠った場合に、欠格要件が原因で古物商許可申請が通過しないことがあるかもしれない。
この記事を監修した専門家