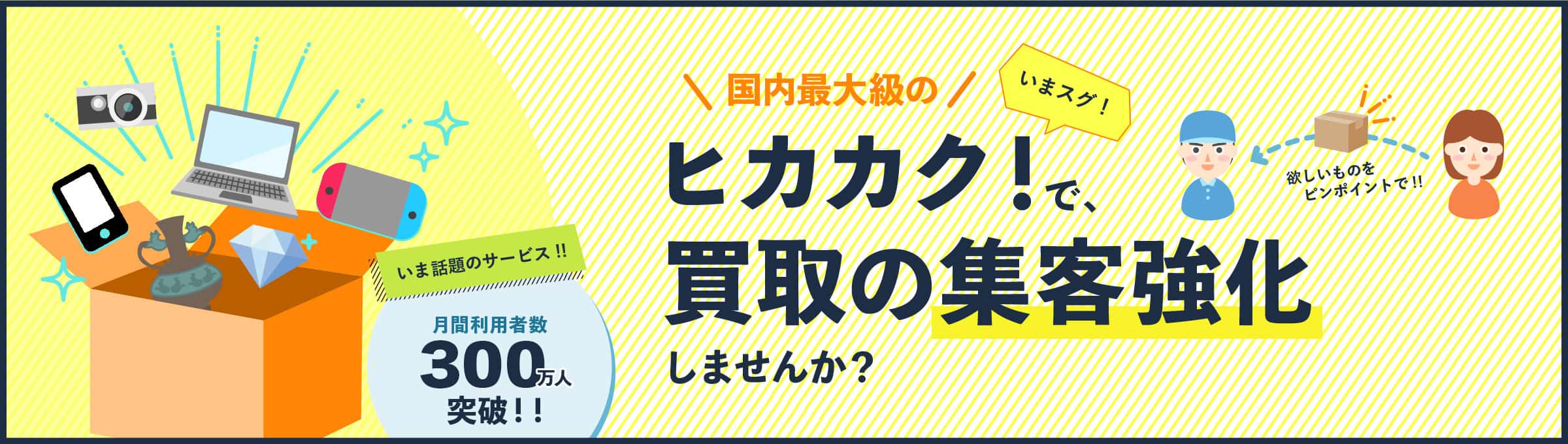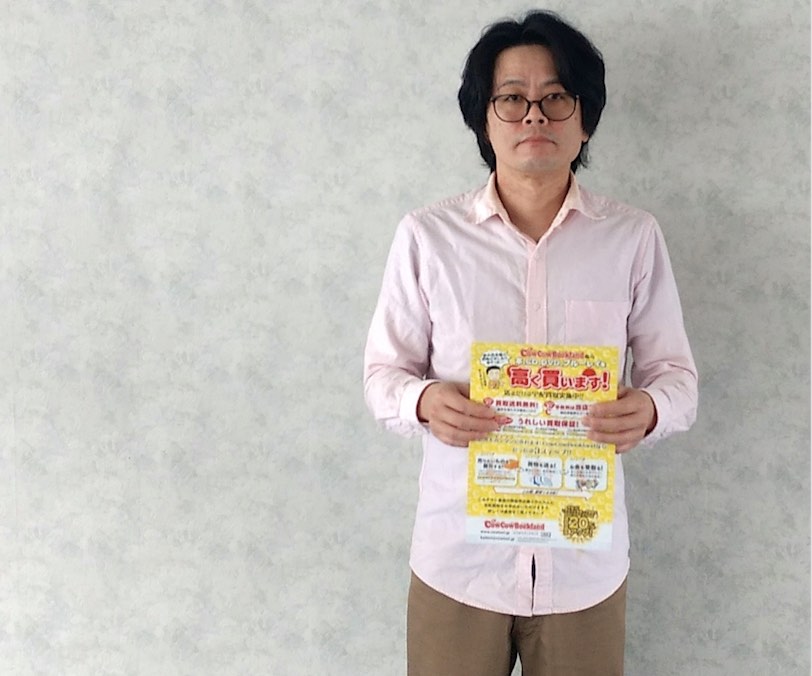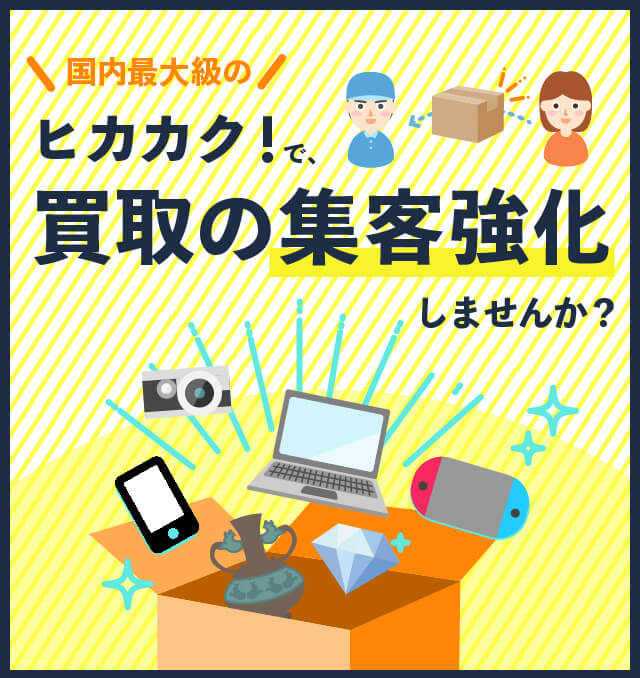不用品回収業者や物を処分したい人にとって知っておかなければならないのが、家電リサイクル法の対象外商品。不用品を回収し、あるいはしてもらい、処分する上で必要不可欠な知識となるだろう。
仮に対象外の商品や適切な処分方法を知らない場合に、回収業者は違法行為で罰せられる危険性がある上、消費者であっても不法投棄の責任は持ち主に求められる。
また、放置方法がわからず、不用品を抱えたままになる可能性もあるだろう。そこで、家電リサイクル法の対象外商品を整理した上で、処分方法について確認していきたい。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
家電リサイクル法の概要
家電リサイクル法の正式名称は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号・平成13年施行)となる。
特定家庭用機器再商品化法が定められた経緯は、一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品が、約半分はそのまま埋め立てられていたことに由来する。廃家電製品には有用な資源が多く含まれている上に、廃棄物最終処理場がひっ迫する問題が生じていた背景から、制定されたとされる。
環境を守ることを目的とした法律であるため、以下の要件が義務付けられている。
- ・小売業者に対しては引取の義務
- ・製造業者に対してはリサイクルの義務
- ・消費者に対しては料金支払いの義務
概要の詳細については環境省のホームページに掲載されている。
制度趣旨
家電リサイクル法の目的は、ごみ減量化とともに、家電品の中にある資源(鉄、アルミ、ガラスなど)の有効活用である。
制定の背景としては、深刻な不法投棄・不法スクラップ問題が背景ある。そのため、国・地方自治体が連携し、不法投棄や不法スクラップ対策をおこなっている。リサイクル法が施行された平成10年代前半に比べれば減少傾向にあるが、未だ年間総量3.6万トンの不法投棄が行われているのが現状のようだ。
平成28年においては、廃家電の回収率向上に向けたアクションプラン及び取組状況の検証に関する検討会がおこなわれた。ここでは、家電リサイクル法が施行されてから13年が経過していることを受けて、評価や見直しがされている。
このように、時代背景やこれまでの実践によるフィードバックからも、制度は常に見直されている。なお、討論会の取りまとめついては、以下のリンクから見ることができる。
調査結果
さらに、定期的な議論だけでなく、不法投棄などの状況に関しても毎年の調査がおこなわれており、調査結果を公表している。それだけでなく、都道府県などの今後の対応方針に関する調査なども取りまとめており、かなり慎重に社会問題に取り組んでいると考えられる。
もっとも最新の平成29年度におこなわれた調査報告については、以下のリンクより確認ができる。
義務付け対象
製造業者などに一定水準以上のリサイクル(再商品化など)を義務付けされている。その他の者に対しては、リサイクルの義務はない。ただし、廃棄物処理法は、廃棄物を処理する全ての者へ義務付けされている点は注意が必要だ。
現在の家電リサイクル状況
家電の排出には、主に処分と買い替えがある。小売店で新しい家電を購入しその際におこなう買い替えの場合は、小売店による家電リサイクル法に沿った処理がおこなわれている。現在、家電リサイクル回収率の目標値を設定している。
家電リサイクル法の対象
製品に「家庭用」と記載されている、家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)が対象である。家庭用機器は、事業所で使用していても、家電リサイクル法による処分が必要である。これらの排出については、変則として、家電リサイクル法に基づき、リサイクル料金と収集運搬料金は必要となる。
また、これらの廃棄方法については、以下の4つに定められている。
- ・新しい製品に買い換える際には、新しい製品を購入する小売業者に取引を依頼する。
- ・処分する製品を購入した小売業者がわかる場合には、処分する製品を購入した小売業者(家電4品目の小売販売と行としておこなうもの)に取引を依頼する。
- ・産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定取引場所への運搬をおこない、または排出業者自ら指定取引場所への運搬をおこない、製造業者などに引き渡す。この際には、有料の家電リサイクル券が必要となる。
- ・廃棄物処理法に基づき、適切な処理をおこなうことができる産業廃棄処分許可業者により処分をおこなう。この際には、産業廃棄物の処分をおこなう業者が適切な処分方法をおこなっているか確認する必要がある。
詳細については、環境省が作成した書類で確認することができ、以下のリンクから飛ぶことが可能だ。
また、それぞれの家電の家電リサイクル法の適用についても確認していく。
エアコン
エアコンの室内機だけでなく、室外機・エアコン付属のリモコン・室内機の純正取付部材・商品に梱包された工事部材も含まれる。判断基準はエアコン室内機が家電リサイクル法に該当するかどうかで、室内機が家電リサイクル法に該当しない場合は、室外機やリモコンその他の部品も該当しない。
- ・壁掛けのセパレート型・ガスヒーターエアコン・ハイブリットエアコン(石油・ガス・電気併用)
- ・マルチエアコン
- ・床置きセパレート式・ハイブリットエアコン(石油・ガス・電気併用)
- ・ウインド型
テレビ
テレビのみではなく、テレビに付属したリモコン・着脱式付属専用スピーカー・電気コードやスタンドなどの付属品も含む。
- ・ブラウン管テレビ
- ・ブラウン管式VTR内蔵型テレビ
- ・ラジカセ一体型テレビ
- ・液晶・プラズマテレビ
- ・液晶・プラズマHDD・DVD一体型テレビ
- ・チューナー分離型テレビ
冷蔵庫
冷却や制御に電気を使用するもの(ガスなどの併用を含む)、冷温庫は温める機能があるが、対象品に含まれる。
- ・冷蔵庫
- ・冷凍冷蔵庫
- ・ワインセラー
- ・保冷庫
- ・冷温庫
- ・チェスト型冷凍庫
- ・アップライト型冷凍庫
- ・引き出し型冷凍庫
- ・商品同梱の付属品(製氷皿、棚、野菜カゴなど)
- ・吸収式冷蔵庫(冷媒にアンモニアを使用)
- ・ペルチェ素子方式冷蔵庫(一部メーカーでは「電子冷蔵庫」)
- ・ポータブル冷蔵庫(車載含む)
なお、家庭用業務用分類分類については以下が参考となる。
洗濯機
洗濯機は以下の通りだ。
- ・洗濯乾燥機
- ・全自動洗濯機
- ・2槽式洗濯機
- ・小型洗濯機(排水機能があるもの)
- ・電気衣類乾燥機(ドラム式)
- ・ガス衣類乾燥機
- ・商品同梱の付属品
家電リサイクル法対象外のもの
家電リサイクル法が適用されないものもある。そこで、対象外のものをピックアップしていく。
空調機器
エアコンもしくはエアコン類似の空調機器で対象外のものは次の通りだ。
- ・天井埋め込み型
- ・壁埋め込み型
- ・天吊型セパレート式
- ・パッケージエアコン
- ・冷風機
- ・ウインドファン
- ・除湿機
- ・リモコン付属の乾電池
- ・室外機の置き台や屋根
- ・ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニット
- ・印刷物
- ・外付けコインボックス
テレビ
テレビもしくはテレビ類似の製品で家電リサイクル法対象外のものは次の通りだ。
- ・リモコンの電池
- ・パソコン関連のディスプレイモニター(パソコンリサイクル対象)
- ・車用液晶テレビ
- ・充電式携帯用テレビ
- ・建物組み込み型の液晶テレビ
- ・一次電池や充電池を使用するテレビ
- ・有機ELテレビ
- ・コインボックス内蔵型テレビ
- ・プロジェクションテレビ
冷蔵庫
冷蔵庫もしくは冷蔵庫類似の製品で家電リサイクル法対象外のものは次の通りだ。
- ・業務用冷蔵庫
- ・おしぼりクーラー
- ・保冷米びつ
- ・ショーケース(店舗用)
- ・冷凍ストッカー(店舗用)
- ・取扱説明書などの印刷物
- ・ホテル用システム冷蔵庫(課金式)
- ・冷水機
- ・製氷機
- ・化粧品専用の保冷庫
洗濯機
洗濯機もしくは洗濯機類似の製品で家電リサイクル法対象外のものは次の通りだ。
- ・衣類乾燥機付き布団乾燥機
- ・衣類乾燥機能付きハンガー掛け
- ・衣類乾燥機付き扇風機
- ・衣類乾燥機付き除湿機
- ・衣類乾燥機能付きハンガー
- ・電動バケツ(排水機能がないもの)
- ・脱水機
- ・衣類乾燥機置き台
- ・取扱説明書などの印刷物
- ・コインランドリーなどで使用のコインボックス内蔵型洗濯機・衣類乾燥機
- ・外付けのコインボックス
各種リサイクル法関連のリンク集
家電リサイクル法以外にも、そのほかリサイクル法が存在する。ここでは、参考になるリンクを掲載しておく。
- ・自動車(自動車リサイクル法の対象になるもの)→環境省 自動車リサイクル関連
- ・アルミ缶・スチール缶・ガラスびん・紙パック・ダンボール・紙製容器包装・パッとボトル・プラスチック(容器包装リサイクル法の対象になるもの)→容器包装リサイクル法とは
- ・食品(食品リサイクル法の対象になるもの)→農林水産省 食品ロス・食品リサイクル
- ・アスファルト、コンクリート、材木などの特定建築資材(建築リサイクル法の対象になるもの)→環境省 建設リサイクル法の概要
家電リサイクル法対象外の廃棄に関する法令
家電リサイクル法の対象とならない商品の排気に関しては、小型家電リサイクル法が適用される。これは、平成25年(2012年)4月に施行され、小型家電は自治体の回収ボックスや集積所で回収する決まりとなっている。
パソコンを含むほとんどの小型家電製品がその対象となる。回収場所の詳細については、以下のリンクから確認が可能だ。地図や品目などから検索をかけることができる。
家電リサイクル法に関連する法律として、以下のものがある。
廃棄物処理法
業務用の家電4品目は、家電リサイクル法の対象にならず、廃棄物処理法の対象となる。詳細は以下のリンクから確認できる。
オゾン層保護法
昭和元年(1989年)、特定物質の規制などによるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)が施行された。詳細は以下のリンクから確認できる。
フロン排出抑制法
家電リサイクル法に該当しない業務用冷蔵庫や業務用エアコンを廃棄するときには、フロン排出抑制法の規制を受ける。
平成27年(2014年)、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保などに関する法律(フロン回収・破壊法)が改正され、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が成立した。
資源有効利用推進法
平成13年(2001年)、資源の有効な利用の促進に関する法律が施行された。
家電リサイクル法対象外の商品の廃棄方法
家電リサイクル法の対象外である場合、廃棄物処理法に従い廃棄するが、小型家電リサイクル法やフロン排出抑制法、資源有効利用推進法の規制を受ける。特に、フロン類の環境破壊の度合いは深刻でありフロン排出抑制法の罰則規定は重いため、注意が必要である。ここでは、それぞれの廃棄方法を確認していく。
小型家電リサイクル法による廃棄
小型家電リサイクル法に該当する場合、各自治体により回収方法が若干違うため、先ほども紹介したのポータルサイトで個別に確認する必要がある。
廃棄物処理法・フロン排出抑制法による廃棄
廃棄物処理法とフロン排出抑制法に則る廃棄が必要である場合に、以下の方法がある。
- ・第一種フロン類充塡回収業者にフロンを回収してもらう方法
- ・産廃業者・リサイクル業者に製品をそのまま回収してもらう方法
の2つがある。
両者とも、法や条例規則に基づき引取証明書と、再生証明書もしくは破壊証明書をもらい、フロン排出抑制法に基づいた処理がなされたことを確認する必要がある。
まとめ
家電リサイクル法は不法投棄の対策や有用な資源を活用するために作られた。だが、家電リサイクル法対象外の商品についても、自動車リサイクル法、容器包装リサイクル法、食品リサイクル法、建築リサイクル法、小型家電リサイクル法などさまざまな法律によって処分方法が決まっている。
また、仮に消費者として物を処分してほしい場合にも、違法の回収業者に頼むことで思わぬトラブルに巻き込まれることがあるため注意が必要だ。
格安で回収してもらえたとしても、回収してもらったものが不法投棄されていたり、回収後に高額な料金を請求される危険性がある。特に不法投棄の場合に、持ち主に責任が問われるだろう。また、廃棄物処理法は、廃棄物を処理する全ての者へ義務付けされているため、注意が必要だ。
不用品を抱えず適切な処分をするためにも、しっかりと整理をおこなっていきたい。
この記事を監修した専門家