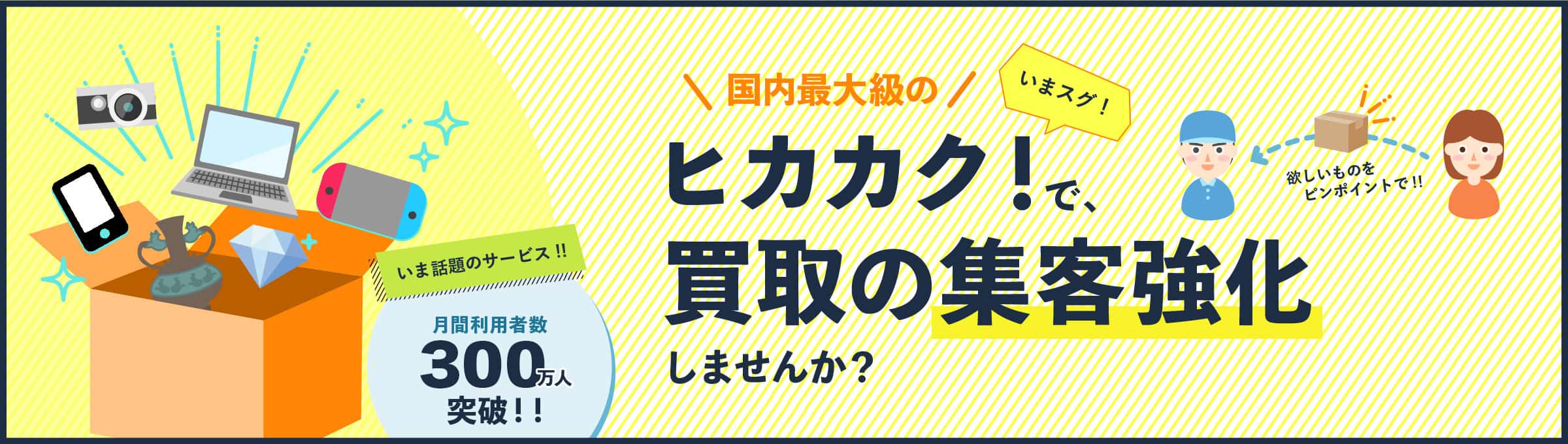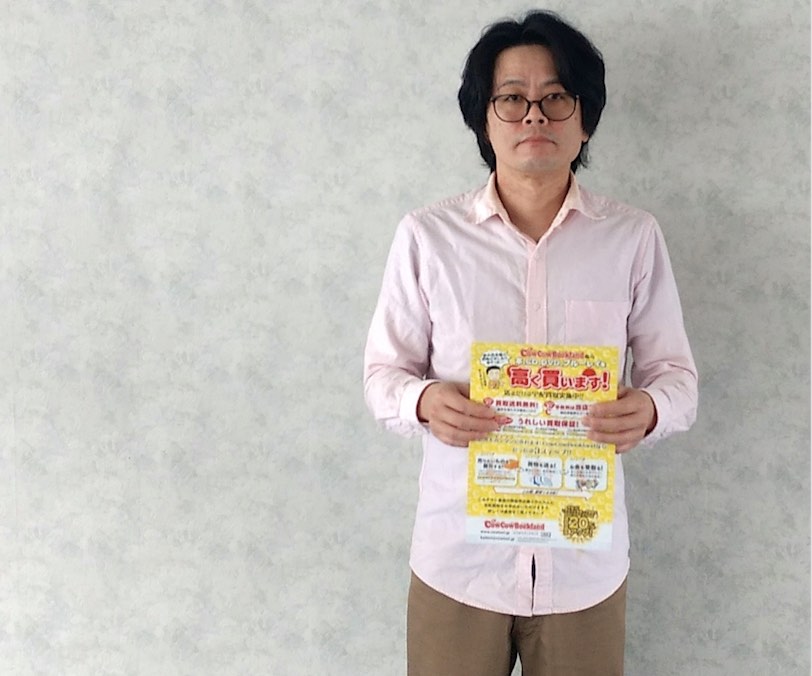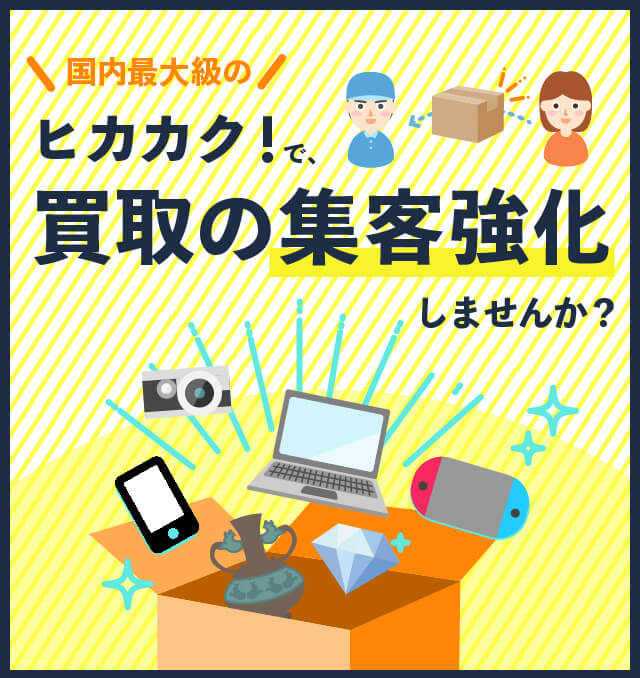買取事業者にとって、古物営業法は必ず理解しておきたい規制である。それには古物とは何か、古物営業とは何かをしっかりと押さえておく必要がある。
そして、古物営業法に違反した場合、どんな罰則や行政処分があるのかについても熟知しておきたい。そこで、ここでは古物とは何かからはじめ、古物営業の種類、古物営業法に違反したときの罰則と行政処分をまとめた。
また、具体的な逮捕事例も紹介していく。ネットオークションなど転売の場が急速に拡大している現在、どのような逮捕事例があるのかチェックしておこう。

CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
そもそも古物とは
古物営業法違反について知るためには、まず、古物とは何かについて知っておくことが重要だ。古物には古物営業法という規制があり、古物営業をする場合には、古物とは何かについてしっかりと把握していくことが必要となるからだ。逆に、古物に該当しなければ古物営業法の規制を受けないということになる。
古物営業法で古物と定められているものは「1度使用された物品(a)」「使用されていない物品で使用のために取引されたもの(b)」「aまたはbの物品に幾分の手入れをしたもの」である。aは観賞用の美術品をはじめとして、切手、乗車券、商品券などがある。また、船や飛行機、工作機械なども古物営業法の対象となる。
要するに、一度消費者の手に渡ったものが古物の対象となる。したがって、メーカーから卸売・小売といった流通段階にあるものは除かれる。
ここでいう「一度使用された物品(a)」の「使用」とは、その物本来の目的を満たす使い方のことだ。したがって、自転車ならば乗って移動することであり、衣類なら着ることが目的となる。つまり、その物本来の目的で使えないものは古物とは認められないのだ。
また、「使用されない物品で、使用のために取引されたもの(b)」という表現も分かりにくい言葉だ。これが該当するケースは、一度消費者の手に渡ったものの使用されず、新品のまま買取業者に売却したような場合である。
買い取り事業者やリサイクル業者は店頭あるいは、ヤフオク・メルカリなどのネットオークションに出品する場合があるだろう。この場合、新品であっても古物営業法の対象となるので注意が必要だ。
「aまたはbの物品に幾分の手入れをしたもの」の「幾分の手入れ」の意味もしっかりと押さえておきたい。幾分の手入れとは、その物本来の使い方や目的に変更がない範囲で行う修理や加工のことである。
たとえば、古くて動かない工作機械を、メンテナンスを行って使える状態にすることや、古本の側面をやすりがけしてきれいにするなどは「幾分の手入れ」にあたる。
古物とは何か理解できただろうか。このような古物および古物営業法に対する知識は、買い取り業者ならば必ず理解しておく必要がある。なお、大型機械の場合、20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両は古物に該当しない。
また、1トンを超える機械で、アンカーボルトなどで固定されていて簡単に取り外しができない機械、5トンを超える機械で自走できない・けん引できない物は古物から除外される。
古物営業の規定とは
古物営業のやり方には3つの規定がある。いずれかに該当する場合は公安委員会から許可を受ける、または届け出をすることが必要となる。
1号営業
「1号営業」は古物を売買したり交換したりする営業をすることだ。公安委員会からの許可が必要で、許可を受けた人を古物商とよぶ。委託を受けて売買したり交換したりすることも「1号営業」にあたる。
バッグや時計、靴など、海外で限定的に販売されている商品の入手を引き受けて利益を上げている古物商も多い。海外に買付にいく業者もあるが、なかにはネットオークションなどを駆使することにより、最小の労力で最大限の利益をあげる方法をとる業者もいるという。
ただし、リサイクルショップやフリーマーケット、バザーなどで行われている取引が古物営業にあたるかはケースバイケースとなっており、営利性などの観点から個別で判断されることになる。
2号営業
「2号営業」は古物商の人たちの間で古物の売買または交換を行う「古物市場」を経営することをいう。オークションのようなせり売りが一般的な古物市場の形式だ。
つまり、一般の人は参加できない市場ということになる。このような市場の営業を営む人を「古物市場主」と呼ぶ。古物市場主となるには公安委員会から許可を受ける必要がある。
古物せりあっせん業(3号営業)
「古物せりあっせん業(3号営業)」はインターネットオークションのような、古物を売買したい人のあっせん業務を行う営業のことだ。この営業を行う業者を古物せりあっせん業者と呼ぶ。
最近では、ヤフオクや、モバオク、eBayなど一般の人にとってもネットオークションの選択肢が増えてきている。複数のオークションやフリマアプリの相場をチェックすることは、高く売るための基本的なテクニックのひとつといえるだろう。
逆にいえば、一般の人は何を売りたいかを考えれば人が集まるということになる。不動産買取査定と買取オークションサイトとして成功している「さてオク」などはその一例といえるだろう。
古物営業法違反の罰則・行政処分
古物営業をする際に気を付けなければならないことが、古物営業法である。古物営業法を違反すると罰則や行政処分がある。どのような処分になるのか紹介しようと思う。
違反した場合の罰則
古物営業法に違反した場合の罰則は古物営業法に定められており、以下の通りとなっている。
無許可営業の場合
「無許可営業」の場合、「懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科」。
名義貸しの場合
「名義貸し」の場合「懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科」。
取引場所の制限違反の場合
「取引場所の制限違反」の場合「懲役1年以下または50万円以下の罰金もしくは併科」。「取引場所」として許可されている場所は、営業している場所、つまり、古物商が古物商以外の人から古物を買い受けできる場所か、買い取りを依頼してきた相手方の住所の2つだ。
古物商市場における古物商間以外の取引の場合
「古物商市場における古物商間以外の取引」の場合は「懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金もしくは併科」。
古物許可証携帯義務違反と行商従業者証携帯義務違反の場合
「古物許可証携帯義務違反と行商従業者証携帯義務違反」の場合は30万円以下の罰金。
古物商許可標識掲示義務違反の場合
「古物商許可標識掲示義務違反」も同じく30万円以下の罰金と定められている。
その他
また「許可証の返納」「営業内容変更の届出」「許可証の携帯」「標識の掲示」「HPへの表示」などは10万円以下の罰金と定められている。
違反した場合の行政処分
古物営業法に違反した場合、2種類の行政処分が取られる。
許可の取り消し
1つは「許可の取り消し」である。これは偽りや不正な手段で許可を受けていた場合や、許可を受けてから6カ月以上に渡り古物営業を行った形跡がない場合に取られる行政処分である。
また、3カ月以上所在が不明になったときもこの行政処分の対象となる。許可の欠格事由に該当することが判明した場合や公安委員会の処分に違反した場合も、この処分が下されることがある。
営業停止
2つめの行政処分は「営業停止」である。営業停止の期間は6カ月以内と定められている。この行政処分が適応される事例は、古物商またはその従業員が古物営業法などに違反する行為を行ったときと定められている。
また、盗品等の売買の防止措置が取られていない場合、盗品等の速やかな発見が阻害されていると認められる場合も営業停止の処分が下される。
指示
また「指示」という行政処分もある。これは、営業停止の原因となる行為に対し、公安委員会が文書で違反行為を戒める場合である。
古物営業法違反の逮捕事例
ここでは古物営業法違反の逮捕事例をいくつか紹介する。現在の特徴としては、骨董店やリサイクルショップ、着物の買取業者などが逮捕される事例より、一般人が逮捕される事例が目立つ傾向がある。
これは、インターネットを通じて手軽に転売ビジネスが始められるようになった事情があるだろう。しかし、ビジネスの幅が広がることによって古物営業法違反が適応される範囲も広がっているので、プロの買い取り業者やネットオークションを経営している会社なども逮捕事例をしっかりチェックしておきたいところだ。
コンサートチケットの転売
古物商の資格を持っていない一般人がコンサートチケットを転売したとして逮捕されている。2016年9月に、香川県在住の当時25歳の女性が、アイドルグループである「嵐」のコンサートチケットを転売したとして、古物営業法違反で逮捕された。
この女性は、2015年の11~12月に「嵐」のチケット5枚をネットオークションを通じて出品、札幌市の女性らに約7万円で転売していた。この女性は過去にも同じ方法でチケット約300枚を転売し、合計1,000万円以上の利益を得ていたということである。
この女性は「無許可営業」によって逮捕されている。つまり、古物商の資格を持っていれば、転売はなんら問題のない行為である。また、一般人がコンサートに行けなくなったからヤフオクやチケットショップに売るのは全く問題ない。
しかし、「せどり」や「転売目的」で商品を仕入れた場合には古物として扱われるため、古物商の許可が必要となる。この女性の場合、明らかに転売ビジネスとしてコンサートチケットを入手している。よって、逮捕されたというわけだ。
現在は買取業者の選択が非常にたくさんある。そのため、一般人でも、保証書や箱など付属品を揃えておくなど、少し工夫するだけで高く買い取ってもらうことが可能だ。
必要なくなったらオークションサイトで売る方法や、古本・ゲーム・CDなどは「ネットオフ」、パソコン・家電なら「じゃんぱら」など得意分野をもつショップで高く買い取ってもらう方法もある。
買取価格
スピード
手数料
許可番号
ポリシー
ウイルス
対策
買取価格
スピード
手数料
許可番号
ポリシー
ウイルス
対策
そのため、「転売」という敷居が低くなってきていることは事実だ。しかし、ビジネスで行うならば、古物商の資格が必要であることを忘れてはならない。
盗難品の譲受で逮捕
古物商の資格を持っていても逮捕されるケースがある。古物営業でリサイクルショップを行っていた人が、盗難品を譲受した容疑で逮捕された。このケースは初犯であり、過去に問題のある営業を行っていなかったため執行猶予となる見込みであるとのことだ。
このような場合、通常、数日~数カ月間の営業停止処分となり、その後は営業を再開できるのが一般的だ。しかし、悪質な場合は免許取り消しとなる場合もある。その場合、執行猶予期間終了後に再度取得申請が可能だ。
本人の言い分によると、盗難品と知らずに製品を引き取ってしまったとのことらしい。このような事はリサイクルショップや骨董店、ブランド品の買い取り業者など、あらゆる古物商の身にも起こり得る。買い取りを行う場合には、身分証の確認をしっかりと取る、盗品の疑いのある持ち込みは受け付けないなどの基準を設けておくことも重要となるだろう。
まとめ
古物営業には1号営業、2号営業、3号営業があり、いずれかに該当する場合は公安委員会から許可を受ける、届け出をすることが必要となる。
また、古物営業法に違反すると罰則や行政処分を受けなければならず、罰則で一番重い刑だと「懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科」であり、一番軽くても「10万円以下の罰金」となっている。行政処分では「許可の取り消し」「営業停止」「指示」がある。
最近はインターネットを通じて転売ビジネスが始められるようになったため、一般人が逮捕される事例が目立つ。古物営業法について買取業者だけではなく、一般人でも違反しないように理解することが重要である。